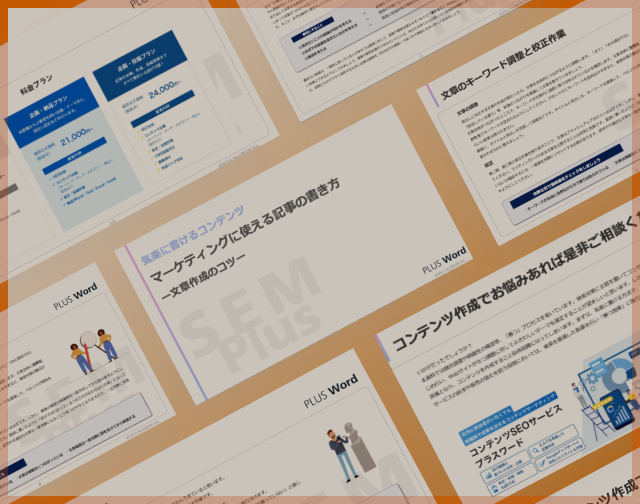専門学校のWEB集客における記事作成(コンテンツSEO)のポイント

「専門学校のWEB集客ではどのような記事を作成すれば良いのか」「どのようにコンテンツSEOを進めれば良いのか」などお悩みではないでしょうか?本記事では、専門学校がWEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法、記事作成の流れなど、初めてWEB集客に取り組むWEBサイト運営者にも分かりやすく解説します。

専門学校のWEB集客で記事作成(コンテンツSEO)を行うメリット
専門学校のWEB集客で記事作成を行うメリットは、以下の通りです。
- 専門学校に関連するページが増えるためサイトの専門性が高まりSEOに効果的
- 専門学校に興味を持っている潜在層にアプローチができる
- 卒業後の仕事内容をイメージさせる事ができる
- SNSでの拡散や自然な被リンクの獲得に繋がる
- WEBサイトの情報が充実し専門学校の認知度拡大や信頼性向上に繋がる
専門学校に関連するページが増えるためサイトの専門性が高まりSEOに効果的
専門学校のWEB集客で記事作成を行うメリットの1つ目は、専門学校に関連するページが増えるためサイトの専門性が高まりSEOに効果的であることです。
WEBサイトの専門性は、GoogleのGoogle検索品質評価ガイドラインに掲載されているE-E-A-Tのひとつです。コンテンツの質を評価する指標として利用されているため、専門性を高めることでSEOにおいて一定の効果が期待できます。
コンテンツSEOを実施する過程において、専門学校に関連するページを増やすようにすれば、Googleから専門性が高いサイトだと判断されやすくなります。専門性の高さは他のサイトとの相対評価なので、どのくらいのページを作成すれば専門性が高いと判断されるのかは扱うテーマ次第です。
専門学校のWEBサイトの場合、「専門学校」としての専門性というより、どのジャンルの専門学校なのかが専門性に影響します。
デザイン系の専門学校であれば「デザイン」、語学系の専門学校なら「語学」といったように、扱うジャンルに関するページを作成することで、そのジャンルに関する専門性が高いと判断されます。
専門学校に興味を持っている潜在層にアプローチができる
専門学校のWEB集客で記事作成を行うメリットの2つ目は、専門学校に興味を持っている潜在層にアプローチができることです。
▼ 見込み顧客は以下のように分類されます。
| 顕在顧客 | ・専門学校を比較・検討している ・専門学校について情報収集している ・専門学校への入学を検討している |
| 潜在顧客 | ・特定の職業に興味がある ・特定の職業に就く方法を調べている |
具体的に言えば、「美容師になるために専門学校に入学したい」、「どこの専門学校が良いだろうか」と検討している人が顕在顧客です。
一方、美容師になってみたいと考えているものの、「どうすれば美容師になれるのか分からない」、「どのような方法で美容師を目指すのか検討している」段階の人は潜在顧客となります。
顕在顧客は専門学校に入学したいという明確な意欲があるため、「美容専門学校 おすすめ」といったようにキーワードが選定しやすく、リスティング広告やMEO対策の方が効果的とされています。
一方、潜在顧客はまだ専門学校に入学するという結論には至っていない段階のため、さまざまなキーワードで検索するケースが多いです。すべてのキーワードに対して広告を出稿するとコストがかかる上に、問い合わせに結びつく可能性も低く費用対効果が悪いです。
コンテンツSEOであれば記事を増やすことでさまざまなキーワードにも対応でき、潜在顧客に対して効率良くアプローチできます。
卒業後の仕事内容をイメージさせる事ができる
専門学校のWEB集客で記事作成を行うメリットの3つ目は、卒業後の仕事内容をイメージさせる事ができることです。
▼ 専門学校には、以下のようにさまざまな種類があります。
- 国家資格・公的資格取得系
- 語学系
- 医療系
- 美容系
- 観光・エアライン系
- ホテル・ブライダル系
- コンピューター系
- デザイン系
いずれの専門学校も、特定の職業に就くことが前提となっています。
専門学校に入学したいと考えて専門学校のWEBサイトを訪問する人、つまり顕在顧客は、卒業後の仕事内容はある程度イメージできている状態です。
一方、潜在顧客には特定の職業に対して憧れや興味はあるものの、まだ具体的な業務内容や年収などについては詳しく知らないケースも想定されます。
専門学校のWEBサイトで卒業後の職業について詳しく解説した記事を掲載しておくことで、上記のような潜在顧客へアプローチできます。専門学校の必要性やメリットを提示することで、問い合わせに繋げられるでしょう。
SNSでの拡散や自然な被リンクの獲得に繋がる
専門学校のWEB集客で記事作成を行うメリットの4つ目は、SNSでの拡散や自然な被リンクの獲得に繋がることです。
専門学校のWEBサイトでコンテンツSEOを実施することで専門学校の知名度が高くなれば、SNSや外部サイトで専門学校が話題になることでサイテーションを獲得できたり、外部サイトで紹介されることで被リンクを獲得できたりする機会が増加します。
サイテーションや被リンクを獲得することはGoogleからの評価を高める効果もあるため、SEO対策としても効果的です。
WEBサイトの情報が充実し専門学校の認知度拡大や信頼性向上に繋がる
専門学校のWEB集客で記事作成を行うメリットの5つ目は、WEBサイトの情報が充実し専門学校の認知度拡大や信頼性向上に繋がることです。
専門学校のWEBサイトでコンテンツSEOを実施した結果、さまざまなキーワードで検索上位表示でき、検索流入を確保できるようになれば、専門学校もしくは専門学校のWEBサイトで扱うコンテンツに興味があるユーザーに対する認知度が向上します。
また、専門学校のWEBサイトで経営理念や進学実績などの情報を充実させれば、見込み顧客からの信頼性を高めることができ、問い合わせに繋がりやすくなります。
専門学校の記事作成におけるキーワード選定の方法
専門学校のキーワード選定では、顕在顧客と潜在顧客が検索時に使用する可能性が高いキーワードを選定します。顕在顧客向けのキーワードは、専門学校が扱うジャンルと地域名を組み合わせたものです。
たとえば、福岡にある税理士専門学校であれば以下のようなキーワードになります。
- 「税理士 専門学校 福岡」
- 「税理士 専門学校 福岡 学費」
- 「税理士 専門学校 福岡 おすすめ」
- 「税理士 専門学校 福岡 社会人」
- 「税理士 専門学校 福岡 高卒」
一般的に顕在顧客は自身が通える範囲の専門学校を探すため、検索キーワードには地域名を含めなければいけません。福岡市だけでなく久留米市や北九州市にも学校がある場合には、それぞれの地域名をキーワードに含めます。
上記のようなキーワードは検索ボリュームは少ないものの、明確な目的を持って検索しているため問い合わせに繋がる可能性が高いです。一方、潜在顧客は専門学校に行って勉強したいという結論に至っていない段階なので、キーワードに「専門学校」や地域名のキーワードを含める必要はありません。
税理士に興味を持つ潜在顧客が、検索時に使用するキーワードを選定します。
- 「税理士 年収」
- 「税理士になるには」
- 「税理士 資格」
- 「税理士と会計士の違い」
- 「税理士 仕事内容」
問い合わせに直結するキーワードではありませんが、リードナーチャリングを実施することで問い合わせを得る可能性が高くなります。また、キーワードに「税理士」というキーワードが含まれるため、税理士の専門学校としての専門性が高くなり、ブランディングにも繋がります。
ただし、上記キーワードは日本国内に住む潜在顧客が使用するキーワードなので、特定の地域だけで運営している専門学校の場合、集客効果が低くなる可能性があります。
大阪に住んでいる潜在顧客が「税理士になるには」というキーワードで検索してWEBサイトを訪問しても、学校が福岡県内にしかなければ通学する可能性は低いからです。
専門学校関連の記事作成ポイント11選
専門学校関連の記事作成ポイントは、以下の通りです。
- コース・学科にあわせたテーマを設定する
- ターゲットが読みやすい文章構成、文章にする
- 入学後の不安を払拭できる情報を入れ込む
- 生徒から親までが見ることを意識したトーン&マナーで作成する
- 記事内にコースや学科を紹介するページへのリンクを設置する
- 記事の末尾に自校の紹介文をまとめる
- 記事の著者情報を記載する
- 学校の様子が分かる動画を記事で紹介する
- 在校生や卒業生のインタビューを紹介する
- 学科が多い場合は科目ごとにカテゴリを分けておく
- テーマを幅広く扱う場合はタグを使用する
【ポイント①】コース・学科にあわせたテーマを設定する
専門学校関連の記事作成ポイントの1つ目は、コース・学科にあわせたテーマを設定することです。専門学校への入学を検討している人は、どこの専門学校が良いかよりどのジャンルを扱う専門学校なのかを基準に選定するケースが一般的です。
医療系の専門学校にするか美容系の専門学校にするか悩むケースは少なく、検索する際にも、「理学療法士 専門学校」や「美容師 専門学校」といったように卒業後の職種名を入れるケースが一般的です。
専門学校で扱うコースや学科をカテゴリに設定しておくことで、上記のようなキーワードにも対応できます。
【ポイント②】ターゲットが読みやすい文章構成、文章にする
専門学校関連の記事作成ポイントの2つ目は、ターゲットが読みやすい文章構成、文章にすることです。高校卒業後に入学する専門学校では保護者がオープンキャンパスに同伴するケースも多く、入学を検討している学生だけでなく保護者もどのような学校なのか関心を持っています。
記事のテーマによっては保護者自身が検索して記事を読む可能性もあるため、学生と保護者ともに読みやすい構成や執筆文章を心掛けることが重要です。
【ポイント③】入学後の不安を払拭できる情報を入れ込む
専門学校関連の記事作成ポイントの3つ目は、入学後の不安を払拭できる情報を入れ込むことです。専門学校を比較検討している段階において最も重視されるのは、目指す職業に就くことができるだけの知識やスキルを身に付けられるのか、実際に就職できるのかです。
入学後に就職できる見込みがないなら、大学や短大を選ばずに専門学校に入学する意味は全くないので、入学後の不安は払拭しておかなければいけません。
学生が安心して入学できると感じられるような情報を掲載しておくことで、問い合わせを獲得できる可能性を高めることができます。
【ポイント④】生徒から親までが見ることを意識したトーン&マナーで作成する
専門学校関連の記事作成ポイントの4つ目は、生徒から親までが見ることを意識したトーン&マナーで作成することです。前述したように、専門学校のWEBサイトは入学を検討している学生だけでなく保護者も閲覧する可能性があります。
学生だけに限らず、保護者が読むことも踏まえたトーンで執筆するようにしましょう。
【ポイント⑤】記事内にコースや学科を紹介するページへのリンクを設置する
専門学校関連の記事作成ポイントの5つ目は、記事内にコースや学科を紹介するページへのリンクを設置することです。トップページに限らずどの記事からWEBサイトへ流入した場合でも、他のページへ移動できるリンクが設置されていなければ、読者は他のページを閲覧することはできません。
記事内にコースや学科を紹介するページへのリンクを設置することで、コースや学科を紹介するページへ移動することができるようになりますが、コースや学科を紹介するページ以外のページを閲覧することができなくなってしまいます。
ひとつの記事にすべてのページへのリンクを設置するとリンクだらけになってしまい、利便性を大きく損ないます。一般的には、記事内ではなくWEBサイトの上部にグローバルナビゲーションを設置します。
WEBサイトの主要なページへ移動できるカテゴリが表示されているため、読者は必要に応じて他のページへ移動できます。
【ポイント⑥】記事の末尾に自校の紹介文をまとめる
専門学校関連の記事作成ポイントの6つ目は、記事の末尾に自校の紹介文をまとめることです。記事の末尾には、記事全体の内容をまとめた内容を記述するより、読者に対して具体的な行動を起こさせる文章やリンクボタンを設置することをおすすめします。
適切な内容の記事であれば、記事の「まとめ」部分に来る前に読者が抱える疑問や問題は解決しているはずだからです。検索して記事を読む読者は問題や課題をすることが目的であり、コラム記事のように読むことが目的ではありません。
記事に書かれた内容では、課題を解決できなかった場合や読者に対して別の情報を提供することを目的として、他の記事やサービスページ、資料ダウンロードページへのリンクボタンを設置することが重要です。
専門学校へ入学することが課題解決の手段であれば、記事の末尾に自校の紹介文を掲載するようにしましょう。ただし、文脈を無視して読者が求めていないリンクボタンや自校の紹介文を掲載しても、読者が期待するような行動を取ってくれるとは限りません。
読者にどのような行動を起こさせることがベストなのかを検討したうえで、最適なCTAを設置することが重要です。
【ポイント⑦】記事の著者情報を記載する
専門学校関連の記事作成ポイントの7つ目は、記事の著者情報を記載することです。Googleは誰が記事を書いたのかもコンテンツの質を評価する指標としているため、記事の著者情報を記載することはSEO対策として効果的です。
有名な講師や受賞歴のある講師がいるかは専門学校を選定する際に重視されるため、講師が記事を書くことで問い合わせを獲得できる可能性を高めることができるでしょう。
ただし、有名な講師や受賞歴のある講師が在籍している場合でも、講師が実際に記事を書いていない場合には、記事の著者を講師としてはいけません。
学生が入学して講師に確認すれば実際に記事を書いたのかは確認できてしまいます。SEO効果を期待して架空の著者情報を掲載すれば読者や学生だけでなく、社会的な信頼を失ってしまうかもしれません。
【ポイント⑧】学校の様子が分かる動画を記事で紹介する
専門学校関連の記事作成ポイントの8つ目は、学校の様子が分かる動画を記事で紹介することです。コンテストの様子や授業風景などのように、文章や画像だけでは十分に情報を伝えられない場合には、動画を撮影して設置することで読者にリアルな情報を伝えられます。
動画は、文章よりも記憶の定着率が2倍、画像の7倍・文章の5,000倍の情報量を持つと言われているコンテンツです。モバイルでの視聴にも向いているため離脱に繋がりにくく、SNS拡散が期待できるなどのメリットもあります。
【ポイント⑨】在校生や卒業生のインタビューを紹介する
専門学校関連の記事作成ポイントの9つ目は、在校生や卒業生のインタビューを紹介することです。専門学校への入学を検討している学生の不安材料として、学校に馴染めるのか、卒業後はどのような仕事をするのかがあります。
前述した学校の様子が分かる動画を作成するとともに、在校生や卒業生へのインタビュー動画を作成することで、文章だけよりも在校生がどのように学校生活を送っているのか、卒業後にどのような仕事をしているのかをリアルに伝えることができます。
【ポイント⑩】学科が多い場合は科目ごとにカテゴリを分けておく
専門学校関連の記事作成ポイントの10つ目は、学科が多い場合は科目ごとにカテゴリを分けておくことです。
カテゴリ分けの例
■ 学部・学科紹介
- 声優・エンターテイナー学部
- 芸能スタッフ部
- アニメーション学部
- クリエイター学部
- ゲーム学部
- こども学部
【出典】代々木アニメーション学院「学部・学科紹介」
■ 学科&コース・資格
- カットコース
- トータルビューティ
- コース
- 選択授業
- 通信課程
- 資格・検定
- 国家試験対策
【出典】福岡美容専門学校「学科&コース・資格」
【ポイント⑪】テーマを幅広く扱う場合はタグを使用する
専門学校関連の記事作成ポイントの11つ目は、テーマを幅広く扱う場合はタグを使用することです。カテゴリは階層構造にすることができるため、テーマが幅広い場合でも対応できます。
一方、階層構造にすることはできないものの複数のカテゴリを横断して記事を分類できるのがタグです。単純に幅広いテーマを扱う場合にはカテゴリだけの方が便利ですが、カテゴリとは別の方向性で記事を分類する必要がある場合にはタグを使用します。
専門学校に関する記事の推奨文字数と推奨記事作成数
専門学校の記事の推奨文字数は3,000文字~5,000文字、推奨記事作成数は50ページ~100ページです。日本人の平均読書速度は1分当たり600文字程度と言われており、記事の文字数が多すぎれば途中で離脱されるかもしれません。
記事の文字数を3,000文字~5,000文字にしておけば5分~8分程度で完読できるため、途中で離脱されるリスクを削減できます。
記事の文字数を増やすことで検索順位が上がりやすくなるといったことはないので、記事を作成する段階で無理に文字数を設定する必要はありません。記事を読んだ読者を満足させられるか、問い合わせに繋がる内容になっているかを意識して記事を作成しましょう。
一方、記事数については多すぎて問題になることはありません。扱うテーマごとにカテゴリで分類し、読者が記事を見つけやすくするようにしておきましょう。
専門学校のWEBサイトで扱うジャンル次第で大きく異なりますが、読者や検索エンジンから専門性が高いと判断されるためには最低でも50記事~100記事程度は必要です。競合サイトがどのくらいの記事数なのかを調査して記事数を決めるようにしましょう。
専門学校のWEB集客における記事作成の流れ
専門学校のWEB集客における記事作成の流れは、以下の通りです。
- キーワードとテーマを選定する
- 記事の構成を作成する
- 執筆をする
- 関連する画像を用意する
- 記事を公開する
STEP1. キーワードとテーマを選定する
専門学校のWEB集客における記事作成では、初めにキーワードとテーマを選定します。専門学校の記事作成において初めにキーワードを選定するのは、記事のターゲットを明確にするためです。
たとえば、税理士を目指す人は、以下のようにさまざまな人がいます。
- 高校・大学を卒業後に税理士を目指す人
- 在学中に資格の取得を目指す人
- 税理士事務所で働きながら資格の取得を目指す人
- 会社の税務担当者として働きながら企業内税理士を目指す人
- 専業主婦から一念発起して税理士を目指す人
キーワードを設定せずに税理士を目指す方法を解説しようとすると、誰に向けた記事なのかはっきりしない記事になってしまいます。一方、「税理士 主婦」や「税理士 会社員」といったようにキーワードを設定しておくと、具体的なターゲットをイメージしながら記事を作成できます。
資格の取得に充てられる時間やいつまでに合格を目指すのかなどそれぞれで状況が異なるため、万人に向けた記事を作成するより、ターゲットを絞って記事を作成した方が効果的です。
専門学校のWEB集客におけるキーワードの選定方法については、前述した「専門学校の記事作成におけるキーワード選定の方法」で確認してください。
STEP2. 記事の構成を作成する
次に、専門学校の見込み顧客へ向けたキーワードとテーマを元に、記事の構成を作成します。記事の構成を作成する上で重要なことは、検索ユーザが求める情報は前半に、問い合わせを獲得するための情報は後半に配置することです。
検索ユーザーは、悩みや疑問を解消したり必要な情報を得たりすることを目的として検索しているので、記事の冒頭部分にCTAを設置しても効果的ではありません。
検索ユーザーが求める情報を提供した後に、課題を解決する方法としての情報を提供し、問い合わせに結びつける必要があります。
STEP3. 執筆をする
次に、作成した記事の構成に従って、専門学校の見込み顧客へ向けて記事を執筆します。専門学校のWEBサイトに掲載する記事を執筆する際のポイントは、読者に信頼性や権威性があると感じさせる文体にすることです。
専門学校への入学を検討する人のほとんどは将来専門職に就くことを目指しており、真剣な気持ちで記事を読みます。多くの人にとって就職は人生において重要な出来事であり、記事に書かれている内容や表現が適当なものであれば、安心して入学できると感じてはもらえないでしょう。
見込み顧客に対して、信頼感・安心感を与えることを意識して執筆することが重要です。
STEP4. 関連する画像を用意する
次に、専門学校の記事の内容と関連する画像を用意し、サムネイル画像とアイキャッチ画像を作成し、記事に設置します。
▼ 専門学校のWEBサイトに掲載する主な画像は、以下の通りです。
- 授業風景
- 講師
- 学校の外観
- アクセスマップ
- 授業で使用する教材・制作物
記事に画像を設置する際には、altタグで画像の内容が分かるテキストを設定しておく必要があります。
STEP5. 記事を公開する
最後に、完成した記事を専門学校のWEBサイトで公開します。記事を公開する前に、公開しても問題がないかプレビューなどで確認しておくことが重要です。
【公開する前のチェックポイント】
- スマホで閲覧した際にレイアウトが崩れていないか
- パーマリンク設定は適切か
- ディスクリプションは設定しているか
- 誤字脱字はないか
- 外部サイトをコピペしていないか
- 内容に間違いはないか
- レギュレーションに沿った文章になっているか
専門学校の記事作成の注意点
専門学校に関する記事を作成する際の注意点は、以下の通りです。
- カテゴリのテーマを狭くしすぎない
- コピーコンテンツを作成しない
専門学校のWEBサイトでコンテンツSEOを実施するコツ・ポイントは、以下の通りです。
- 中長期的な視点の施策と捉える
- 定期的にリライトを行う
関連する記事のテーマを狭くしすぎない
専門学校に関する記事を作成する際の注意点の1つ目は、カテゴリのテーマを狭くしすぎないことです。
サイトのカテゴリ分けでなく記事コンテンツのカテゴリを分ける目的は、複数の記事の中から目的の記事を見つけやすくすることです。カテゴリのテーマを狭く設定してしまうと、そのカテゴリに分類できる記事がほとんどなくなり、カテゴリ分けした意味がなくなってしまいます。
該当する記事がそれほど多くない場合は、他のカテゴリに分類できないかを検討してみましょう。
中長期的な視点の施策と捉える
専門学校のWEBサイトでコンテンツSEOを実施するコツ・ポイントの1つ目は、中長期的な視点の施策と捉えることです。コンテンツSEOは、リスティング広告やSNSアカウント運用のようにすぐに効果が見込める施策ではありません。
立ち上げたばかりのWEBサイトやコンテンツSEOをまだ始めていないWEBサイトの場合、ある程度の検索流入が見込めるようになるまでには半年~1年ほどかかる場合もあります。
一方で、リスティング広告やSNSアカウント運用では施策の実施を停止すれば集客効果もなくなってしまいますが、コンテンツSEOでは記事数が増加するごとに相乗的な効果が期待できる施策です。
検索流入だけを期待されやすいですが、ブランディング効果による影響も期待できるため、中長期的な視点の施策と捉えるようにしましょう。
定期的にリライトを行う
専門学校のWEBサイトでコンテンツSEOを実施するコツ・ポイントの2つ目は、定期的にリライトを行うことです。記事に掲載されている情報が古いままだと、記事を閲覧した読者は新しい情報を得るために検索し直して別のWEBサイトへ移動してしまうかもしれません。
たとえば、専門学校からの進学実績が数年前の情報のままにしていると、直近の情報を紹介すると都合が悪いのか、直近の進学率は低いのではないかと不安に感じさせてしまうこともあるでしょう。
専門学校では最新の知識を学習するケースも多いので、WEBサイトで扱う情報については常に鮮度を高め、トレンドを意識して記事を作成することが重要です。
記事の鮮度はGoogleも重視する要素なので、定期的にリライトを行うことでWEBサイトの評価が高くなり、検索上位表示されやすくなります。
コピーコンテンツに注意する
専門学校に関する記事を作成する際の注意点の2つ目は、コピーコンテンツを作成しないことです。専門学校に興味を持つユーザーは複数のWEBサイトを見る可能性が高く、自社の記事と他のWEBサイトの記事が似たような文章・内容であれば、違和感を感じるかもしれません。
記事の大半が他のWEBサイトの記事をコピペしたものであれば、信頼できない専門学校だと判断される恐れもあります。
第三者が作成した文章や画像を使用する場合は、引用のルールに従って引用元を記載しなければいけません。他のWEBサイトの記事を許可を得ずにコピペすると、著作権違反とみなされるケースもあります。
また、Googleからコピーコンテンツだと判断されると、ペナルティを受けて記事がインデックスから除外されたり、検索順位が大きく低下する可能性もあります。
専門学校の記事作成で参考になる例
【東京スポーツレクリエーション専門学校】

東京スポーツレクリエーション専門学校さんの記事は専門学校に入った後、「どのような仕事があるのか?」また、「その仕事につく事でどのくらいの収入が得られるのか?」を詳細に記載しています。これにより、将来就きたい仕事について調べている学生さんへの認知度を高めています。
また、その職業に就くために必要となる具体的な資格や、スキル、年収の上げ方も記載されているため専門性の高い記事となっています。
ツールを使ってオーガニックトラフィックを見ると、記事を入れてからトラフィック数が10倍以上になっているのが確認できます。

専門学校という記事のテーマ選定が難しいジャンルながら、記事作成で潜在層を多く獲得している良い例と言えます。
まとめ
今回は、初めてWEB集客に取り組む専門学校のWEBサイト運営者に向けて、WEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法、記事作成ポイント、推奨文字数と推奨記事作成数、記事作成の流れまで解説しました。
WEB広告やSNSアカウント運用などのWEB集客方法と比べると、コンテンツSEOは潜在顧客に対して効率良くアプローチできる施策です。検索ユーザーを意識した記事作成を継続的に実施することで、検索流入が期待できるだけでなく専門学校としてのブランディングにも繋がります。
本記事で解説した記事作成ポイントを参考に、コンテンツSEOに取り組んでみましょう。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
 コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/06/09
コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/09
コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/07/25
コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/07/252025/07/25
-
 コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/06/09
コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOロングテールキーワードとは|SEOで重要な理由と選び方を解説2025/06/09
コンテンツSEOロングテールキーワードとは|SEOで重要な理由と選び方を解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOWebライティングとは?手順やポイントを初心者向けに解説2025/06/09
コンテンツSEOWebライティングとは?手順やポイントを初心者向けに解説2025/06/092025/06/09