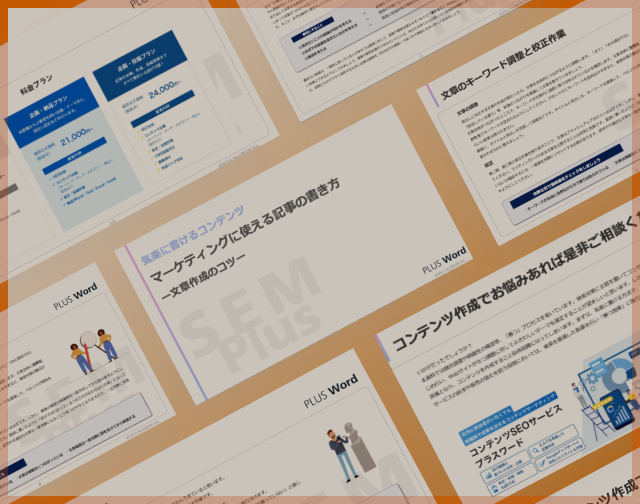学習塾のWEB集客における記事作成(コンテンツSEO)のポイント

「学習塾のWEB集客ではどのような記事を作成すれば良いのか」「どのようにコンテンツSEOを進めれば良いのか」など、お悩みではないでしょうか?この記事では、学習塾がWEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法や記事作成の流れまで、初めてWEB集客に取り組むWEBサイト運営者にも分かりやすく解説します。

学習塾がWEB集客で記事を作成(コンテンツSEO)するメリット
学習塾がWEB集客で記事を作成するメリットは、以下の4つです。
- 学習に関連するページが増えサイトの専門性が高まりSEOに効果的
- 学習塾に関心のある保護者や生徒へのアプローチができる
- WEBサイトの情報が充実するため認知度拡大に繋がる
- チラシに比べターゲットを絞った集客ができる
それぞれのメリットについて具体的に解説します。
学習に関連するページが増えサイトの専門性が高まりSEOに効果的
学習塾がWEB集客で記事を作成するメリットの1つ目は、学習に関連するページを増やすことで学習に関する専門性が高いと評価され、SEO効果が期待できることです。
学習塾が見込み顧客を集客する場合、志望校に関する情報や試験勉強など受験に関連するページを作成することになります。受験に特化したサイトになるので、ユーザーや検索エンジンから受験に関して専門性が高いと評価されるようになります。
ユーザーから専門性が高いと評価されればサイテーションや被リンクを獲得する機会が多くなり、検索エンジンからの評価が高くなります。また、Googleはコンテンツの質を評価する際の指標として専門性を用いており、サイトの専門性が高いと判断されればSEOにおいて有利に働きます。
学習塾に関心のある保護者や生徒へのアプローチができる
学習塾がWEB集客で記事を作成するメリットの2つ目は、学習塾に関心のある保護者や生徒へのアプローチができることです。
SNSやWEB広告で集客する場合、学習塾に興味がないユーザーまで集客することになるため、集客したユーザーのすべてが見込み顧客になるわけではなく、コンバージョンに結び付くとは限りません。
一方、コンテンツSEOは、学習塾に関心のある保護者や生徒へアプローチする集客方法です。見込み顧客だけを集客できるため、高いCVRが期待できます。
WEBサイトの情報が充実するため認知度拡大に繋がる
学習塾がWEB集客で記事を作成するメリット3つ目は、認知度拡大に繋がることです。
学習塾のサイトの場合「エリア+学習塾」など顕在層向けのキーワードでの集客が中心となりますが、潜在層向けのコンテンツを作成する事で幅拾いキーワードで集客をおこなう事が出来ます。
その結果、多くのユーザーの目に止まる事となり認知度拡大に繋がる可能性があります。また、WEBサイトの情報量が多くなれば、サイトの専門性が高くなるためサイト全体の評価が上がり、多くのキーワードで上位表示される可能性が高まります。
その結果、多くのユーザーがサイトを訪問するようになるため、学習塾の認知度が高くなります。
チラシに比べターゲットを絞った集客ができる
学習塾がWEB集客で記事を作成するメリット4つ目は、チラシに比べターゲットを絞った集客ができることです。
新聞の折り込みチラシ、ポスティングなどで集客する場合、学習塾に興味がないユーザーや学習塾を利用する可能性のないユーザーに対してもチラシを配布する事になります。
一方、学習塾に興味があるユーザーが検索するキーワードに合わせた記事を作成した場合、学習塾を探しているユーザーや情報収集をしているユーザーだけをターゲットにする事が出来ます。そのため、記事作成はチラシに比べてターゲットを絞って効率よく集客を行なう事が出来ます。
学習塾の記事作成におけるキーワード選定の方法
学習塾の記事作成におけるキーワード選定では、自分の子どもを学習塾へ行かせたいと考えている保護者と学習塾を利用する学生が検索エンジンで検索する際に利用するキーワードを選定します。
▼ 学習塾のWEB集客におけるターゲットは、大きく分けると以下の2つです。
- 顕在層:学習塾を積極的に探している
- 潜在層:学習塾の必要性を認識していないものの、利用する可能性がある
受験を控えて勉強をしているわけではない社会人や、受験する子どもがいない家庭などは見込み顧客ではないため、ターゲットにしても意味はありません。学習塾のキーワード選定では、上記のような顕在層及び潜在層にある見込み顧客を意識して選定する必要があります。
▼ 顕在層が検索時に使用する可能性が高いキーワードは、以下の通りです。
塾・学習塾・個人塾・進学塾・個別指導・マンツーマン指導・少人数
大学受験・高校受験・中学受験・高校生・中学生・小学生
○○高校受験・○○中学受験・○○大学受験
また、学習塾は子どもが通える範囲の中から選ぶ傾向にあるため、以下のように地域名を組み合わせて検索されます。
学習塾 小学生 練馬区 田柄
進学塾 高校受験 足立区
特定の地域だけで学習塾を運営している場合、「学習塾」や「学習塾 おすすめ」など、全国をターゲットにしたキーワードを選定しても効果的ではありません。
地域名を含めたキーワードを選定しておくことで、見込み顧客が「学習塾」や「学習塾 おすすめ」などのキーワードで検索した場合でも、ローカル検索機能により検索上位表示されやすくなります。
また、子どもを学習塾へ行かせようと考えていない潜在層へ向けたキーワード選定も重要です。「修悠館 偏差値」「修悠館高校 進学実績」といったキーワードを選定することで、潜在層を集客できるようになります。
学習塾の集客では「学習塾」といったキーワードを中心に集客することが多いですが、子どもを志望校へ行かせたいと考える保護者の心情から検索キーワードを選定することが重要です。
また、学習塾の認知度が高くなっている状況の場合には、自社が運営する学習塾の名前もキーワード選定で意識しておきましょう。
学習塾の記事カテゴリ例
学習塾のWEBサイトにおける記事カテゴリ例は、以下の通りです。
- 勉強法
- 学校について(難易度・特徴・費用など)
- 学習塾について(費用・選び方など)
- 中学受験
- 高校受験
- 大学受験
- 保護者(進学率・コミュニケーション方法・ほめ方など)
それぞれのカテゴリで、どのようなコンテンツを作成すれば良いのかを解説します。
勉強法
学習塾の記事カテゴリ「勉強法」では、どのような方針で生徒を指導するのか、どうやって生徒を合格させるのか、他の学習塾とはどこが違うのかについて解説します。
保護者からの問い合わせを獲得できるかに大きく関わるコンテンツなので、他の学習塾との差別化を意識することが重要です。
学校について(難易度・特徴・費用など)
学習塾の記事カテゴリ「学校について」では、学習塾で合格を目指す学校の難易度や特徴、入学費用を解説します。学習塾への入学を検討していない保護者や生徒でも、志望校の難易度や特徴、費用について調べる機会は多いです。
それぞれの学校について詳しく紹介することで検索流入が期待できるようになり、学習塾の必要性をアピールできればコンバージョンが獲得できる可能性が高くなります。
学習塾について(費用・選び方など)
学習塾の記事カテゴリ「学習塾について」では、どのような学習コースを用意しているのか、それぞれの費用はどのくらいか、どのような基準で選べば良いのかを解説します。
【例】
| 小学生コース | スタンダードクラス 中高一貫校向けクラス 英語学習クラス |
| 中学生コース | スタンダードコース トップ高校入試クラス |
中学受験
学習塾の記事カテゴリ「中学受験」では、中学受験に向けて、どのようなカリキュラムを用意しているのか、どのようなペースで学習するのかを解説します。
中学受験は公立中学校ではなく私立中学校や県外の難関校への受験が前提となるため、個別の学校に関するコンテンツや合格実績、合格した生徒の声などのコンテンツを作成するのもおすすめです。
高校受験
学習塾の記事カテゴリ「高校受験」では、高校受験に向けて、どのようなカリキュラムを用意しているのか、どのようなペースで学習するのかを解説します。偏差値別にコースを用意している場合には、詳しい学習内容が分かるようにしておきましょう。
中学受験と同様に、合格実績と合格した生徒の声もコンテンツとして作成することが重要です。また、特定のエリアで塾の運営をおこなっている場合は、よくある志望校についての記事を作成するのも有効です。
大学受験
学習塾の記事カテゴリ「大学受験」では、大学受験に向けて、どのようなカリキュラムを用意しているのか、どのようなペースで学習するのかを解説します。
大学受験では中学受験や高校受験より合格実績が重視される傾向にあるため、各大学に何人の生徒が受験して合格できたのか分かりやすく紹介することが重要です。
大学受験になると合格を目指す学校が全国を対象とするため、各大学の難易度や特徴、卒業後の就職先、大学出身の有名人など、幅広いテーマでコンテンツを作成できます。
保護者(進学率・コミュニケーション方法・ほめ方など)
学習塾の記事カテゴリ「保護者」では、志望校の進学率や子どもとのコミュニケーションの取り方、子どもの褒め方など、潜在層の保護者に向けた情報を発信します。
【コンテンツ例】
- 受験を控えた子どもとの接し方
- 中学受験の子どもをやる気にさせる方法
- 中学受験のメリット・デメリット
- 受験生の親がやってはいけないこと
学習塾の記事作成ポイント8選
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントは、以下の8つです。
- 簡潔かつ説得力のある文章で書く
- ターゲットにあわせたトーン&マナーで執筆する
- 塾の様子がわかる写真を挿入する
- 記事タイトルの書き方を工夫する
- 実際の講師が記事を作成するのもおすすめ
- 記事の著者情報を記載する
- 生徒の声や口コミを記事内で紹介する
- テーマを幅広く扱う場合はカテゴリを分けておく
それぞれのポイントについて具体的に解説します。
【ポイント①】簡潔かつ説得力のある文章で書く
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントの1つ目は、簡潔かつ説得力のある文章で書くことです。説得力のある文章とは、明確な事実に基づいた、論理的な文章です。
結論だけしか書かれていないと、内容が本当なのか読み手には判断できません。なぜそのような結論に至ったのか理由を説明し、事例を上げて理解しやすくする必要があります。
たとえば、「授業満足度98%」という文章を見ても、どうやって満足度を調べたのか、何人にアンケートしたのか、実際に何人が満足したのかは分かりません。数字だけあればいくらでも誤魔化すことができてしまいます。
実際に満足した生徒や保護者へ実施したインタビュー記事を掲載する、インタビューを動画で掲載するといった明確な根拠を提示し、説得力を高めることが重要です。
【ポイント②】ターゲットにあわせたトーン&マナーで執筆する
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントの2つ目は、ターゲットにあわせたトーン&マナーで執筆することです。
小学生や中学生が通う学習塾の場合、WEB集客のターゲットは保護者になります。学習塾に通うのは小学生や中学生ですが、決裁権は保護者にあるからです。
近年では小学生や中学生でもネット検索する機会はありますが、自分が通う学習塾を自分で検索して探す可能性は低く、自分だけで通うかどうかを決断するわけでもありません。子どもを学習塾へ通わせるかどうか、どこの学習塾に通わせるかは決裁権のある保護者が結論を出すことになります。
つまり、保護者向けのコンテンツについては、保護者を意識したトーンにする必要があるということです。
一方、中学受験や高校受験の勉強方法など、小学生や中学生に向けたコンテンツについては、保護者に向けたトーンにする必要はありません。
小学生や中学生を集客しても直接コンバージョンに繋がる可能性は低いですが、学習塾のサイトを訪問した生徒自身が学習塾を保護者に紹介する形でコンバージョンに繋がる可能性はあります。
上記のように、学習塾のコンテンツは、誰が検索するのか、誰が読むページなのかを意識し、ターゲットに合わせたトーンで執筆しなければいけません。
【ポイント③】塾の様子がわかる写真を挿入する
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントの3つ目は、塾の様子がわかる写真を挿入することです。学校なら授業参観などで授業の様子を確認する機会がありますが、学習塾の場合は保護者が授業の様子を確認する機会はほとんどありません。
中の様子が見えづらい学習風景などを写真を挿入することで、見学では見えない様子などを確認でき、保護者への安心にも繋がります。また、学習塾の経営者や授業を担当する講師の写真を掲載しておくことも効果的です。
再生時間が短くても動画を掲載しておけば、写真よりも高い効果が期待できます。
【ポイント④】記事タイトルの書き方を工夫する
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントの4つ目は、記事タイトルの書き方を工夫することです。学習塾で用紙している学習コースを紹介する記事の場合、記事のタイトルが長くなりやすいです。
例えば「【幼児向け】○○の○勉強方法を解説!~」「【大学受験】やる気のでる○○~」など、【】を使う等見やすさを重視することで、記事タイトルが読みやすくなります。
記事のタイトルだけでなく記事の見出しにおいても、ポイントや手順を解説する際に以下のように【】を使うことで統一感が生まれてすっきりした見た目になります。
| ポイント | 【ポイント①】簡潔かつ説得力のある文章で書く 【ポイント②】ターゲットにあわせたトーン&マナーで執筆する 【ポイント③】塾の様子がわかる写真を挿入する 【ポイント④】記事タイトルの書き方を工夫する |
| 手順 | 【STEP1】キーワードとテーマを選定する 【STEP2】記事の構成を作成する 【STEP3】執筆をする |
また、記事のタイトルや見出しにキーワードを入れておくことで、検索上位に表示されやすくなる効果も期待できます。
【ポイント⑤】実際の講師が記事を作成するのもおすすめ
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントの5つ目は、実際の講師が記事を作成することです。学習塾選びでは、生徒へ授業を行う講師の指導方法や人柄も重視されています。
文章には人柄が反映されることが多く、講師が記事を作成することで人柄やどんな学習環境であるかを伝えることができ、保護者や生徒へのアピールに繋がります。
講師の指導方法を解説した記事を掲載しておけば、学習塾を利用するかどうか迷っている保護者や生徒の決断を後押ししてくれるかもしれません。
【ポイント⑥】記事の著者情報を記載する
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントの6つ目は、講師の経歴や人柄が分かるコンテンツを作成することです。
前述したように、学習塾選びでは生徒へ授業を行う講師の指導方法や人柄も重視されており、講師ごとにコンテンツを作成することで、どのような講師なのか、子どもを任せても大丈夫なのか判断できるようになります。
近年では学習塾講師のトラブルも増加しており、受験に合格できるかと同じくらい講師の人間性も重視されています。講師について何も書かれていなければ、保護者が不安に感じて敬遠されてしまうかもしれません。
有名な講師や受賞歴のある講師が在籍している場合は、積極的にアピールすることが重要です。他の学習塾との差別化要素であり、コンバージョン獲得に大きく貢献するコンテンツなので、できる限り作成しておきましょう。
【ポイント⑦】生徒の声や口コミを記事内で紹介する
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントの7つ目は、生徒の声や口コミを記事内で紹介することです。学習塾選びでは、実際に受講した生徒の声や口コミも重視されています。
学習塾のWEBサイトには都合の良いことしか書かれていない、信用できないと考える保護者がほとんどだからです。実際に受講した生徒の声や口コミを記事内で紹介することで、学習塾のリアルな意見を伝えることができます。
ただし、SNSなどで噂されている学習塾の口コミを紹介するのはおすすめできません。実際に学習塾を利用した生徒へ学習塾側が直接意見を聞く必要があります。
テキストだけでは信憑性に欠けると思われる可能性があるため、生徒の写真も掲載する、生徒へインタビューした動画を掲載して生の声を伝えるといった工夫が効果的です。また、「〇〇塾 口コミ」といったキーワードでの検索流入も期待できます。
【ポイント⑧】テーマを幅広く扱う場合はカテゴリを分けておく
学習塾のWEBサイトにおける記事作成のポイントの8つ目は、テーマを幅広く扱う場合はカテゴリを分けておくことです。学習塾のWEBサイトで扱うテーマごとにカテゴリを分けておくことで、ユーザーが目的の記事に到達しやすくなります。
たとえば、コンテンツSEOを実施する段階で「受験」というカテゴリだけしか作成されていないと、中学受験や高校受験、大学受験も同じカテゴリ内に分類されてしまうため、ユーザーは求める記事を見つけるまでに時間がかかってしまいます。
中学受験を目指す小学生に向けた記事を「中学受験」もしくは「小学生」カテゴリに分類することで、サイトを訪れた小学生はカテゴリページの中から求める記事を探しやすくなるわけです。
また、カテゴリ分けを実施しておくことで、以下のような効果も期待できます。
- コンテンツを作成しやすくなる
- 検索エンジンがサイトをクロールしやすくなる
- 同じキーワードで記事を作成してしまうことが少なくなる
- カニバリの発生を防止できる
学習塾の記事の推奨文字数と推奨記事作成数
学習塾の記事の推奨文字数は3,000文字~5,000文字、推奨記事作成数は50ページ~100ページです。文字数が500文字や1,000文字程度だと記事を閲覧したユーザーは十分な情報を得られず、別の記事を探したり検索し直したりすることになり、満足度が低下する恐れがあります。
一方、記事の文字数が1万文字だと、記事が流し読みされてしまったり、情報量が多すぎて途中で離脱されたりするかもしれません。3,000文字~5,000文字で記事を作成することで、ユーザーの満足度と完読率のバランスが良くなり、コンバージョンを獲得しやすくなります。
文字数が多い方が検索上位表示されやすいと思われるかもしれませんが、Googleは文字数とコンテンツの質に関連性はないと明言しており、無理に文字数を増やす必要はありません。
ページ数については、少ないより多い方がSEOで有利に働き、検索流入やサイト内の巡回が増加します。サイトの専門性を高める必要性を考慮すると、最低でも50ページ、できれば100ページは作成しておくことをおすすめします。
ただし、低品質なページを量産することは、検索エンジンからペナルティを受ける可能性が高く、逆効果です。子どもを抱えた保護者がどのような記事を求めているのかを、どのようなキーワードで検索するのかを意識し、記事を増やすようにしましょう。
学習塾のWEB集客における記事作成の流れ
学習塾のWEB集客における記事作成の流れは以下の通りです。
- キーワードとテーマを選定する
- 記事の構成を作成する
- 執筆をする
- 関連する画像を用意する
- 記事を公開する
それぞれのステップでは何をするのか、どのような点に注意すべきかを解説します。
STEP1. キーワードとテーマを選定する
学習塾のWEB集客における記事作成では、初めにキーワードとテーマを選定します。
記事作成において、初めにキーワードを選定するのは、キーワードを設定せずに記事を作成すると、誰に向けた記事なのか、どのような情報を盛り込むのかが曖昧になってしまうからです。
▼ キーワード選定のポイントは以下の通りです。
- 検索上位表示の見込みがないキーワードを選定しない
- コンバージョンに繋がらないキーワードを除外する
- 同じ検索意図のキーワードを除外する
キーワードの選定方法については、前述した「学習塾の記事作成におけるキーワード選定の方法」で確認してください。
STEP2. 記事の構成を作成する
次に、学習塾の潜在顧客へ向けたキーワードとテーマを元に、記事の構成を作成します。構成を作成する際には、学習塾の競合サイトを確認し、情報が不足していないかを確認することが重要です。
サジェストキーワードや関連キーワード、共起語などから検索意図をくみ取り、必要な見出しを作成しつつ構成に入れ込むようにしましょう。
STEP3. 執筆をする
次に、作成した記事の構成に従って、学習塾の潜在顧客へ向けて記事を執筆します。
▼ 記事を執筆する際のポイントは以下の通りです。
- ターゲットにあわせたトーン&マナーで執筆する
- ターゲットキーワードを意識する
- 検索ユーザーの検索意図を意識する
- 結論から先に書く
STEP4. 関連する画像を用意する
次に、記事の内容と関連する画像を用意し、サムネイル画像とアイキャッチ画像を作成し、記事に設置します。
▼ 学習塾の記事で用意する画像は以下の通りです。
- 授業風景
- 経営者・講師の顔写真
- 学習塾の外観
画像は素材サイトでも入手できますが、可能な限り独自に撮影した画像を用意し、撮影することをおすすめします。
また、画像だけでなく、動画を記事に設置するのも効果的です。
STEP5. 記事を公開する
最後に、完成した記事を学習塾のWEBサイトで公開します。
▼ 記事を公開する前に、以下の点を確認しておきましょう。
- hタグとタイトルタグは適切に設定されているか
- パーマリンクを半角英数字で設定しているか
- メタディスクリプションは設定しているか
- 誤字脱字はないか
学習塾の記事作成で参考になる例
【栄光ゼミナール】

栄光ゼミナールのコラムは、表やイラストを使って作られているため読みやすくわかりやすいのが特徴です。テーマも有名大学に関する学習法や教科ごとの勉強法を解説するなど、より実践的で専門家じゃないと書けないテーマを扱っています。
また、 対象ユーザーを受験生だけに限定せず決済者である保護者向けのコンテンツを入れているのもポイントです。ただアクセス数を増やすための記事ではなく、サイトに訪れたユーザーにとって役に立つ記事を作成する事で自社の信頼性を高めている良い例と言えます。
まとめ
今回は、初めてWEB集客に取り組む学習塾の運営者に向けて、学習塾がWEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法、記事作成ポイント、推奨文字数と推奨記事作成数、記事作成の流れまで解説しました。
学習塾がWEB集客する場合、学習塾を利用するのは生徒であり、学習塾を利用するかどうかを決定するのは保護者であるという点を留意する必要があります。
一般的には、保護者が学習塾へ「子どもを行かせる」のであって、子どもが自分で学習塾を比較検討してWEBサイトから問い合わせをする可能性は低いです。
また、生徒が行きたいと思う学習塾と、保護者が子どもに行かせたいと考える学習塾は、必ずしも一致するとは限りません。
生徒向けのコンテンツが不要なわけではありませんが、あくまでも子どもを学習塾へ活かせるかどうかの結論を出すのは保護者であり、保護者に向けたコンテンツの作成が中心になります。
たとえば、中学受験を控えた生徒に向けて「中学受験に合格するコツ」という記事を作成しても、生徒自身が検索する可能性が低い上に、問い合わせに結びつく可能性も低いです。「中学受験を控えた生徒」ではなく、「中学受験を控えた生徒を持つ保護者」へ向けた記事を作成する必要があります。
保護者の気持ちになって、保護者が必要とする記事を作成しましょう。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
 コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/06/09
コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/09
コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/09
コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/092025/09/09
-
 コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/06/09
コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOロングテールキーワードとは|SEOで重要な理由と選び方を解説2025/06/09
コンテンツSEOロングテールキーワードとは|SEOで重要な理由と選び方を解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOWebライティングとは?手順やポイントを初心者向けに解説2025/06/09
コンテンツSEOWebライティングとは?手順やポイントを初心者向けに解説2025/06/092025/06/09