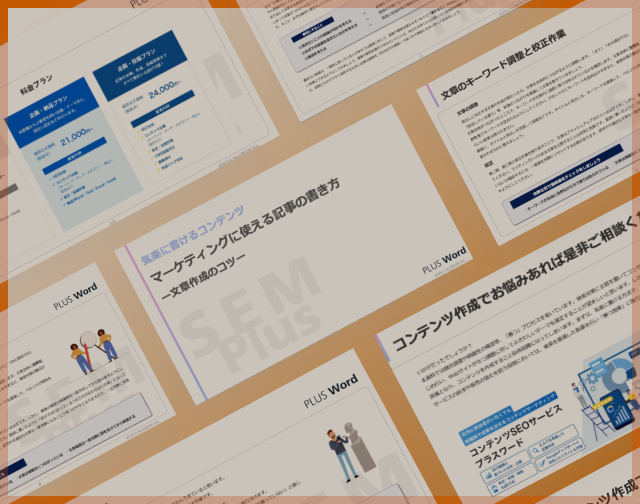葬儀会社のWEB集客における記事作成(コンテンツSEO)のポイント

「葬儀会社のWEB集客ではどのような記事を作成すれば良いのか」「どのようにコンテンツSEOを進めれば良いのか」などお悩みではないでしょうか?本記事では、葬儀会社がWEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法、記事作成の流れなど、初めてWEB集客に取り組むWEBサイト運営者にも分かりやすく解説します。

葬儀業者がWEB集客で記事作成(コンテンツSEO)を行うメリット
葬儀業者がWEB集客で記事作成を行うメリットは、以下の通りです。
- 葬儀に関する情報量を充実させることでユーザーからの信頼に繋がる
- 事前に情報収集をしている潜在層へのアプローチが可能
- 葬儀に関連するページが増えサイトの専門性が上がりSEO効果が高まる
葬儀に関する情報量を充実させることでユーザーからの信頼に繋がる
葬儀業者がWEB集客で記事作成を行うメリットの1つ目は、葬儀に関する情報量を充実させることでユーザーからの信頼に繋がることです。葬儀会社を比較検討している顕在層は、WEBサイトに掲載された情報からどこの葬儀会社を依頼するかを判断します。
葬儀プランしか掲載されておらず他の葬儀会社と大差がない場合、価格だけでどこの葬儀会社に任せるかを判断されてしまうかもしれません。
一方、葬儀に関する情報量を充実させておけば、利用者からの信頼感と安心感を高めることができ、競合する他社との差別化に繋がります。
事前に情報収集をしている潜在層へのアプローチが可能
葬儀業者がWEB集客で記事作成を行うメリットの2つ目は、潜在層へアプローチできることです。
▼ 葬儀会社のWEB集客における顕在層と潜在層は以下の通りです。
| 顕在層 | ・家族が急逝して慌てて葬儀会社を探している故人の家族 ・高齢の家族のために、事前に葬儀会社を探している家族 ・終活の一環として自分で葬儀会社を探している高齢者 |
| 潜在層 | ・高齢の家族がいる人 ・高齢者 |
急逝した場合には葬儀会社をゆっくり比較検討するだけの時間の余裕がなく、病院から紹介された葬儀会社や近所の葬儀会社へ直接連絡するなど、検索して調べたりWEBサイトを閲覧したりすることがないケースも想定されます。
一方、亡くなった時に慌てなくて済むように葬儀会社に事前に相談して生前契約するケースの場合、比較検討する時間の余裕があり、WEB集客の効果が期待できます。
さらに、誰にでもいつかは必ず必要になる葬儀会社という性質上、葬儀会社の潜在層は高齢の家族と高齢者であり、非常に幅広いです。
日常生活では関わる機会の少ない葬儀会社ですが、潜在層へのアプローチを意識してコンテンツを作成しておくことで、急逝した際に社名を思い浮かべてもらえたり、生前契約する際の候補に挙げてもらえたりする可能性が高くなります。
顕在層へのアプローチはリスティング広告やMEO対策の方が効果的ですが、潜在層へのアプローチには適していません。コンテンツSEOであれば、効率良く潜在層へのアプローチができ、葬儀会社への問い合わせに結び付けることができます。
葬儀に関連するページが増えサイトの専門性が上がりSEO効果が高まる
葬儀業者がWEB集客で記事作成を行うメリットの3つ目は、葬儀に関連するページが増えサイトの専門性が上がりSEO効果が高まることです。葬儀会社のWEBサイトで記事を公開しただけで、すぐにオーガニック検索からの流入が期待できるようになるわけではありません。
検索エンジンからの評価を高め、高品質なコンテンツだと判断される必要があります。
▼ Googleは、コンテンツの質を評価する際にE-E-A-Tという指標を利用しています。
| Experience(経験) | コンテンツ制作者の実体験や経験値に関する項目 |
| Expertise(専門性) | コンテンツの作成者もしくはWEBサイトがそのジャンルにおいて、専門家として高いスキルを持っているかどうか、専門家として信頼できるかどうかの指標 |
| Authoritativeness(権威性) | コンテンツ作成者やWEBサイト、運営元の組織や個人が広く認知されているか、また信頼できる情報源として特定の分野で認知された権威であるかどうか |
| Trust(信頼) | コンテンツの情報がどれだけ信頼できるか |
つまり、コンテンツSEOを実施することで葬儀に関連するページを増加させることができれば、サイトの専門性が上がることで高品質なコンテンツだと評価されやすくなり、SEO効果が高まるということです。
ただし、Googleから専門性が高いと評価されるには、葬儀に関連した記事を量産する必要があります。
葬儀と関係のないテーマや低品質な記事、コラムやお知らせなどの検索流入を期待できない記事を作成しても、専門性が高いとは判断されません。
葬儀会社の見込み顧客がどのような悩みや疑問を抱えているのか、どのようなキーワードで検索するかを意識し、記事を作成することが重要です。
葬儀関連の記事作成におけるキーワード選定の方法
基本的に葬儀は葬儀会社を利用して行われるため、葬儀会社を探している人が顕在層となります。
葬儀関連の記事作成における顕在層へ向けたキーワードは、以下のキーワードを組み合わせた複合キーワードになります。
| 軸キーワード | 葬儀・葬式・葬儀場・葬儀社・葬儀会社・葬儀業者・斎場 |
| 地域 | 北九州市・五反田駅・新潟市西区大野町 |
| 宗教・宗派 | 法相宗・華厳宗・天台宗・真言宗・浄土宗・浄土真宗 曹洞宗・臨済宗・日蓮宗・融通念仏宗 |
| 葬儀の形式 | 家族葬・密葬・一日葬・直葬・火葬・自宅葬 生前葬・樹木葬・お別れの会・自由葬 |
【例】
「葬儀会社 新潟市西区大野町」
「浄土真宗 大谷派 福岡市 斎場」
「家族葬 品川区」
一方、葬儀会社の潜在層は、高齢の家族がいる人や高齢者です。葬儀をしない人や葬儀会社を利用しないケースはかなり限定されるため、ターゲットは幅広くなります。遺族の負担を意識して生前契約をする高齢者も増加しており、認知度も高くなっています。
すでに生前契約をしているユーザーは見込み顧客ではなくなってしまうため、葬儀会社を選ぶ段階よりも前にターゲットへアプローチすることが重要です。
近年では終活を意識したコンテンツを作成する葬儀会社が増加しており、生前葬や生前契約に結びつけています。葬儀会社のWEBサイトのカテゴリとしてコンテンツを作成するケースから、別サイトやサブドメインでコンテンツを作成して葬儀会社のWEBサイトへ誘導するケースもあります。
葬儀関連の記事作成におけるキーワード選定では、特定の地域だけで運営している葬儀会社が全国をターゲットにしたキーワードで集客すると、費用対効果が低下する可能性がある点に注意する必要があります。
たとえば、新潟市西区大野町だけで運営している葬儀会社のWEBサイトの場合、以下のようなキーワードで集客しても、集客したユーザーのうち問い合わせに結びつくユーザーはごくわずかです。
- 生前葬とは
- 喪主の挨拶の仕方
- 香典袋の選び方・書き方・相場
上記のようなキーワードはどこに住んでいる人でも検索する可能性があるキーワードなので、コンバージョン率としてはかなり低くなってしまいます。
検索流入が必要なキーワードなのか、問い合わせに結びつくキーワードなのかを検討した上でキーワードを選定するようにしましょう。
葬儀関連の記事のカテゴリ例
葬儀関連の記事のカテゴリ例は以下の通りです。
- 葬儀の準備
- 葬儀のマナー(喪主)
- 葬儀のマナー(参列者)
- 弔辞例文
- 葬儀後にやる事
- 法事・法要
カテゴリ分けを実施しておくことで、以下のような効果が期待できます。
- ユーザーが目的の記事に到達しやすくなる
- コンテンツをスムーズに作成できる
- 検索エンジンのクローラビリティが向上する
- 重複した内容の記事作成を防止できる
- キーワードカニバリゼーションの発生を防止できる
葬儀の準備
葬儀関連の記事のカテゴリ「葬儀の準備」では、葬儀の喪主に向けた葬儀前の準備に関するコンテンツを作成します。
【コンテンツ例】
- 葬儀・通夜日程の決め方
- 葬儀までに準備しておくこと
- 遺影用の写真の選び方
- 葬儀に参列してもらう方の範囲の決め方
- 葬儀に参列してもらう方への連絡方法
葬儀のマナー(喪主)
葬儀関連の記事のカテゴリ「葬儀のマナー(喪主)」では、葬儀に関連して喪主は何をするのか、どのような点に注意すれば良いのかを解説したコンテンツを作成します。
【コンテンツ例】
- 喪主の挨拶の仕方
- 会場の席順や焼香の順番について
- 供花・供物の並び順
- 葬儀の受付係は誰に依頼すればよいか
- 返礼品や香典返しの選び方・相場
葬儀のマナー(参列者)
葬儀関連の記事のカテゴリ「葬儀のマナー(参列者)」では、葬儀の参列者に向けたマナーを解説したコンテンツを作成します。
【コンテンツ例】
- 家族葬での供花の送り方
- 香典袋の選び方・書き方・相場
- お通夜に参列する際の身だしなみ・服装
- お供えの花を贈るときのマナー
基本的にはすぐに葬儀会社を利用するユーザーではないので、問い合わせを訴求するのではなく、事前相談や生前契約、会員登録などへの誘導が狙いとなります。
弔辞例文
葬儀関連の記事のカテゴリ「弔辞例文」では、葬儀の喪主に向けて、弔辞例文に関するコンテンツを作成します。
【コンテンツ例】
- 弔辞で使ってはいけない言葉
- 弔辞の長さ・構成
- 弔辞の書き方・包み方
- 弔辞を読むタイミング
- 弔辞の読み方
葬儀後にやる事
葬儀関連の記事のカテゴリ「葬儀後にやる事」では、故人の家族に向けて、葬儀後に必要な手続きに関するコンテンツを作成します。
【コンテンツ例】
- 後飾りとは
- 葬儀に参列された方への御礼
- 遺品の整理
すでに葬儀会社を利用したユーザーに向けたコンテンツなので、問い合わせに直結するわけではありません。将来の利用に向けて、事前相談や生前契約への訴求が重要になります。
法事・法要
葬儀関連の記事のカテゴリ「法事・法要」では、故人の家族に向けて、法事・法要に関するコンテンツを作成します。
【コンテンツ例】
- 初七日法要では何をするのか
- 法事・法要とは
- 1周忌で準備すること
こちらも葬儀後に行うことがテーマなので、事前相談や生前契約、会員登録などへの誘導が狙いとなります。
葬儀関連の記事作成ポイント6選
葬儀関連の記事作成ポイントは以下の6つです。
- 文章を中心に分かりやすく簡潔に紹介する
- 執筆はユーザーに寄り添い丁寧な文章を心がける
- 小見出しや箇条書きを活用して読みやすい工夫をする
- 華やかな印象の画像の使用を避ける
- 文章での解説が難しい場合は動画を設置する
- 幅広いテーマを扱う場合はタグを使用する
【ポイント①】文章を中心に分かりやすく簡潔に紹介する
葬儀関連の記事作成ポイントの1つ目は、文章を中心に分かりやすく簡潔に紹介することです。
故人が急逝した場合、ほとんどの場合は記事をゆっくり読む余裕がなく、分かりにくい表現だったり関係のない話が書かれていたりすると、WEBサイトからの離脱の要因となってしまいます。
故人の家族が必要とする情報を、文章を中心に分かりやすく簡潔に紹介することが重要です。検索エンジンは主にテキストデータから記事の内容を把握するため、文章を中心としたコンテンツにすることが求められます。
たとえば、葬儀プラン別の料金表などを文章ではなく画像で作成すると、検索エンジンが記事の内容を正確に把握できない恐れがあります。一方、取り扱う祭壇の種類や葬儀会社へのルートなどは文章だけでは伝わりにくいため、画像を設置することをおすすめします。
【ポイント②】執筆はユーザーに寄り添い丁寧な文章を心がける
葬儀関連の記事作成ポイントの2つ目は、執筆はユーザーに寄り添い丁寧な文章を心がけることです。家族が亡くなった人が閲覧するページについては、お悔みごとでもあることを踏まえ、ユーザーに寄り添った文章を心掛ける必要があります。
不適切な表現や過度なキャッチコピーが使用されていると、不快に感じてページから離脱されてしまうかもしれません。明るいトーンで文章を執筆することを避け、信頼感・安心感が感じられるトーンで文章を執筆することが重要です。
【ポイント③】小見出しや箇条書きを活用して読みやすい工夫をする
葬儀関連の記事作成ポイントの3つ目は、小見出しや箇条書きを活用して読みやすい工夫をすることです。
小見出しとは、記事の中の特定の範囲の文章を要約した短い言葉です。一般的に、記事全体にはh1タグを、大見出しにはh2タグを、小見出しにはh3以下のhタグを使用します。
記事に対して適切にhタグを使用することで、記事を閲覧するユーザーが読みやすくなり、理解を助ける効果が期待できます。また、hタグはSEO対策においても重要な役割を持つため、hタグの使用ルールに従って適切に使用しなければいけません。
箇条書きとは、並列した情報を文章として表記するのではなく、それぞれの情報をひとつひとつ分けて列挙する方法です。
【例】
私が好きな食べ物は、トンカツ・ハンバーグ・エビフライ・ピーマンの肉詰め・チンジャオロースです。
【箇条書きした場合】
私が好きな食べ物は以下の通りです。
・トンカツ
・ハンバーグ
・エビフライ
・ピーマンの肉詰め
・チンジャオロース
WEBサイトの記事では、リストタグを用いて箇条書きを表現します。
上記の場合だと、以下のように表記します。
<ul>
<li>トンカツ</li>
<li>ハンバーグ</li>
<li>エビフライ</li>
<li>ピーマンの肉詰め</li>
<li>チンジャオロース</li>
</ul>
hタグやタイトルタグ、リストタグなどのHTMLタグは記事を作成する際に使用する機会が非常に多いので、どのような役割があるのか、どのように使用するのかを確認しておきましょう。
【ポイント④】華やかな印象の画像の使用を避ける
葬儀関連の記事作成ポイントの4つ目は、華やかな印象の画像の使用を避けることです。
葬儀会社を選ぶ人、葬儀を行った人、葬儀に参加した人の意見として、以下のようなものがあります。
- 葬儀を華やかにしたい
- 華やかに故人を送る事が出来て満足した
- 花祭壇が華やかでとても満足した
葬儀会社のWEBサイトで、華やかな印象の画像の使用をあえて避ける必要はありません。厳かな雰囲気にしようとしてモノトーンの画像だけにしてしまうと、葬儀を華やかにしたいと考えるユーザーから敬遠され逆効果になってしまうからです。
葬儀会社選びにおいて祭壇の華やかさ、豪華さは重視されており、華やかな祭壇の画像を設置することは、葬儀を華やかにしたいと考える顧客に向けたアピールになります。
一方、葬儀とは直接関係のない画像や原色中心のイラスト画像など、葬儀の厳かなイメージを壊してしまう画像は使用を避けなければいけません。
一般消費者向けの記事では、ユーザーの目を引くために過剰な装飾を行ったり、奇抜な写真やイラストが使用されたりするケースがあります。葬儀会社の利用者の大半は高齢者であり、落ち着いたイメージのWEBサイトでないと不安に感じてしまうかもしれません。
過剰な装飾は控えるようにし、利用者に安心感・信頼感を与えるようにしましょう。
【ポイント⑤】文章での解説が難しい場合は動画を設置する
葬儀関連の記事作成ポイントの5つ目は、文章での解説が難しい場合は動画を設置することです。動画はテキストや画像に比べると5,000倍の情報量を持つと言われており、視聴者の記憶に定着しやすいコンテンツです。
たとえば、焼香のやり方をテキストだけで解説しようとするとかなり説明が難しく、画像を使用するとしては複数の画像が必要になります。動画であれば記事のスペースを無駄に消費することなく、コンパクトに情報を提供することが可能です。
ユーザビリティを高める動画を記事に埋め込むことはSEOにも効果的なので、可能な限り動画を設置してみましょう。
▼ 葬儀会社のWEBサイトにおすすめの動画コンテンツは、以下の通りです。
- 喪主の挨拶の仕方
- 焼香のやり方
- 焼香する際の人の流れ
- 火葬後の骨上げの手順
- 生前葬の様子の紹介
【ポイント⑥】幅広いテーマを扱う場合はタグを使用する
葬儀関連の記事作成ポイントの6つ目は、幅広いテーマを扱う場合はタグを使用することです。前述したように、葬儀会社のWEBサイトで複数のテーマを扱う場合、カテゴリを分けておくことで、ユーザーが目的の記事に到達しやすくなります。
たとえば、喪主に向けた葬儀のマナーに関する記事と参列者に向けた葬儀のマナーを同じカテゴリに分類してしまうと、喪主がマナーについて書かれた記事を探す場合に時間がかかってしまうかもしれません。
以下のように別のカテゴリにしておくことで、求める情報がどのカテゴリにあるのか一目で分かるようになります。
- 葬儀のマナー(喪主)
- 葬儀のマナー(参列者)
一方、複数のカテゴリにまたがるテーマで記事を分類する場合には、カテゴリではなくタグを使用します。
たとえば、以下のようにカテゴリ分けされている時に、新たに服装に関するカテゴリを作成してしまうと、一つの記事が複数のカテゴリに分類されてしまいます。
- 葬儀前
- 葬儀後
- 法事・法要
このような場合には、「服装」カテゴリを作成するのではなく、「服装」タグを作成します。
葬儀前について知りたいユーザーは「葬儀前」カテゴリを、服装について知りたいユーザーは「服装」タグを見ることで求める情報を得ることができ、必要のない記事を読む必要がなくなります。
【葬儀会社のWEBサイトのカテゴリ・タグの例】
| カテゴリ | タグ |
|---|---|
| 葬儀前 喪主 参列者 葬儀後 法事・法要 | マナー 服装 お金 |
葬儀関連の記事の推奨文字数と推奨記事作成数
葬儀関連の記事の推奨文字数は3,000文字~5,000文字、推奨記事作成数は50ページ~100ページです。
Googleは記事の文字数の記事の順位には関連性はない、そのような設定はないと明言しています。
Google が優先する文字数があるとどこかで聞いたか読んだかしたために、特定の文字数になるように記事を書いていますか(そのような設定は存在しません)。
Google検索セントラル「検索エンジンを第一に考えたコンテンツ作成を回避する」
3,000文字だと検索上位表示できない、5,000文字なら上位表示できるといったことはないということです。一方、BacklinkoやAhrefsの調査によれば、文字数が多い記事の方が検索流入数が多くなっているそうです。
SEOとは関係のない記事を閲覧するユーザー目線だと、記事の文字数が300文字だと記事を読む前の段階から情報量が少ないと感じてしまうかもしれません。逆に、記事の文字数が数万文字だと、読み進めていくうちに途中で読むことに疲れて離脱する恐れがあります。
ユーザーに必要な情報を伝えることと、検索エンジンからの評価を得ることのバランスを考えると、3,000文字~5,000文字程度にすることをおすすめします。
葬儀会社のWEBサイトの記事数については、50記事~100記事が目安になります。この場合の記事数には、お問い合わせページやプライバシーポリシーなどの検索流入を期待しないページは含みません。何らかのキーワードで検索流入を期待する記事が対象となります。
ある程度まとまった量の記事を作成することで検索エンジンから専門性が高いと評価されやすくなり、ユーザーからも利便性が高いと評価されるでしょう。
ただし、文字数を増やそうとして外部サイトの記事をコピぺして記事を作成したり、自動生成ツールを使用して記事を作成したりすると、Googleからペナルティを受ける恐れがあります。
また、葬儀と直接関係のないテーマの記事を作成すると、検索エンジンがWEBサイトの専門性を正確に把握できなくなる可能性があります。
葬儀会社のWEBサイトへ誘導するために別のテーマでコンテンツを作成する場合は、別のサイトかサブドメインを作成することをおすすめします。
葬儀業者のWEB集客における記事作成の流れ
葬儀業者のWEB集客における記事作成の流れは、以下の通りです。
- キーワードとテーマを選定する
- 記事の構成を作成する
- 執筆をする
- 関連する画像を用意する
- 記事を公開する
STEP1. キーワードとテーマを選定する
葬儀会社のWEB集客における記事作成では、初めにキーワードとテーマを選定します。葬儀会社の記事作成において初めにキーワードを選定するのは、検索エンジンはユーザーが入力したキーワードと関連性の高いコンテンツを検索結果に表示する仕組みだからです。
キーワードを選定し、どのようなキーワードで検索流入を狙うのか、検索上位表示を目指すのかを明確にしたうえで構成の作成と執筆に取り掛かることで、ユーザーと検索エンジンから評価されるコンテンツを作成できるようになります。
▼ キーワードの選定手順は以下の通りです。
- メインキーワードを決める
- メインキーワードに付随する関連キーワードを出す
- キーワードの検索ボリュームを出す
- キーワードを精査する
- キーワードをグルーピングする
葬儀会社のWEB集客におけるキーワードの選定方法については、前述した「葬儀関連の記事作成におけるキーワード選定の方法」で確認してください。
STEP2. 記事の構成を作成する
次に、葬儀会社の見込み顧客へ向けたキーワードとテーマを元に、記事の構成を作成します。
▼ 記事の構成を作成する手順は以下の通りです。
- 記事を作る目的を確認
- ペルソナを設定
- キーワードを設定
- 検索意図を確認
- 検索上位記事を確認
- タイトル・見出しを設定
構成を作成する際には、検索エンジンは網羅性の高いコンテンツを検索上位に表示する傾向にあるため、検索ユーザーが求める情報がすべて網羅されているかを確認することが重要です。
選定したキーワードで実際に検索し、上位に表示されている記事と比較して情報量が不足していないかを確認しておきましょう。
また、葬儀会社のWEBサイトを訪問するユーザーを具体的にイメージすることも重要です。葬儀会社の場合、故人の家族だけでなく、終活の一環として事前相談や生前契約を検討している高齢者もターゲットとなります。
どちらをターゲットにした記事なのかを明確にしておかなければ、正しく訴求ができません。記事を閲覧するユーザーの気持ちになって構成を作成しましょう。
STEP3. 執筆をする
次に、作成した記事の構成に従って、葬儀会社の見込み顧客へ向けて記事を執筆します。
▼ 記事を執筆する際のポイントは以下の通りです。
- ターゲットにあわせたトーン&マナーで執筆する
- ターゲットキーワードを意識する
- 検索ユーザーの検索意図を意識する
- 結論から先に書く
葬儀会社のWEBサイトを閲覧するのは高齢者が大半なので、高齢者になじみのないカタカナ語や英単語は避けるようにしましょう。
【例】
- ログイン → 会員の方
- CONTACT → お問い合わせ
- ACCESS → 交通案内
STEP4. 関連する画像を用意する
次に、葬儀・記事の内容と関連する画像を用意し、サムネイル画像とアイキャッチ画像を作成し、記事に設置します。
【葬儀会社のWEBサイトにおすすめの画像・動画】
| 画像 | 動画 |
|---|---|
| 葬儀会社へのアクセスマップ コース別の祭壇 葬儀会場の様子 待合室・控室の様子 | 喪主の挨拶の仕方 焼香のやり方 焼香する際の人の流れ 火葬後の骨上げの手順 生前葬の様子の紹介 |
▼ 記事に画像を設置する際の注意点は、以下の通りです。
- 画像のファイルサイズが大きすぎないか
- 画像の形式は適切か
- altタグを設定したか
- 第三者の画像を盗用していないか
- 引用している場合は引用元を明記しているか
STEP5. 記事を公開する
最後に、完成した記事を葬儀会社のWEBサイトで公開します。
▼ 記事を公開するタイミングで忘れがちなのが以下の3点です。
- パーマリンクを半角英字にしていない
- カテゴリ設定をしていない
- ディスクリプションを設定していない
【葬儀関連のパーマリンク例】
| 挨拶 | greeting |
| 喪主 | chief-mourner |
| 参列者 | attendee |
| 家族葬 | family-funeral |
| 生前葬 | funeral-while-alive |
葬儀に関する記事作成の注意点
▼ 葬儀に関する記事作成の注意点は以下の通りです。
- 読みにくい漢字にはふりがなをふる
読みにくい漢字にはふりがなをふる
葬儀に関する記事では日常生活ではあまり目にしない単語が登場するケースが多く、読み方が分からない人もいるかもしれません。葬儀会社のWEBサイトを閲覧するユーザーの大半は高齢者です。読めない単語が見つかった時にネットで調べる習慣がないかもしれません。
葬儀の喪主は弔辞や弔電を読む機会があるため、読みにくい漢字を使用する場合にはふりがなをふっておくようにしましょう。
【葬儀に関する難読漢字と読み方の例】
| 難読漢字 | 読み方 |
|---|---|
| 逝去 | せいきょ |
| 急逝 | きゅうせい |
| 弔問 | ちょうもん |
| 衷心 | ちゅうしん |
| 読経 | どきょう |
| 袱紗 | ふくさ |
| ご尊父 | ごそんぷ |
また、高齢者が読みやすい文字サイズと文字フォントにしておくことも重要です。
高齢者が利用するWEBサイトの場合、視力の低下を考慮して文字サイズを16px以上(12pt以上)、明朝体よりゴシック体を使用するようにしておきましょう。
広めの行間にする、ボタンのサイズを大きくする、直感的に操作できるUIを導入するといった対策も効果的です。
葬儀の記事作成で参考になる例
【いい葬儀】

いい葬儀は、葬儀に関するノウハウ記事が200以上ある大型のメディアサイトです。特徴はテーマによって異なる形式で記事を作成している点です。
例えばユーザーに分かりやすいように会話型にしたり、一般的なものは表やイラストを使って作成しています。また、記事の内容はテーマに直接関係のある見出しとコンテンツだけを配置しているため、シンプルで分かりやすいものとなっています。
記事監修者としてメディアに露出している方の情報が掲載されている事で安心感もあり、葬儀の記事作成では参考になる点が多いメディアです。
まとめ
今回は、初めてWEB集客に取り組む葬儀会社のWEBサイト運営者に向けて、葬儀会社がWEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法、記事作成ポイント、推奨文字数と推奨記事作成数、記事作成の流れまで解説しました。
葬儀会社のWEB集客で重要なことは、顕在層だけでなく潜在層にもアプローチすることです。
家族が急逝した場合や、危篤になった場合は葬儀会社をゆっくり比較検討する時間の余裕がないケースが多く、近くの葬儀会社を選んだり価格だけで比較されてしまったりする恐れがあります。
近年では生前契約や会員登録を導入して見込み顧客を獲得する葬儀会社が増加しており、顕在層からのアプローチを待つだけでは十分な顧客を確保できないかもしれません。
コンテンツSEOにより潜在層へアプローチすることで、生前契約や会員登録を獲得しやすくなり、自社のブランディングにも繋がります。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
 コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/12
コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/12
コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/12
コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/09
コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/09
コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/092025/09/09
-
 コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/30
コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/302025/10/30