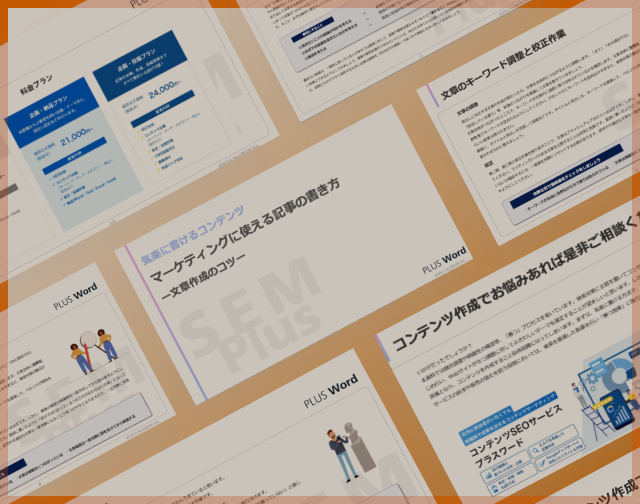社労士のWEB集客における記事作成(コンテンツSEO)のポイント

「社労士のWEB集客ではどのような記事を作成すれば良いのか」「どのようにコンテンツSEOを進めれば良いのか」など、お悩みではないでしょうか?この記事では、社労士がWEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法や記事作成の流れまで、初めてWEB集客に取り組むWEBサイト運営者にも分かりやすく解説します。

社労士がWEB集客で記事作成(コンテンツSEO)するメリット
社労士がWEB集客で記事作成するメリットは、以下の4つです。
- 労働・社会保険に関する得意分野を企業やユーザーにアピールできる
- 労働・社会保険に関するページが増えることでサイトの信頼性が高まりSEOに効果的
- 労働・社会保険に関する疑問を抱えた企業に対してアピールができる
- リスティング広告に比べて低予算で運用ができる
それぞれのメリットについて具体的に解説します。
労働・社会保険に関する得意分野を企業やユーザーにアピールできる
社労士がWEB集客で記事作成するメリットの1つ目は、労働・社会保険に関する得意分野を企業やユーザーにアピールできることです。
社労士は企業における労働・社会保険に関するさまざまな問題に対応する職業ですが、社労士へ依頼することを検討している企業にとっては、どの分野が得意なのかが重要です。
独占業務である労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や帳簿書類等の作成、申請書等の提出に関する手続代行、紛争解決手続代理業務だけでなく、労働社会保険諸法令に基づくコンサルティング業務についても受注する場合には、どの分野を得意としているのかをWEBサイトでアピールする必要があります。
年金問題や労働問題など、自身が得意とする分野に関する記事を作成することで、労働・社会保険に関する得意分野を企業にアピールすることが可能です。
また、過去に自身が解決した事例や、具体的な法律問題の解決方法に関する事例を紹介する記事を作成することで、見込み顧客に対して信頼感・安心感を与えることができます。
労働・社会保険に関するページが増えることでサイトの信頼性が高まりSEOに効果的
社労士がWEB集客で記事作成するメリットの2つ目は、労働・社会保険に関するページが増えることでサイトの信頼性が高まりSEOに効果的であることです。
サイトの信頼性はSEOにおいて重要な要素であり、Googleの検索品質評価ガイドラインにおけるコンテンツ品質評価の指標であるE-E-A-Tのひとつでもあります。
【E-E-A-T】
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
サイトの信頼性は、E-E-A-Tの「経験」「専門性」「権威性」の評価を高めることで、総合的に高めることが可能です。
社労士のWEBサイトの場合だと、
- 社労士としての経験を盛り込んだ記事を作成することで「経験」
- 労働・社会保険に関するページを増やすことで「専門性」
- 社労士自身がWEBサイト運営・記事執筆することで「権威性」
が、高いと評価されます。
また、労働・社会保険に関するテーマはYMYLジャンルに該当するため、他のテーマを扱うWEBサイトより高いE-E-A-Tが求められます。YMYLとは、E-E-A-Tと同様にGoogleの検索品質評価ガイドラインに登場する項目であり、記事を読んだ読者の命や人生に大きな影響を与える可能性が高いジャンルです。
労働・社会保険に関するテーマは企業だけでなく企業で働く従業員にも関わるテーマであり、記事に間違った内容が書かれていた場合、記事を読んだ読者が大きな損害を被ることになってしまう恐れがあります。
Googleは読者に不利益を与えないように、E-E-A-Tが低いサイトの記事が検索上位に表示されないようにしています。つまり、労働・社会保険に関するテーマを記事で扱う場合には、E-E-A-Tを高める必要があるということです。
労働・社会保険に関する疑問を抱えた企業に対してアピールができる
社労士がWEB集客で記事作成するメリットの3つ目は、労働・社会保険に関する疑問を抱えた企業に対してアピールができることです。
労働・社会保険に関する疑問があるからといって、社労士に直接相談してみようと考える企業ばかりではありません。そもそも、誰に相談すればよいかが分からないこともあるでしょう。
「就業規則 作成」といったように、検索することで問題を解決する方法を調べるケースが一般的です。労働・社会保険に関する具体的なトラブルを抱えた企業に向けた記事が上位表示されていれば、自然検索からの集客が期待できます。
リスティング広告に比べて低予算で運用ができる
社労士がWEB集客で記事作成するメリットの4つ目は、リスティング広告に比べて低予算で運用ができることです。リスティング広告はコンテンツSEOに比べると短期間で成果が期待できる集客方法ですが、広告出稿し続けたからといって、得られる効果が高くなるわけではありません。
たとえば、初めて広告を出稿した月と広告を出稿して3年目の月で、期待できる成果は同じです。一方、コンテンツSEOの場合は、毎月のコストが同じでも、半年後と3年後では得られる効果が異なります。
実施した施策に対する効果は積み上がるため、指数関数的に成果が伸びていきます。コンテンツSEOもリスティング広告も、どのくらいのコストをかけるかは自由に設定できるため、どちらも低予算から始めることが可能です。
一方、短期的な視点で見た場合、リスティング広告に比べてコンテンツSEOの方が低予算で運用ができる、というわけではありません。数ヶ月程度の集客であれば、リスティング広告の方が費用対効果が高いケースもあるでしょう。
しかし、1年以上集客するのであれば、コンテンツSEOの方がトータルのコストを抑えて集客できます。
社労士の記事作成におけるキーワード選定方法
社労士の記事作成におけるキーワード選定では、顕在顧客と潜在顧客が検索時に使用する可能性が高いキーワードを選定します。
▼ 社労士の、顕在顧客と潜在顧客は以下の通りです。
| 顕在顧客 | 社労士に依頼することを検討しているユーザー 複数の社労士を比較・検討しているユーザー |
| 潜在顧客 | 労働・社会保険に関する疑問・課題を抱えているユーザー |
顕在顧客は、以下のように「社労士」「社会保険労務士」と地域名を組み合わせたキーワードで検索する可能性が高いです。
- 社労士 福岡
- 社会保険労務士 東京都 港区
上記のようなキーワードで検索する見込み顧客は社労士へ依頼することを前提として検索しているため、問い合わせを獲得できる見込みが高いです。一方、他の社労士と比較・検討される可能性も高いため、社労士としての独自性や専門性をアピールできていなければ、集客できても問い合わせに繋がらないケースもあります。
潜在顧客は、「就業規則 作成」といったように、抱える課題を解決するキーワードを使用します。
社労士へ依頼することを前提として検索しているわけではないので、「社労士」「社会保険労務士」などのキーワードや地域名がキーワードに含まれることはありません。
潜在顧客が「どのような疑問や課題を抱えているのか」「どのようなキーワードを使用して検索するのか」を想定して、キーワードを選定することが重要です。
▼ キーワードを選定する方法には、以下の2つがあります。
- 実際に検索してみる
- キーワード選定ツールを使用する
見込み顧客が使用しそうなキーワードで実際に検索することで、サジェストキーワードや関連キーワードを取得できます。
| サジェストキーワード | キーワードを入力した検索窓に最大10個キーワードが表示される |
| 関連キーワード | 検索結果の「関連性の高い検索」の下に最大8個表示される |
手間をかけずキーワードが取得できますが、取得できるキーワード数が少ないことや見込み顧客が使用しそうなキーワードを想定する必要があること、キーワードをデータとして出力できないことがデメリットです。
キーワード選定ツールなら、上記のようなデメリットを気にせず大量のキーワードを取得できます。
| 無料ツール | 有料ツール |
|---|---|
| Googleキーワードプランナー ラッコキーワード RURI-CO Googleトレンド Ubersuggest | Keywordmap Ahrefs SEM RUSH kwfinder.com SERPStat |
無料ツールでも、手作業でキーワードを取得するより大幅に作業を効率化できます。
社労士関連の記事作成ポイント8選
社労士関連の記事を作成する際のポイントは、以下の8つです。
- 得意分野に関連したターゲットの設定と記事の作成をする
- 法律や制度に関する内容は読み手が分かりやすい表現を使う
- 法改正などが関わるため常に最新の情報を提供する
- 企業担当者向けであることを意識して執筆する
- 注意点やポイントなどのアドバイスを記事で紹介する
- 表や箇条書きを使い読みやすい文章構成にする
- 大量の記事を作成する場合はカテゴリを分けておく
- テーマが幅広くなる場合はタグを使用する
それぞれのポイントについて具体的に解説します。
【ポイント1】得意分野に関連したターゲットの設定と記事の作成をする
社労士関連の記事作成ポイントの1つ目は、得意分野に関連したターゲットの設定と記事の作成をすることです。
【社労士の主な業務】
| 1号業務 | 行政機関へ提出する書類の作成・提出代行 |
| 2号業務 | 就業規則などの帳簿書類の作成 |
| 3号業務 | コンサルティング |
上記の業務のうち、どの業務を依頼したいと考えているユーザーをターゲットにするのかを設定し、記事を作成する必要があります。
1号業務と2号業務は、社労士の独占業務なのでどの社労士も得意としていますが、3号業務に分類されるコンサルティングについては対応分野に幅があるため、自身の得意分野をアピールすることが重要です。
コンサルティング業務は社労士のような資格がなくても行えるため、社労士としての専門知識や経験を活かした記事を作成するようにしましょう。
【ポイント2】法律や制度に関する内容は読み手が分かりやすい表現を使う
社労士関連の記事作成ポイントの2つ目は、法律や制度に関する内容は読み手が分かりやすい表現を使うことです。
社労士の記事は労働・社会保険に関する法令に基づいて作成するケースが多いですが、日常的に法令を目にする機会が少ない読み手にとっては、法令の表現の意味が分からなかったり、単語自体の意味が分からなかったりすることがあります。
解釈が難しい法令には注釈を入れる、難読漢字にはフリガナ・用語解説を入れるといった工夫を心掛けましょう。
【ポイント3】法改正などが関わるため常に最新の情報を提供する
社労士関連の記事作成ポイントの3つ目は、法改正などが関わるため常に最新の情報を提供することです。社労士の記事は労働・社会保険に関する法令に基づいて作成するケースが多いですが、法改正が施行された場合、記事の内容自体を見直す必要があるケースもあります。
改正前の法令に基づいた内容のまま記事を公開していると、記事を読んだ読者に間違った情報を提供することに繋がり、金銭的な損失などの不利益を与えてしまうかもしれません。
法改正については事前に情報を入手しておき、施行前に記事で紹介する、施行後には記事の内容を修正するといった対応を心掛けましょう。
【ポイント4】企業担当者向けであることを意識して執筆する
社労士関連の記事作成ポイントの4つ目は、企業担当者向けであることを意識して執筆することです。社労士の主な顧客は企業なので、企業の担当者や決裁権のある役職者向けのトーンで執筆する必要があります。
一般消費者向けの記事のようなトーンで執筆してしまうと、不安感を与えてしまうかもしれません。記事のターゲットは企業であることを意識して、信頼感・安心感のある表現を心掛けましょう。
【ポイント5】注意点やポイントなどのアドバイスを記事で紹介する
社労士関連の記事作成ポイントの5つ目は、注意点やポイントなどのアドバイスを記事で紹介することです。記事で検索ユーザーの抱える疑問や課題に答えるだけだと、ユーザーは十分に満足できなかったり、問題が解決できなかったりする恐れがあるからです。
就業規則の作り方を解説する記事であれば、作成手順の解説とともに、作成時の注意点や作成するコツなどのアドバイスも紹介することでユーザーの満足度を高めることができます。
また、メリットを紹介する場合にはデメリットも必ず紹介するようにし、デメリットを解消する方法を紹介することも重要です。
【ポイント6】表や箇条書きを使い読みやすい文章構成にする
社労士関連の記事作成ポイントの6つ目は、表や箇条書きを使い読みやすい文章構成にすることです。数値や複数の要素を紹介する場合、文章だけで表現すると内容が伝わりにくくなってしまう恐れがあります。
表や箇条書きを併用し、ユーザーの理解度・満足度を高めることを意識した表現を心がけましょう。
▼ 表を活用した例
| 割増賃金 | |
| 時間外手当 | 賃金の25%以上 |
| 休日手当 | 賃金の35%以上 |
| 深夜手当 | 賃金の25%以上 |
| 深夜に時間外労働させた場合 | 賃金の50%以上 |
▼ 箇条書きを活用した例
【育児休業の対象条件】
・1歳未満の子どもを養育している
・対象の子が1歳6ヵ月になるまでに契約期間が満了することが明らかでない
・週の所定労働日が2日以下ではない
・労使協定の締結で対象外の従業員ではない
【ポイント7】大量の記事を作成する場合はカテゴリを分けておく
社労士関連の記事作成ポイントの7つ目は、大量の記事を作成する場合はカテゴリを分けておくことです。
大量の記事をひとつのカテゴリに分類している状態だと、サイトを訪れたユーザーが目的の記事を見つけるまでに時間がかかり、サイトから離脱されやすくなります。
サイトで扱うテーマごとにカテゴリを作成しておき、対象となる記事を各カテゴリに分類しておくことで、どのようなテーマを扱っているのか、どこに記事があるのかをユーザーに伝えることが可能です。
また、事前にカテゴリを作成しておくことで、重複した記事を作成したり、作成する記事のテーマが特定のテーマに偏ってしまったりすることがなくなります。
【ポイント8】テーマが幅広くなる場合はタグを使用する
社労士関連の記事作成ポイントの8つ目は、テーマが幅広くなる場合はタグを使用することです。親カテゴリと子カテゴリを作成して階層構造にすれば、幅広いテーマを扱う場合であってもカテゴリだけで対応できます。
【親カテゴリと子カテゴリの例】
| 親カテゴリ | 子カテゴリ |
|---|---|
| 保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 |
| 結婚・出産・育児 | 育児休業 産休 |
カテゴリに加えてタグを併用するのは、カテゴリとは異なる方向性で記事を分類した方が利便性が高くなるケースです。
たとえば、「扶養」というテーマは「保険」と「結婚・出産・育児」のどちらにも関わるため、親カテゴリあるいは子カテゴリとして設定するのはオススメできません。
カテゴリとしてではなくタグとして作成することで、複数のカテゴリを横断して記事を分類することができます。ただし、記事数がそれほど多くない状態で大量のタグを作成してしまうと、ユーザーは目的の記事を見つけづらくなってしまう恐れがあります。
サイト全体の記事数やカテゴリ数とのバランス、今後の記事作成数を意識してタグを活用するようにしましょう。
社労士に関する記事の推奨文字数と推奨記事作成数
社労士に関する記事の推奨文字数は3,000文字~5,000文字、推奨記事作成数は50ページ~100ページです。文字数が少なければ十分に検索意図を網羅することが難しくなり、検索上位表示できない恐れがあります。
一方、過剰に文字数を増やしてしまうと、記事のメインテーマが何かあやふやになったり、ユーザーが読み疲れて途中で離脱してしまったりするかもしれません。
網羅性と完読率のバランスを意識して、記事の文字数を決めることが重要です。どのくらいの文字数が適切なのかは、検索上位記事の文字数が参考になります。
検索上位記事の文字数は、以下のツールを使用することで簡単に調べることができます。
- ラッコツールズ工房の「見出し(hタグ)抽出」
- ラッコキーワードの「見出し抽出」
記事の作成数は、多ければ多いほどユーザーの満足度が向上し、専門性が高くなります。文字数のように増やし過ぎて利便性が低下することはないので、出来る限り記事数を増やす方が効果的です。
逆に、記事数が少なすぎるとユーザーを十分に満足させることができず、他のサイトへ離脱されてしまう恐れがあります。記事を作成する際には、50ページ~100ページを目安にしておきましょう。
社労士の記事のカテゴリ設定例
社労士の記事カテゴリの設定例は、以下の通りです。
- 人事・労務
- 働き方
- 助成金
- 入社、退職
- 結婚・出産・育児
- 就業規則
- 社会保険・労働保険
- 労働問題
それぞれのカテゴリで、どのような記事コンテンツを作成すれば良いのかを解説します。
人事・労務
社労士の記事カテゴリ「人事・労務」では、人事・労務に関する情報が掲載された記事を作成します。
【カテゴリ「人事・労務」の記事作成例】
- 中小企業の割増賃金の引き上げはいつからか
- 従業員の副業を禁止することは可能なのか
- 随時改定が行われるのはどのようなケースか
働き方
社労士の記事カテゴリ「働き方」では、働き方に関する情報が掲載された記事を作成します。
【カテゴリ「働き方」の記事作成例】
- リモートワークとは
- フリーアドレスを導入する際の注意点
- テレワーク導入に欠かせないオフィス機器
社労士に依頼するのは企業であり従業員ではないため、従業員向けの記事を作成した場合は問い合わせに繋がらない点に注意して記事を作成する必要があります。
助成金
社労士の記事カテゴリ「助成金」では、助成金に関する情報が掲載された記事を作成します。
【カテゴリ「助成金」の記事作成例】
- キャリアアップ助成金とは
- 創業助成金を受け取る条件
- 業務改善助成金の申請方法
入社・退職
社労士の記事カテゴリ「入社・退職」では、入社・退職に関する情報が掲載された記事を作成します。
【カテゴリ「入社・退職」の記事作成例】
- 社会保険・労働保険の加入手続き
- 任意継続被保険者とは
- 雇用保険の資格喪失手続きの手順
- 離職票の提出期限
- アルバイトでも社会保険に加入させないといけないのか
結婚・出産・育児
社労士の記事カテゴリ「結婚・出産・育児」では、結婚・出産・育児に関する情報が掲載された記事を作成します。
【カテゴリ「結婚・出産・育児」の記事作成】
- 育児休業給付金支給申請書の書き方
- 育児休暇や産前・産後休暇の申請を会社は拒否できるのか
- 産後パパ育休とは
- 育児介護休業法改正における企業の対応
- 育児休業給付金の対象となる従業員は誰か
育児休暇や産前・産後休暇については、企業だけでなく取得する従業員も興味を持つテーマなので、どちらに向けた記事なのかを明確にした上で記事を作成しましょう。
就業規則
社労士の記事カテゴリ「就業規則」では、就業規則に関する情報が掲載された記事を作成します。
【カテゴリ「就業規則」の記事作成例】
- 就業規則の周知義務とは
- 就業規則を変更する手順
- 就業規則の意見書に押印は必要なのか
- 就業規則の閲覧に関する使用者の義務
- 従業員が10人未満でも就業規則を作成する必要があるのか
社会保険・労働保険
社労士の記事カテゴリ「社会保険・労働保険」では、社会保険・労働保険に関する情報が掲載された記事を作成します。
【カテゴリ「社会保険・労働保険」の記事作成例】
- 労災保険とは
- 労働保険 概算保険料申告書の提出先や書き方
- 会社役員は雇用保険に加入できるのか
労働問題
社労士の記事カテゴリ「労働問題」では、労働問題に関する情報が掲載された記事を作成します。
【カテゴリ「労働問題」の記事作成例】
- 36協定(サブロク協定)とは
- 運送業の2024年問題
- LGBTQとは
社労士の記事のタグ設定例
SATO社会保険労務士法人が運営するオウンドメディア「SATO MAGAZINE」では、以下のようにカテゴリとタグを設定しています。
| カテゴリ | タグ |
|---|---|
| 入社 退職 結婚・出産・育児 従業員の変更 介護 病気・ケガ・死亡 会社の各種変更 高齢者 保険料 労務関係 その他 最新の法改正 | 試用期間 雇用契約 助成金・補助金 相談・顧問契約 社労士 労働時間 書式・書き方 就業規則 産休 育児休業 36協定 事業所 会社設立 労災保険 雇用保険 厚生年金 健康保険 |
タグの設定方法については、前述した「【ポイント8】テーマが幅広くなる場合はタグを使用する」を参照してください。
社労士のWEB集客における記事作成の流れ
社労士のWEB集客における記事作成の流れは、以下の通りです。
- キーワードとテーマを選定する
- 構成を作成する
- 執筆をする
- 関連する画像を用意する
- 記事を公開する
- 公開記事の内容確認とリライトを継続的におこなう
それぞれのステップでは何をするのか、どのような点に注意すべきかを解説します。
STEP1. キーワードとテーマを選定する
社労士のWEB集客における記事作成では、始めにキーワードとテーマを選定します。記事を作成する初期段階でキーワードを選定するのは、社労士の見込み顧客である企業が使用するキーワードを意識した記事を作成することが重要だからです。
企業の従業員の悩みや疑問を解決する記事を作成しても集客できるのは企業の従業員であり、企業からの問い合わせに繋がるとは限りません。従業員向けの記事を作成するのではなく、企業側が抱える課題を解決する記事を作成することが重要です。
キーワードの選定方法については、前述した「社労士の記事作成におけるキーワード選定方法」で確認してください。
STEP2. 構成を作成する
次に、社労士の見込み顧客へ向けたキーワードとテーマを元に、記事の構成を作成します。
記事の構成を作成する際のポイントは、以下の通りです。
- キーワードから検索意図を想定する
- 需要の大きいテーマから順に配置する
- 適切な箇所にCTAを設置する
- 見込み顧客に向けた内容になっているかを確認する
- CTAに繋がる文脈にする
STEP3. 執筆をする
次に、作成した記事の構成に従って、社労士の見込み顧客へ向けて記事を執筆します。記事を執筆する際には、一般消費者ではなく企業に向けたトーン・内容にすることを意識することが重要です。
BtoCメディアのように衝動買いを促したり、過度な強調表現を使用したりするのではなく、見込み顧客へ信頼感を与える表現を心がけましょう。
STEP4. 関連する画像を用意する
次に、記事の内容と関連する画像を用意し、サムネイル画像とアイキャッチ画像を作成し、記事に設置します。
▼ 社労士の記事で用意する画像は以下の通りです。
- 作成・提出する書類の画像
- 申請書や証明書の現物画像
- 社労士自身や社労士事務所スタッフの顔社員
- 顧客とヒアリングしている風景
- 顧客の顔社員
主要な顧客は企業なので、社会保険労務士事務所の代表者や主要なスタッフの顔写真は必須といえるでしょう。
顔写真と合わせて経歴や所属、保有資格なども紹介したページを作成しておくと、見込み顧客に対して信頼感・安心感を与えることができます。また、記事に画像を設置する際には、altタグを使用しておく必要があります。
altタグとは、検索エンジンに対して、何の画像なのか、画像がどのような意味を持つのかを正確に伝えるためのタグです。検索エンジンは記事に設置された画像ファイルから画像の内容を正確に認識できないので、altタグで画像の意味を理解させなければいけません。
▼ altタグを使用することで、以下のような効果も期待できます。
- 視覚障害者の理解を助ける
- 画像の読み込み遅延時に代替テキストを表示できる
- 画像検索で記事が表示されやすくなる
STEP5. 記事を公開する
次に、完成した記事を社労士のWEBサイトで公開します。社会保険労務士事務所の顧客は一般消費者ではなく企業なので、ある程度記事が完成した状態で公開することをおすすめします。
書かれている内容に間違いがあったり、誤字・脱字が多かったりすると、事務所としての信頼性が低下する恐れがあるからです。
▼ 記事を公開する際のチェックポイントは、以下の通りです。
- 記事のテーマとターゲットにズレがないか
- 日本語として成立している文章になっているか
- 景品表示法や著作権法に抵触していないか
- 関連した記事への内部リンクは設置されているか
- パーマリンクは半角英数字で記述されているか
STEP6. 公開記事の内容確認とリライトを継続的におこなう
最後に、公開した記事の効果を検証し、成果が出るまでリライトを繰り返し実施します。
コンテンツSEOでは検索流入を前提とした記事を作成する施策なので、記事が検索上位表示されていなかったり、問い合わせへ誘導できていなかったりする状態だと、期待する効果を発揮することはできません。
記事を作成・公開したままで放置するのではなく、記事公開から一定期間経過後に効果を検証する必要があります。
また、定期的に記事の内容をチェックし、最新の情報を提供できているか、記事の内容が法改正に対応できているかをチェックすることも重要です。
社労士に関する記事作成例
【SATO MAGAZINE】

SATO社会保険労務士法人は、取引先・関与先は約5,400社、全国6拠点の業界最大手の社労士グループです。
SATO社会保険労務士法人が運営するオウンドメディア「SATO MAGAZINE」では、経験の浅い担当者や経営者で理解ができるように分かりやすく解説されており、複雑な内容についてはイラストや図表を活用してイメージしやすく工夫されています。
経験豊富な社会保険労務士が記事を執筆しているため、単なる情報提供だけでなく実務的なノウハウも豊富です。
「入社」や「退職」、「結婚・出産・育児」といったカテゴリに加え、「雇用契約」や「労働時間」、「育児休業」といったタグが設けられており、必要な情報にアクセスしやすくなっています。
まとめ
今回は、社労士がWEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法や記事作成の流れまで解説しました。社労士がWEB集客を実施する場合、顕在顧客だけでなく潜在顧客まで含めて幅広いユーザーを集客することが重要です。
潜在顧客向けの記事を作成することで、社労士へ依頼することを検討していない企業にもアプローチでき、競合他社との過剰な競争を避けて問い合わせを獲得できます。
本記事で解説したキーワード選定の方法や記事作成の流れを参考に、幅広い見込み顧客にアプローチできる記事を作成しましょう。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
 コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/12
コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/12
コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/12
コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/09
コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/09
コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/092025/09/09
-
 コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/30
コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/302025/10/30