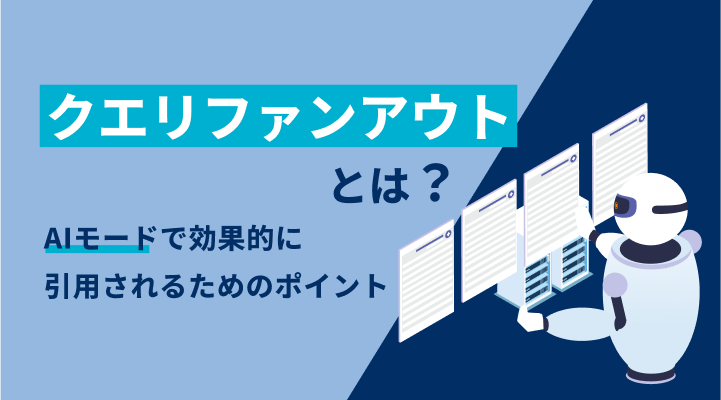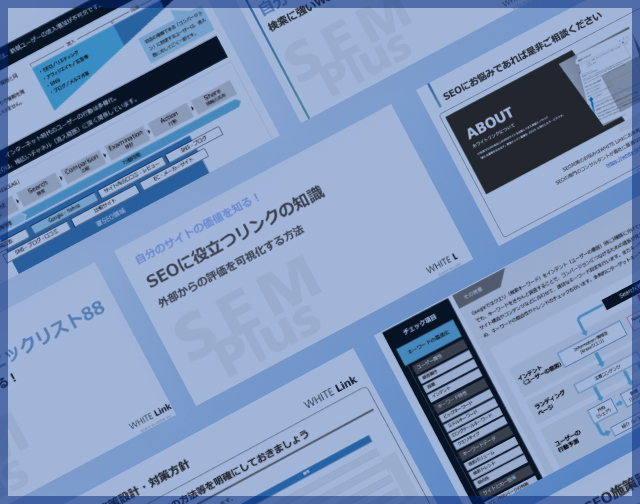関連性の高い被リンクとは?重要と言われる背景と定義を解説

外部対策に取り組む場合「関連性のある被リンクを増やした方が良い」「関連性が低い被リンクは逆効果になる」と聞いた事がある方も多いのではないでしょうか?今回は、関連性が重要と言われる理由や関連性の定義について、Googleの特許や実際に施策をおこなった経験を基に詳しく解説します。被リンク獲得をおこなう方は是非最後までご覧ください。

関連性の高い被リンクとは
関連性の高い被リンクとは、リンク元ページとリンク先ページのトピックに関連性がある被リンクの事です。関連性の低い被リンクに比べて、関連性が高い被リンクを獲得した方が自サイトのSEO効果が高くなります。
ただし、関連性が低いからといってSEO効果がないわけではありません。多くのサイトから被リンクを集めているサイトからの被リンクであれば、SEO効果は高くなります。
関連性の高い被リンクが重要と言われるようになった背景
関連性の高い被リンクが重要と言われるようになった背景には、PageRankの特許が関係しています。
初期のPageRankの算出方法(ランダムサーファーモデル)では、リンクの数と質によってリンク先ページを評価する仕組みだったため、単純にPageRankの高いページから多くの被リンクを集めるだけでSEO高価が高くなりました。
その後、Googleが2004年に出願し2010年に承認されたRanking documents based on user behavior and/or feature dataの特許にリンク元ページとリンク先ページの関連性について言及されていた事で、被リンクの関連性が重要視されるようになります。
いわゆる、みなさんが大好きなリーズナブルサーファーモデルと言われるPageRankのモデルですね。
海外のSEOメディア「SEO BY THE SEA」がこの特許を取り上げた記事を公開した事もあり、被リンクの関連性が重要視されるようになっていきました。
関連性の高い被リンクの定義
リーズナブルサーファーモデルの特許を見ると、関連性の高い被リンクの定義は以下になります。
- アンカーテキストとページのテーマが一致している
- リンク元ページとリンク先ページのテーマが一致している
- リンクの前後にあるテキストに関連性がある
ただし、リーズナブルサーファーモデルの特許は約20年近くに出願された特許のため、2024年現在では変更されている可能性もありますが、ユーザーがクリックする可能性を元にPageRankを算出している事を考えると大きく変わっている可能性は低いため、是非参考にしてみてください。
リンク元ページとリンク先ページのテーマ
リンク元ページのテーマとリンク先ページのテーマの関連性もSEO評価に影響があります。リーズナブルサーファーモデルの特許を見ると、リンク先ページとリンク元ページの関連性が高い方が、PageRankが分配される仕組みとなっていることが分かります。
例えば、SEOについて記載したページの場合、同テーマであるSEOトピックのページからのリンクと、広告に関するページからのリンクであれば、前者の方が関連性が高いためSEO評価が高くなります。
ただし、関連性がないテーマのページからのリンクだからと言ってSEO効果がないわけではありません。あくまで、リンク先ページに流れるリンクジュースの量が変わるだけです。
アンカーテキストとページのテーマ
アンカーテキストとページのテーマが一致している場合は、リンクの重要度が高くなるためSEO効果が高まります。
例えば、「ポークカレーの作り方」について説明されているぺージの中で唐突に「バイクの乗り方」というアンカーテキストが出てきた場合、当然ユーザーがリンクをクリックする可能性は少なくなります。
逆に「ビーフカレーの作り方」というアンカーテキストが出てきた場合はクリックされる可能性が高くなるため、リンクの重要度が高くなり、PageRankが多く分配されます。
リンクの前後にあるテキスト
リンクの前後に記述された単語や、文脈の関連性もSEO評価に影響します。
例えば、「SEO」を紹介するページの中に「被リンク」というアンカーテキストがあるとします。このアンカーテキストの前後の文章には、被リンクの効果や重要性を紹介する文章があるのとないのではユーザーがクリックする可能性が変わります。
当然、アンカーテキストに関連する文脈がリンクの前後にある方がクリックされる可能性が高くなるため、リンクの重要度が高くなります。
被リンクは「関連性と質」どちらが重要なのか
被リンク獲得をおこなう場合、リンクの関連性とリンクの質では、リンクの質の方が重要となります。ここで言うリンクの質とはPageRankの高さの事を指しますが、現在は確認する事ができないのでahrefsのDRに置き換えて解説します。
つまり、こういうことです。
関連性高いDR10のサイトからのリンクよりも、関連性の低いDR40のサイトからのリンクの方がSEO効果が高い
その理由は、PageRankの仕組みがページに訪れたユーザーがページ上のリンクをクリックする可能性に基づいているためです。
DRが高いサイトは多くのサイトからリンクされているため、多くのユーザーが訪問する可能性があります。結果として、DR10のサイトよりもDR40のサイトからのリンクの方が、自サイトへのリンクをクリックする可能性が高くなるため、理論上はPageRankが高くなります。
そのため、被リンクについて良く言われる「サイトと関連性が低い被リンクは効果がない」は間違いであり、関連性が高くてもPageRankが0のサイトからリンクを獲得してもSEO効果は殆どありません。
関連性が低いサイトからのリンクはぺナルティになるは間違い
被リンク施策でよく言われる、「関連性が低い被リンクはペナルティになる」「関連性が低い被リンクは効果がない」これは間違いです。
まず、「関連性が低い被リンクはペナルティになる」と言われる背景には、SEO評価を意図的に上げる為に作成されたリンクファームや、PBN(プライベートブログネットワーク)の殆どが関連性の低いサイトであり、その多くが手動ペナルティの対象だった事が影響しています。
しかしながら上記手法がGoogleペナルティの対象となった理由は、関連性の低さではなく、自作自演により意図的にPageRankを操作しようとする手法そのものがGoogleのガイドラインに反していたためです。つまり、ページテーマが関連していたとしてもペナルティになっていたと考えられます。
また、Googleはスパムリンクについて、アルゴリズムによって効果が無効化されるため、放置して構わないと公式に何度も発言しています。
自サイトと関連性が低いからと言ってGoogleの否認ツールからリンクの否認申請をおこなうと、本来SEO効果があったリンクを削除してしまいSEO評価が低下する可能性があるため注意しましょう。
関連性が高い被リンクでSEO効果がないケース
前述した関連性が高い被リンクでも、以下に該当するリンクの場合はSEO効果がありません。
それぞれ解説します。
nofollowのリンク
被リンクにnofollowタグが設定されている場合は、SEO効果がない被リンクとなります。
nofollowとは、検索エンジンにリンク先ページのクロールを拒否する指示を出すためのHTML属性です。nofollowは元々、口コミサイトや掲示板サイトなどのコメント欄にSEO目的で自サイトへのリンクを設置するのを防ぐために作られました。
そのため、nofollowが設定されたリンクの場合はリンク先ページにリンクジュースが流れずSEO効果はなくなります。ただし、現在はnofollowの役割が変更されヒントモデルになったため、nofollowリンクでもSEO効果が多少ある可能性があります。
また、シードサイトからの距離が近いリンクであればnofollowでも一定の効果が期待できます。
noindexが設定されているページからのリンク
noindexが設定されているページからのリンクも、SEO効果はありません。
noidnexとは、Googleのインデックスを拒否するためのタグのことです。インデックスを拒否している場合、Googleの検索エンジンはそのページの品質を見る事はなくなるため全ての評価が失われます。
これについては、Googleのジョン・ミューラー氏が2018年の動画の中で解説しています。
そのため、自サイトと関連性が高いページであったとしても、noindexタグが設定されているページからの被リンクにSEO効果はありません。
相互リンクでWEBサイトのお知らせ欄からリンクして貰う事があると思いますが、お知らせページ自体にnoindexが設定されているケースを見かけるため、相互リンクをおこなう際は事前に確認しておきましょう。
クラスC以上が同じIPアドレスからの被リンク
IPアドレスとは、インターネット上の住所のようなものになりデバイスやWEBサイトを識別するための一意の番号です。

クラスC以上が同じIPアドレスのWEBサイトからの被リンクも、SEO効果はありません。
分かりやすく解説すると、以下のようになります。
- 自サイトのIP:111.222.333.44
- リンク元IP:111.222.333.55 クラスC以上が同じためリンクの価値はなくなる
- リンク元IP:111.222.332.44 クラスC以上が異なるためリンク価値がある
同じクラスC以上のIPアドレスからの被リンクはSEO効果が期待できない理由として、検索エンジンがこれらのリンクを自然なリンクではないと判断するためです。
簡単に言うと、運営元が同じサイトを自作自演で被リンクとして使っていると判断されるという事です。
【参考】:https://patentimages.storage.googleapis.com/7d/01/a2/a69211bc0400c8/US6725259.pdf
まとめ
今回は、被リンクの関連性について解説しました。
Googleがアルゴリズムを公開していないため、過去の特許や実際の経験を元に解説しましたが、関連性の高いサイトからの被リンクは現在でもWEBサイトのSEO評価を高める効果があります。
ただし関連性の高い被リンクだけが、SEO効果を高めるわけではありません。どのような被リンクが評価されるのか正しい知識を付けた上で継続的に増えていく仕組みを作っておく事が大切です。
社内に被リンク獲得のノウハウやリソースがない場合に、弊社の被リンク獲得代行サービスまで気軽にお問合せくださいませ。

- 被リンク完全解説
- 被リンク獲得方法
- 被リンク精査方法
- 被リンクの調べ方
- 被リンク獲得代行
ぜひ、読んで欲しい記事
-
 SEO対策Googleクローラーとは?仕組みと申請方法・巡回頻度を高めるやり方2026/01/16
SEO対策Googleクローラーとは?仕組みと申請方法・巡回頻度を高めるやり方2026/01/162026/01/16
-
 SEO対策h1タグとは?初心者向けにSEO効果と正しい使い方を徹底解説2026/01/16
SEO対策h1タグとは?初心者向けにSEO効果と正しい使い方を徹底解説2026/01/162026/01/16
-
 SEO対策YMYLとは?対象ジャンルやSEOを成功させるためのポイントを解説2025/12/19
SEO対策YMYLとは?対象ジャンルやSEOを成功させるためのポイントを解説2025/12/192025/12/19
-
 SEO対策キーワード選定のやり方・コツを初心者向けに徹底解説2025/11/20
SEO対策キーワード選定のやり方・コツを初心者向けに徹底解説2025/11/202025/11/20
-
 SEO対策クリニックのSEO対策ガイド│キーワード設計から対策方法まで徹底解説2025/11/14
SEO対策クリニックのSEO対策ガイド│キーワード設計から対策方法まで徹底解説2025/11/142025/11/14
-
 SEO対策ページの表示速度はSEOに影響する?計測方法と10の改善方法を解説2025/11/05
SEO対策ページの表示速度はSEOに影響する?計測方法と10の改善方法を解説2025/11/052025/11/05