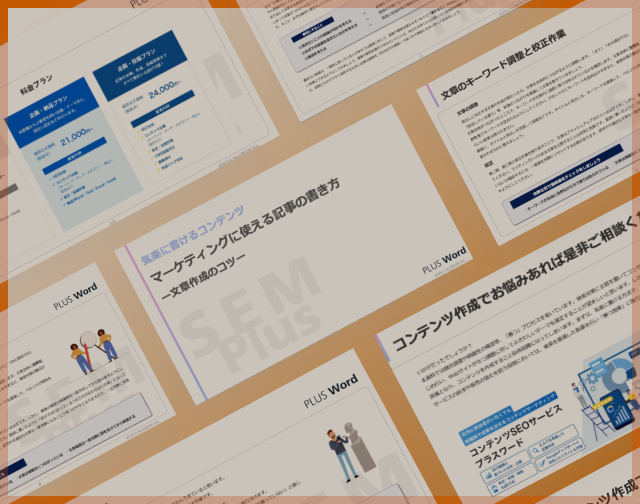注文住宅会社のWEB集客における記事作成(コンテンツSEO)のポイント

「注文住宅会社のWEB集客ではどのような記事を作成すれば良いのか」「コンテンツSEOをどう進めれば良いのか」など、お悩みではないでしょうか?本記事では、注文住宅会社がWEB集客で記事を作成するメリットや、記事作成ポイント、記事作成の流れなど初めてWEB集客に取り組む注文住宅会社のサイト運営者にも分かりやすく解説します。

注文住宅業者がWEB集客で記事作成(コンテンツSEO)を行うメリット
注文住宅業者がWEB集客で記事作成を行うメリットは、以下の通りです。
- 注文住宅に関する専門性が高い事をユーザーにアピールできる
- 注文住宅に関連するページが増えサイトの専門性が上がりSEO効果に繋がる
- 注文住宅を検討している見込み顧客へのアプローチができる
- 注文住宅の購入を検討している潜在顧客への認知にも繋がる
それぞれのメリットについて分かりやすく解説します。
注文住宅に関する専門性が高い事をユーザーにアピールできる
注文住宅業者がWEB集客で記事作成を行うメリットの1つ目は、注文住宅に関する専門性が高い事をユーザーにアピールできることです。
▼ 見込み顧客が注文住宅会社を選ぶ基準としては、以下のようなものが想定されます。
- コスト
- 対応設備や機能
- デザイン
- 技術力
- アフターメンテナンス
- 資金計画や土地探しについてのサポート
用意されたプランの中からセレクトする企画住宅を購入する場合とは異なり、注文住宅を検討している見込み顧客は、デザイン力や機能、建築士の人柄を重視しています。
建築の専門家ではない見込み顧客からすれば、自身の要望をどれだけ汲み取って実現してくれる会社なのかが重要なわけです。施工事例や注文住宅に関連した記事を作成することで、デザイン力や技術力をアピールできます。
注文住宅に関連するページが増えサイトの専門性が上がりSEO効果に繋がる
注文住宅業者がWEB集客で記事作成を行うメリットの2つ目は、注文住宅に関連するページが増えサイトの専門性が上がりSEO効果に繋がることです。
Googleは記事の内容からサイトの専門性を判断しているため、特定のテーマの記事を増やすことで専門性が高いと判断されやすくなり、検索上位に表示されやすくなります。
注文住宅を検討している見込み顧客へのアプローチができる
注文住宅業者がWEB集客で記事作成を行うメリットの3つ目は、注文住宅を検討している見込み顧客へのアプローチができることです。
▼ 注文住宅会社の見込みユーザー層は、以下のように分類されます。
| 顕在層 (見込み客) | ・注文住宅会社を比較・検討している ・注文住宅会社について情報収集している ・注文住宅の購入を検討している |
| 潜在層 | ・どのような住宅を購入するか検討している ・住宅について情報収集している ・住宅の購入を検討している |
| 非認知層 | ・賃貸物件もしくは実家に住んでいる |
注文住宅を本格的に検討しているユーザーはデザインだけではなく、間取りや機能について、外壁材やキッチンの形など詳細に情報を収集する可能性が高くなります。
注文住宅に関する情報を記事で発信する事でユーザーの疑問を解決出来るだけではなく、自分の希望を叶えてくれる会社という印象を与える事出来ます。
つまり、より購入意欲の高いユーザーに対してアプローチ出来るという事です。
注文住宅の購入を検討している潜在顧客への認知にも繋がる
注文住宅業者がWEB集客で記事作成を行うメリットの4つ目は、注文住宅の購入を検討している潜在顧客への認知にも繋がることです。
▼ 注文住宅会社にとっての潜在層は以下の通りです。
- どのような住宅を購入するか検討している
- 住宅について情報収集している
- 住宅の購入を検討している
分譲住宅や企画住宅、分譲マンションではなく、注文住宅の購入を検討している人は顕在層になります。
注文住宅の購入を検討している顕在層だけにアプローチすると、注文住宅を購入する可能性がある、住宅の購入を検討している潜在層へのアプローチはできません。
注文住宅について深く検討されないまま、分譲住宅や企画住宅、分譲マンションを購入してしまうかもしれません。顕在層だけでなく住宅の購入を検討している潜在層へもアプローチし、リードナーチャリングを実施することで、顕在層となる可能性を高めることができます。
注文住宅関連の記事作成におけるキーワード選定の方法
注文住宅の記事制作におけるキーワード選定では、見込み顧客がどのようなキーワードで検索するかを想定する必要があります。
前述したように、注文住宅会社の見込み顧客は以下の通りです。
| 顕在層 | ・注文住宅会社を比較・検討している ・注文住宅会社について情報収集している ・注文住宅の購入を検討している |
| 潜在層 | ・どのような住宅を購入するか検討している ・住宅について情報収集している ・住宅の購入を検討している |
| 非認知層 | ・賃貸物件に住んでいる |
注文住宅会社の顕在層は、「注文住宅」・「ハウスメーカー」・「工務店」といったキーワードに地域名を加えて検索します。
ただし、「ハウスメーカー」・「工務店」だと、注文住宅ではなく企画住宅を購入しようとしている人にもアプローチする点に注意しなければいけません。
注文住宅会社の潜在層へアプローチする場合には、住宅を購入していない人が検索時に使用するキーワードを選定する必要があります。
たとえば、「住宅 外壁塗装」「住宅 リフォーム」などのキーワードはすでに住宅を購入している人が使用するキーワードなので、集客しても問い合わせや成約に結びつくことはありません。
また、「規格住宅 選び方」「規格住宅 デメリット」などのキーワードは注文住宅を検討している人が検索する可能性がありますが、「規格住宅 おしゃれ」「規格住宅 間取り」などのキーワードを使用する可能性は低いです。
上記のように、自社の見込み顧客が使用するキーワードなのか、集客しても問い合わせに結びつかないキーワードではないかを意識してキーワードを選定するようにしましょう。
注文住宅関連の記事作成ポイント12選
注文住宅関連の記事作成ポイントは、以下の通りです。
- 自社の得意分野に関するテーマ・ターゲットを設定する
- 実際に請け負った物件の事例写真・間取り画像を挿入する
- テーマに対するデメリットや注意点も解説する
- お客様の口コミを紹介する
- 期間や流れ、数値を紹介する場合は図表を使う
- 設備や仕様に関する専門用語には解説をつける
- 一般的な建築の内容ではなく、自社の強みに関係するテーマで作る
- 文章は固くなりすぎず親しみやすいトーンで書く
- 記事の末尾で自社の強みを紹介する
- 記事数が多くなる場合は先にカテゴリを分けておく
- テーマを幅広く扱う場合はタグを使用する
- トレンドに関わる記事は積極的に記事の見直しとリライトを行う
それぞれのポイントについて分かりやすく解説します。
【ポイント①】自社の得意分野に関するテーマ・ターゲットを設定する
注文住宅関連の記事作成ポイントの1つ目は、自社の得意分野に関するテーマ・ターゲットを設定することです。注文住宅会社の得意分野はお客様の要望に合わせて住宅を建築することであり、見込み顧客は住宅の購入を検討している人になります。
見込み顧客を集客するためには、見込み顧客が興味を持つテーマの記事を作成することが重要です。
【ポイント②】実際に請け負った物件の事例写真・間取り画像を挿入する
注文住宅関連の記事作成ポイントの2つ目は、実際に請け負った物件の事例写真・間取り画像を挿入することです。注文住宅会社のようなサービスサイトでは、コンバージョン獲得に大きな影響を与えるコンテンツとして事例紹介が注目されており、ほとんどのWEBサイトに設置されています。
間取りや完成物件を文字で表現しようとする人は少ないと思いますが、画像を設置することで文章よりも分かりやすく実際に請け負った物件の情報を伝えることができます。一方、画像を設置したうえで、間取りや物件の特徴を補足する文章を書くことは重要です。
たとえば、外壁を黒のガルバリウムにすることでどのような印象を与えられるのか、鉄骨のスケルトン階段にすることでどのような効果があるのか、といったように、画像を見ただけでは得られない情報を付加することで、さらに効果を高めることができます。
また、画像だけでは奥行きや位置関係が掴みにくい場合があるので、動画も合わせて公開しておくことをおすすめします。
【ポイント③】テーマに対するデメリットや注意点も解説する
注文住宅関連の記事作成ポイントの3つ目は、テーマに対するデメリットや注意点も解説することです。注文住宅にはメリットだけでなくデメリットも当然存在するため、記事の中であえてデメリットに触れないでいると逆に不信感を与えることになります。
同様に、注文住宅を購入して良かったと感じる人だけでなく、失敗した、後悔したと感じる人もいるはずです。注文住宅は高額な買い物なので、特に、「失敗したくない」「後悔したくない」という心理が働きやすくなります。
あえて失敗した、後悔したという人の意見を紹介することで、自分にも当てはまるのか、自分には関係ない問題なのかを確認でき、不安感を解消することができます。
【ポイント④】お客様の口コミを紹介する
注文住宅関連の記事作成ポイントの4つ目は、お客様の口コミを紹介することです。事例紹介と同様にお客様の声もサービスサイトでは問い合わせを獲得できるかを大きく左右されるコンテンツです。
どのような住宅を建築できるかも重視されていますが、実際に購入したお客様がどう感じたのか、どこが良かったのかについても比較・検討する上で重要な要素となっています。
注文住宅のように高額な買い物の場合にはSNSなどの口コミや評判だけでは判断できないので、自社のWEBサイトでお客様のからの意見を紹介することが重要です。
【ポイント⑤】期間や流れ、数値を紹介する場合は図表を使う
注文住宅関連の記事作成ポイントの5つ目は、期間や流れ、数値を紹介する場合は図表を使うことです。
注文住宅はお客様からの問い合わせから実際に購入されるまでにさまざまな工程を踏む必要がありますが、具体的な作業の流れは、初めて住宅を購入するお客様にとってイメージしづらい場合がほとんどです。
打ち合わせの流れを文章にすると分かりにくくなるため、図表や画像を作成して伝えるようにしましょう。断熱性や耐震性、遮音性など材質ごとの数値の違いを伝える場合は、テーブル表を使用すると見やすくなります。
【ポイント⑥】設備や仕様に関する専門用語には解説をつける
注文住宅関連の記事作成ポイントの6つ目は、設備や仕様に関する専門用語には解説をつけることです。注文住宅を購入する場合には建築工法や使用する材質など細かい部分まで打ち合わせることになるため、日常生活では使用しない専門用語が数多く登場します。
専門家としては日常的に使用している単語であっても、一般消費者には理解できない可能性もあるため、設備や仕様に関する専門用語には解説を付けるようにしましょう。
【ポイント⑦】一般的な建築の内容ではなく、自社の強みに関係するテーマで作る
見込み顧客が注文住宅会社に期待しているのは、自分の要望をどれだけ実現できるか、優れたデザインの住宅を建築できるか、機能性は確保できているかです。
注文住宅会社の比較・検討する際には、会社の強みは何か、他社と何が違うのかをチェックされます。
デザインにこだわっているならデザインに関するテーマで、自然素材にこだわっているなら自然素材に関するテーマで記事を作成することで、自社の強みを見込み顧客へアピールできます。
【ポイント⑧】文章は固くなりすぎず親しみやすいトーンで書く
注文住宅関連の記事作成ポイントの8つ目は、文章は固くなりすぎず親しみやすいトーンで書くことです。注文住宅会社の主な顧客は一般消費者なので、IR情報やプレスリリースといった法人向けの記事と同じトーンで書いてしまうと、読者が堅苦しく感じてしまうかもしれません。
自社の主張を押し付けるのではなく、読者に寄り添った親しみやすいトーンで書くことを心がけましょう。ただし、注文住宅の購入はほとんどの顧客の人生で一度だけの大きな買い物であり、フランクすぎる文章では不信感を与えてしまうかもしれません。
親しみやすさと信頼感のバランスを意識して執筆することが重要です。
【ポイント⑨】記事の末尾で自社の強みを紹介する
注文住宅関連の記事作成ポイントの9つ目は、記事の末尾で自社の強みを紹介することです。注文住宅会社が記事を作成する目的は問い合わせを獲得することなので、問い合わせに繋がるCTAを記事の中に設置することが重要です。
ただし、文脈を無視して記事の末尾に自社の強みを紹介すると、読者から読まれないまま離脱されるケースもあります。検索ユーザーは自身が抱える疑問や悩みを解消するために記事を読んでいるので、記事を読んで満足したタイミングで離脱する可能性が高いからです。
記事のまとめの次に自己紹介や依頼するメリット、サービスページへのリンクを設置するだけでは、問い合わせに結びつくとは限りません。記事の末尾にこだわり過ぎず、問い合わせに結びつく箇所にCTAを設置しましょう。
【ポイント⑩】記事数が多くなる場合は先にカテゴリを分けておく
注文住宅関連の記事作成ポイントの10つ目は、記事数が多くなる場合は先にカテゴリを分けておくことです。記事を複数のカテゴリで分類するのは、すべての記事をひとつのカテゴリに分類してしまうと、サイトを訪れた読者が求める記事を見つけるまでに時間がかかるからです。
テーマが異なる記事を作成する場合には、記事を作成する前にカテゴリを作成しておきましょう。あらかじめカテゴリを作成しておくことで、どのような記事を作成すべきなのかを整理することができ、類似した内容で記事を作成してしまうことを防止できます。
【ポイント⑪】テーマを幅広く扱う場合はタグを使用する
注文住宅関連の記事作成ポイントの11つ目は、テーマを幅広く扱う場合はタグを使用することです。複数のカテゴリに共通するテーマで記事を分類したい場合に、カテゴリとタグを併用します。
| カテゴリ | 記事の内容 |
|---|---|
| 注文住宅 | 注文住宅の外観について 注文住宅の間取りについて 注文住宅の補助金について |
| 企画住宅 | 企画住宅の外観について 企画住宅の間取りについて 企画住宅の補助金について |
上記のように、外観や間取り、補助金は、注文住宅だけでなく企画住宅でも扱うテーマです。新たに外観や間取り、補助金をカテゴリに追加すると、複数のカテゴリに記事が分類されてしまいます。
上記の場合には、カテゴリではなくタグとして設定することで、記事の重複を避けたうえで、特定のテーマに関する記事だけを読んでもらうことができます。ただし、記事数がそれほど多くない場合に複数のタグを設定すると、かえって利便性が低下する場合もあります。
【ポイント⑫】トレンドに関わる記事は積極的に記事の見直しとリライトを行う
注文住宅関連の記事作成ポイントの12つ目は、トレンドに関わる記事は積極的に記事の見直しとリライトを行うことです。
デザインや間取り、素材など、住宅のトレンドは毎年変化しています。SDGsが話題になった時には省エネ住宅が注目され、新型コロナが流行した際には玄関近くの手洗い場やテレワーク専用スペースが注目されました。
トレンドの変化に応じてユーザーが使用するキーワードも変化するため、トレンドが変化した際には新たに記事を作成するか、既存記事をリライトすることを検討しましょう。
ただし、トレンドが変わるたびに記事をリライトして内容をコロコロ変えてしまうと、逆に不信感を与えてしまう恐れもあります。過去のトレンドに関する記事はそのまま維持しておき、新たに誕生したトレンドについては別に記事を作成することをおすすめします。
また、法律改正にともなって建築基準が変わる場合には、改正されてから記事をリライトするのではなく、事前に記事をリライトしておく必要があります。
注文住宅に関する記事の推奨文字数と推奨記事作成数
注文住宅の記事の推奨文字数は5,000文字~10,000文字、推奨記事作成数は50ページ~100ページです。
検索上位表示できるかという観点では、記事の文字数は重要ではありません。Googleは、「記事の文字数と記事の品質には関連性がなく、特定の文字数で記事を作成することで検索上位されやすくなるといった設定はない」と明言しています。
文字数よりも、検索ユーザーの検索意図を満たしているか、ユーザーが求める情報が網羅されているかの方が重要です。
一方、記事を閲覧したユーザーから問い合わせを獲得できるかという観点だと、ある程度の文字数が必要です。問い合わせしてみようと思わせる説得力のある文章を加えると、3,000文字~5,000文字程度が目安となります。
文字数が1万文字を超えるとユーザーが離脱するリスクが高くなるため、記事を分割することを検討するのも良いでしょう。記事の作成数については、数ページ程度だとサイトの専門性が十分に評価されない可能性があります。
問い合わせページや施工事例ページ、お客様の声ページなど検索流入を前提としていないページを除き、50ページ~100ページが目安となります。ただし、コピーコンテンツや低品質なコンテンツなどを作成して記事を量産すると、Googleからペナルティを受けてしまうかもしれません。
記事を増やすことだけを意識するのではなく、検索ユーザーが求める記事を作成するようにしましょう。
注文住宅のWEB集客における記事作成の流れ
注文住宅のWEB集客における記事作成の流れは以下の通りです。
- キーワードとテーマを選定する
- 記事の構成を作成する
- 執筆をする
- 関連する画像を用意する
- 記事を公開する
それぞれの手順を具体的に解説します。
STEP1. キーワードとテーマを選定する
注文住宅のWEB集客における記事作成では、始めにキーワードとテーマを選定します。注文住宅の記事作成において始めにキーワードを選定するのは、記事のテーマとターゲットを明確にする必要があるからです。
Googleに代表される検索エンジンは、ユーザーが検索時に使用したキーワードと関連性の高い記事を検索結果に表示する仕組みになっています。検索するユーザーの検索意図と記事の内容がマッチしていなければ、検索結果に記事が表示されず、集客することもできません。
また、記事のターゲットがあやふやなまま記事を作成すると、記事を読んだユーザーは誰に向けた記事なのか分からず、途中で離脱する恐れがあります。キーワードを選定することで検索意図とターゲットを明確に設定することができ、検索上位表示及びコンバージョン獲得が期待できる記事を作成できます。
注文住宅のWEB集客におけるキーワードの選定方法については、前述した「注文住宅の記事作成におけるキーワード選定の方法」で確認してください。
STEP2. 記事の構成を作成する
次に、注文住宅の見込み顧客へ向けたキーワードとテーマを元に、記事の構成を作成します。
▼ 記事の構成を作成する手順は以下の通りです。
- 記事を作る目的を確認
- ペルソナを設定
- キーワードを設定
- 検索意図を確認
- 検索上位記事を確認
- タイトル・見出しを設定
注文住宅に関連した記事の構成を作成する場合には、読者をCTAへ誘導する導線を作成することが重要になります。記事を作成する目的は問い合わせを獲得することであり、記事を読んだ読者を満足させただけでは意味がないからです。
たとえば、「注文住宅会社の選び方」という記事に選び方だけを解説しても、見込み顧客が自社を選択するとは限りません。選び方を解説した上で、問い合わせしてみようと思わせる導線を用意し、CTAに誘導する必要があります。
STEP3. 執筆をする
次に、作成した記事の構成に従って、注文住宅の見込み顧客へ向けて記事を執筆します。
▼ 執筆する際のポイント・注意点は以下の通りです。
- 記事のトーン・マナーを統一する
- 結論から先に書く
- 正しい文法で書く
- 冗長表現を使用しない
- キーワードを詰め込まない
STEP4. 関連する画像を用意する
次に、注文住宅の記事の内容と関連する画像を用意し、サムネイル画像とアイキャッチ画像を作成し、記事に設置します。
▼ 注文住宅に関連した画像は以下の通りです。
- 注文住宅会社の外観画像
- 注文住宅会社へのアクセスマップ
- 過去に建築した住宅の外観・内装・間取り
- 住宅を購入したお客様の画像
STEP5. 記事を公開する
最後に、完成した記事を注文住宅のWEBサイトで公開します。
▼ 記事を公開する際の注意点は以下の通りです。
- 半角英数字でパーマリンクを設定する
- ディスクリプションを設定する
- カテゴリを設定する
- 誤字脱字がないかを確認する
- コピペ記事になっていないかを確認する
- 著作権違反になっていないかを確認する
- スマホで閲覧した際にレイアウトが崩れていないかを確認する
注文住宅に関連する記事作成の注意点
注文住宅会社のWEBサイトが記事を制作する際の注意点は、以下の通りです。
- 間違った情報を掲載することは許されない
- コピーコンテンツを作成しない
- 著作権に違反しない
注文住宅会社のWEBサイトを運営する際のポイントは、以下の通りです。
- テーマ・ターゲットは広めに設定する
- 中期的な施策として運用する
それぞれの注意点・ポイントについて分かりやすく解説します。
建築基準法など法律に関する内容は誤りに注意する
注文住宅に関連する記事には、建築基準法など法律に関する内容について正確な情報を掲載する必要があります。注文住宅に興味を持つユーザーは、建築基準法など住宅に関わる法律の知識がない場合がほとんどです。
さらに、注文住宅会社が運営するWEBサイトであれば、掲載されている情報は正確なものであり、法律に関する情報についても間違いがあるかもしれないとは思わないでしょう。
建築基準法など法律に関する内容に間違いがあれば、信頼できない会社、安心して任せられない会社だとみなされるかもしれません。法令を引用するなどの対策は重要ですが、法律に関する情報については正確な情報を掲載し、誤解を招くような表現を避けることが重要です。
単純なミスであっても間違いがあればユーザーが大きな損失を受ける恐れもあり、企業としての信頼性も大きく低下する恐れがあります。建築基準法など法律に関する内容を扱う場合には、注文住宅の専門家として細心の注意を払って記事を作成するようにしましょう。
コピーコンテンツや著作権に注意する
注文住宅に関連する記事では、コピーコンテンツを作成したり、著作権に違反したりすることは許されません。コピーコンテンツとは、外部WEBサイトに掲載されている情報をそのまま、あるいは一部を改変して自社のコンテンツとして公開したコンテンツです。
第三者が作成した記事の文章や画像を許可なく自社のWEBサイトで使用することは、原則として禁止されています。記事の内容を紹介することを目的とする場合においても、引用元を明示するなど引用ルールを守って掲載しなければいけません。
許可なく使用した文章や画像が著作物である場合には著作権違反となる恐れがあり、著作権違反に該当しない場合においてもモラル・マナー違反として問題が発生します。
コピーコンテンツを作成することは注文住宅会社としての信頼性を大きく棄損することになり、顧客からの信頼を失うことに繋がるでしょう。また、Googleから記事がコピーコンテンツだと判断された場合、インデックスから除外されたり検索順位が大きく低下したりするなど、ペナルティを受ける恐れもあります。
外部のWEBサイトから盗用してコンテンツを作成するのではなく、独自のコンテンツを作成するようにしましょう。
テーマ・ターゲットは広めに設定する
注文住宅会社のWEBサイトでは、テーマ・ターゲットは広めに設定するようにしましょう。「注文住宅会社の選び方」といった顕在層に向けたコンテンツだけだと、作成できるコンテンツが非常に限定されるだけでなく、競合ページも非常に多くなってしまいます。
注文住宅会社のWEBサイトがコンテンツSEOによって集客する場合は、以下のような見込み顧客が興味を持つテーマを幅広く扱うことが重要です。
- 注文住宅会社を比較検討している顕在層に向けたコンテンツ
- 注文住宅にするかどうかを検討している段階のユーザーに向けたコンテンツ
- 住宅の購入を検討している段階の潜在層に向けたコンテンツ
- 住宅の購入をまだ検討していない非認知層に向けたコンテンツ
潜在層・非認知層も含めたテーマにすることで、さまざまなコンテンツを作成できます。
中期的な施策として運用する
注文住宅会社のWEBサイトにおけるコンテンツSEOは、中期的な施策として運用することをおすすめします。
▼ WEB集客の手法には、コンテンツSEO以外に以下のようなものがあります。
- リスティング広告
- SNS広告
- SNSアカウント運用
- メルマガ配信
いずれも、施策を実施してすぐに集客効果が期待できる手法です。
一方、コンテンツSEOはすぐに効果が期待できる手法ではありません。WEBサイトの運用を始めたばかりだと、効果が出るまでに半年~1年ほどかかる場合もあります。数ヶ月程度での効果を期待するのではなく、中期的な施策として運用するようにしましょう。
注文住宅の記事作成で参考になる例
【株式会社ステーツ】

株式会社ステーツのコラム記事は、ニッチなテーマでもポイントが多く記載されているためユーザーの役に立つコンテンツとなっています。
例えば、「ネコと快適に住む理想の家」のテーマでは
- 抑えておきたポイントが6つ
- 取り入れたい設備、アイテムが3つ
- 事例が3つ
紹介されているため、この記事を読めば他のサイトを見なくても良いと思うほど高いレベルで記事を作成しています。
また、見出しごとに画像を入れているためイメージしやすくなっているのもポイントです。ユーザーにイメージさせる上で、特にこのサイトが優れている点は殆どの記事に参考間取り図が挿入されている事です。
これにより文章だけではなく、実際の間取りのイメージや生活をするイメージを持つことが出来ます。手間暇をかける事で他社コンテンツと差別化をおこない、専門性と独自性を高めている良い記事作成の例と言えます。
まとめ
今回は、初めてWEB集客に取り組む注文住宅会社のWEBサイト運営者に向けて、WEB集客で記事を作成するメリットからキーワード選定の方法、記事作成ポイント、推奨文字数と推奨記事作成数、記事作成の流れまで解説しました。
注文住宅会社がWEB集客を実施する場合、顕在層だけでなく潜在層にもアプローチすることが重要です。顕在層は問い合わせに繋がりやすい一方で、競争が激しくなるため集客コストが高くなりやすいというデメリットがあります。
注文住宅の購入を視野に入れていない潜在層にアプローチすることで、リードナーチャリングを実施することができ、問い合わせに繋げることが可能です。コンテンツSEOは低コストで潜在層へアプローチできる集客手法なので、この記事で紹介した記事作成ポイントを参考に記事を作成してみましょう。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
 コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/06/09
コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/09
コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/07/25
コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/07/252025/07/25
-
 コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/06/09
コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOロングテールキーワードとは|SEOで重要な理由と選び方を解説2025/06/09
コンテンツSEOロングテールキーワードとは|SEOで重要な理由と選び方を解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOWebライティングとは?手順やポイントを初心者向けに解説2025/06/09
コンテンツSEOWebライティングとは?手順やポイントを初心者向けに解説2025/06/092025/06/09