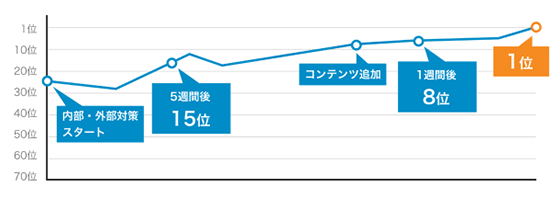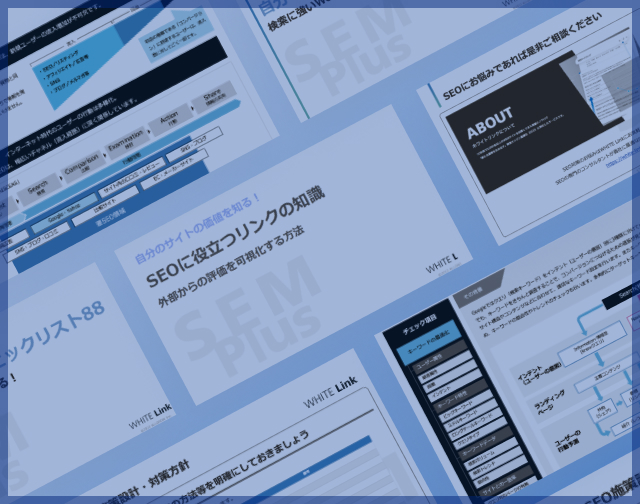離脱率とは│計算方法と改善方法・平均目安を解説

WEBマーケティングやアクセス解析で使うことが多い用語の1つに「離脱率」があります。本記事では「直帰率との違い」「離脱率とは何と何の割合を示しているのか」「離脱率の計算式」「離脱率の平均」などの疑問から「離脱率の改善方法」まで、初心者向けに分かりやすく解説しました。
離脱率とは
「離脱率」とは、WEBサイトに訪れたユーザーが見た全ページの中で、最後に訪れたページの割合です。ここで言う「離脱」は、サイト内の他のページへ移動しないままブラウザを閉じた場合、もしくは外部サイトへ移動した場合を指します。
例えば、ある2人のユーザーがそれぞれページAを閲覧し、次にページBを閲覧した後でサイトから離脱した場合、ページAの離脱率は0%、ページBの離脱数は100%とカウントされます。
2人のユーザーがそれぞれページAとページBを最後にサイトから離脱した場合は、ページAとページBの離脱率はそれぞれ50%になります。WEBマーケティングの世界では「このページの離脱率が高いから改善が必要」といった文脈で利用されます。
離脱率の計算方法
離脱率は、(離脱した訪問者数÷総訪問者)×100で計算することができます。
例えば、あるWEBサイトの「商品ページA」に1週間で500人が訪れ、そのうちの200人がそのページで何もクリックせずにWEBサイトを離れたとします。
この場合の離脱率は、(200÷500)×100=40%のように計算します。
離脱率はページ単位でも、サイト単位でも同じ計算式を使います。
特定のページの離脱率(%)=特定のページの離脱数÷特定のページのPV数×100
WEBサイト全体の離脱率(%)=サイト全体の離脱数÷サイト全体のPV数×100
直帰率との違い
離脱率に似た用語に直帰率があります。直帰率(Bounce Rate)とは、WEBサイトを訪れたユーザーが、他のページを閲覧せずにWEBサイトを離れた割合を指します。
直帰の定義を簡単に説明すると以下になります。
「ユーザーがあなたのWEBサイトのあるページにアクセスします。」→「 そのユーザーが他のページに移動することなく、WEBサイトから離脱します。」
このように「1ページだけを見てサイトを離れる」行動が直帰です。
直帰率が高いと、訪問したユーザーが「求めていた情報やサービスが見つからなかった」もしくは「目的のページではなかった」ことを示唆している可能性があるため、ページの改善が必要になります。
直帰率の計算方法
直帰率は、以下の計算式で算出されます。
直帰率(%)=特定のページの直帰数÷特定のページから始まるセッション数×100
例えば、100人のユーザーが初めにページAを閲覧し、30人がページAで離脱した場合、直帰率は30%になります。
▼ 離脱率との違いは以下になります。
100人のユーザーが初めにページAを閲覧し、30人がページAで離脱し、70人がページBへ移動した後で離脱した場合、直帰率と離脱率はそれぞれ以下のようになります。
| ページA | ページB | |
|---|---|---|
| PV数 | 100PV | 70PV |
| 離脱数 | 30 | 70 |
| 離脱率 | 30% | 100% |
| 直帰数 | 30 | 0 |
| 直帰率 | 30% | 0% |
離脱率が高い=悪いわけではない
一般的には離脱率は低い方が良いとみなされていますが、ページの目的によっては高くても問題がない場合もあります。なぜなら、ページに訪れたユーザーは必ずどこかのページで離脱してしまうからです。
例えば、集客用のメディアサイトとランディングページを別のドメインで作成している場合、離脱率が高くても問題ありません。
- 集客用のメディアサイト、ページ:https://white-link.com/sem-plus/
- ランディングページ:https://plusword.white-link.com/
何故なら、集客用のページから、ランディングページへ離脱してもらうことがサイトの目的だからです。
上記のように離脱率を改善すべきかどうかは、サイトやページの目的によって異なります。ただし、次の項目で説明するページに関しては離脱率が高い場合は改善する必要があります。
離脱率が高い場合は改善する必要があるページ
以下に該当するページに関しては、離脱率が高い場合は改善する必要があります。
- エントリーフォーム・チェックアウトページ
- 流入が多いページ
エントリーフォーム ・チェックアウトページ
エントリーフォーム・ECサイトのチェックアウトページなど、コンバージョン手前のページの離脱率が高い場合は、改善する必要があります。WEBサイトの目的が問合せや申し込み、商品の購入である場合、エントリーフォームやチェックアウトページはサイト運営者にとっては離脱して欲しくないページです。
ユーザーがエントリーフォームやチェックアウトページで離脱すると言うことは、サービスの申し込みや商品の購入する意思があるにも関わらず、フォームの入力が面倒で離脱した可能性があります。
エントリーフォームを改善して、離脱率を低下させ、コンバージョン数を増やしましょう。尚、エントリーフォームの改善方法については別の記事で詳しく解説しています。
流入が多いページ
流入が多いページは、優先して離脱率を改善する必要があります。なぜなら、流入が多いページで離脱率が高いということは多くのユーザーからコンバージョンを獲得するチャンスを逃していることになるからです。
PV数が10のページより、PV数が1万のページの離脱率を改善した方が、費用対効果が高くなります。ただし、PVが少ないページでも、問い合わせページへ移動する割合が高いページなどコンバージョンに近いページについては、離脱率を優先して改善した方が効果的な可能性が高いです。
離脱率をGA4で確認する方法
サイトの離脱率は、Googleが提供しているGoogleアナリティクス4(GA4)で確認できます。
▼ Googleアナリティクス4(GA4)で、離脱率を確認する手順は以下の通りです。
- 画面左側のメニュー「探索」をクリック
- 「自由形式」をクリック
- 「ディメンション」をクリック
- 「ページ/スクリーン」の「ページタイトルとスクリーン名」横のチェックボックスをクリック
- 画面右上の「インポート」をクリック
- 「ディメンション」の「ページタイトルとスクリーン名」を「行」へドラッグ
- 「指標」をクリック
- 「ページ/スクリーン」の「離脱数」と「閲覧開始数」横のチェックボックスをクリック
- 画面右上の「インポート」をクリック
- 「指標」の「離脱数」と「閲覧開始数」を「値」へドラッグ
- 「離脱数」と「閲覧開始数」から離脱率を計算する
尚、Googleユニバーサルアナリティクス(UA)には、「離脱率」という項目がありますが、Googleアナリティクス4(GA4)に「離脱率」という項目は存在しないので、「離脱数」と「閲覧開始数」から離脱率を計算する必要があります。
離脱率の計算方法は「離脱数÷閲覧開始数」×100で算出できます。
離脱率に平均目安はない
離脱率の平均という概念は、WEBマーケティングやWEBのアクセス解析の文脈で用いられるものではありません。理由は、離脱率が特定のページやセッションに基づいて個別に測定される指標であるため、サイト全体の「平均離脱率」を計算しても意味が無いためです。
また、ECサイトを例とした場合、商品ページと決済ページでは、ユーザーの行動や期待が大きく異なるため、それぞれのページの離脱率を直接比較しても意味がありません。
離脱率の改善方法
離脱率の改善方法は以下の7つです。
- EFOをおこなう
- ページの表示速度改善をする
- ページのデザイン・フォントを見直す
- ページタイトルとコンテンツを一致させる
- ユーザーに分かりやすいサイト内動線を作る
- 内部リンクを適切に設置する
- コンテンツを改善する
EFOをおこなう
EFOとはエントリーフォーム最適化のことです。ユーザーがエントリーフォームから途中離脱する理由として、「入力項目が分かりにくい」「入力項目が多い」「全角・半角を間違えるとエラーが発生する」などが考えられます。
そのため、「フォームの入力項目を減らす」「自動入力機能を入れる」などをおこない、ユーザーが入力する際の負担が少なくなるようにしましょう。
ページの表示速度改善をする
ページの表示速度が遅い場合は、ユーザーはストレスを感じるためページを離脱する可能性が高くなります。ページの表示速度を改善する方法は以下の通りです。
- 画像ファイルの形式を変更する
- 画像のデータ量を減らす
- ソースコードを圧縮する
- 不要なプラグインを削除する
上記対応をおこなったら、Googleが提供するpage speed insightsでページの表示速度が改善されたか確認してみましょう。
ページのデザイン・フォントを見直す
ページのデザインやフォントを見直すことで、離脱率を改善できます。なぜなら、ユーザビリティが低いサイトは、ユーザーに強いストレスを与えるからです。特に、モバイルユーザーにとっての使いやすさ、読みやすさは離脱率の改善で重要な要素となっています。
スマホでページを開いた時にレイアウトが崩れていないか、スマホからでも読みやすいフォントサイズになっているか、クリックしやすいボタンの配置になっているかなど、細かく確認しましょう。
ページタイトルとコンテンツを一致させる
ページタイトルとコンテンツが一致していない場合、ユーザーはページを離脱する可能性が高くなります。なぜなら、ほとんどのユーザーはタイトルを確認したのちに、ページを訪問するからです。ページタイトルと、ページの内容が一致していない場合、ユーザーはすぐに離脱します。
例えば、「パンの作り方」というタイトルのページにチャーハンの作り方が書いていた場合、ほとんどのユーザーはページになんらかの不具合があったか、手違いがあったと考えるでしょう。
ページタイトルとコンテンツの内容が一致しているか、全ページ確認しましょう。
ユーザーに分かりやすいサイト内動線を作る
ユーザーに分かりやすいサイト内動線を作ることで、離脱率を改善できます。なぜなら、ユーザーが次に見るべきページの発見がしやすく移動も容易になるからです。ページ内に他のページへ移動するためのリンクがない、もしくは見つけにくい状態だと、諦めて離脱することになるでしょう。
サイト全体にグローバルナビゲーションや、パンくずリストを設置、ページ単位ではテキストリンクをバナーに変更するなどをおこない、ユーザーにとって分かりやすい動線を作成しましょう。
内部リンクを適切に設置する
内部リンクを適切に設置することで離脱率を防止することが出来ます。ユーザーが目的のページに辿り着けない場合や、再検索しないといけない場合は離脱の原因となります。
例えば、記事コンテンツ内に知らない専門用語が出てきた場合、用語の意味が気になったユーザーは、ページから離脱してGoogle検索で調べるかもしれません。
このような離脱を防ぐために、サイト内で関連するページへの内部リンクを適切に設置して対応します。特に流入数が多いページの内部リンクはユーザー行動を意識して最適な動線を作りましょう。
コンテンツを改善する
コンテンツの内容をユーザーにとって価値の高いものに改善することで離脱率を低下させることができます。価値の高いコンテンツとは、ユーザーが求めている回答や情報が分かりやすく書いてあることや、ここでしか得る事が出来ないオリジナルの情報、誰かの実体験を元にした内容などを指します。
サイトに訪れたユーザーが満足するようなコンテンツであれば、他のページへ遷移したり問合せに繋がる可能性が高まります。
まとめ
今回は、離脱率について解説をおこないました。離脱率とは、特定のページで離脱したセッションの割合です。エントリーフォームのようにコンバージョンに近いコンテンツが設置されたページの離脱率が高い場合、改善することで大きな効果が見込めます。
また、TOPページや流入が多いページの離脱率を改善することで、サイト全体のPV数を向上することも可能です。サイト全体、あるいは特定のページの離脱率が高い場合は、原因を特定し改善するようにしましょう。
【その他のアクセス解析指標】
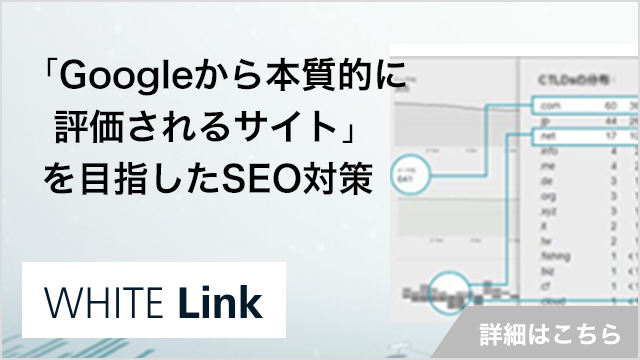
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事