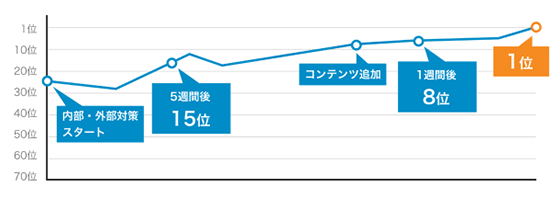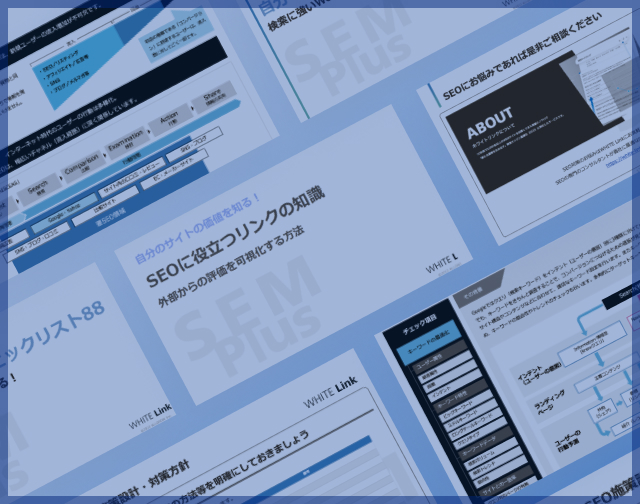エントリーフォーム最適化(EFO)とは|意味・改善方法を解説

WEBマーケターやWEBメディアの担当者なら、「EFO」という単語を目にする機会が多いと思います。しかし、具体的な意味や重要性についてはよく分からないのではないでしょうか?この記事では、EFOの概要から重要性、エントリーフォームから離脱する要因、成功させるためのポイントについて、初心者にも分かりやすく解説します。
EFO(エントリーフォーム最適化)とは
「EFO」とは、現在使用しているエントリーフォームをユーザーに最適化することで、エントリーフォームからの途中離脱を防ぎ、最後まで入力してもらうようにすることです。
「Entry Form Optimization」の頭文字を取って、EFOと呼ばれています。
エントリーフォームの最適化を行う理由、それはWEBサイトやページに訪れたユーザーがフォームに到達したにも関わらず申込みや会員登録に至っていないという問題を解決するためです。
入力項目の分かりづらさや入力した内容がリセットされてしまうなど、ユーザーに少しでもストレスや使いづらさを感じさせてしまうと、せっかく入力フォームまでたどり着いたにも関わらず、途中離脱を招く確率が高くなります。
途中離脱を防ぎ、完了率を高めるために入力フォームを改善することが、EFOです。
WEBマーケティングにおけるエントリーフォームの重要性
WEBマーケティングにおいてエントリーフォームが重視されているのは、リード獲得の大半がエントリーフォームを経由しているからです。
HubSpotの調査によると、Webサイトに設置された入力フォームを経由してリード獲得を行う企業は、全体の74%を占めているそうです。また、有効回答数173のうち130の企業が、入力フォームを利用していると回答しています。
さらに、「コンバージョン獲得に効果を発揮したツールは何か」というアンケートでは、49.7%に企業が入力フォームと回答したそうです。
【参考資料】:入力フォームの離脱を防ぐEFOとは?7つの施策と事例、おすすめツール
SEO対策やコンテンツマーケティングなどの施策を行ってサイトへ集客できたとしても、サイト上で資料請求や会員登録が完了しなければコンバージョンは獲得できません。
CVRを高めるためにはフォームの改善が重要
WEBサイトのCVRを高めるには、入力フォームの改善が欠かせません。なぜなら、ユーザーが最後まで入力しなければ、個人情報を取得できないからです。FullStory社の調査によれば、入力フォームから一度離脱してしまうと、67%のユーザーは戻ってきません。
【フォーム離脱後のユーザー行動】
- フォームには2度と戻らない:67%
- 後から入力し直す:13%
- 別のサイトに遷移する:10%
- カスタマーサービスに直接問合せる
【参考資料】:Form abandonment: How to avoid it and increase your conversion rates
つまり、コンバージョン率を高めるにはエントリーフォームの問題を解決し、途中離脱を大幅に軽減させるための「EFO」が重要だということです。
ユーザーがフォームから離脱する要因
▼ FullStory社の調査によれば、ユーザーが入力フォームから離脱する要因は以下の通りです。
- セキュリティ上の懸念:29%
- フォームの長さ:27%
- 広告やアップセル:11%
- フォームが長すぎる:10%
【参考資料】:Form abandonment: How to avoid it and increase your conversion rates
【WPFormsの調査結果】
- セキュリティ上の理由
- 無料のツールなどフォームに何かが含まれている場合
- 長さや複雑さ
- ドロップダウンフォームフィールドを持つ
- 電話番号・住所・年齢の入力
- 「送信」という単語を使用している
- 2列のフォーム
- フォームのCAPTCHAをオンにする
- 複雑なチェックアウトプロセス
- ユーザーアカウントの作成
- 信頼バッジがない
【参考資料】:101 Unbelievable Online Form Statistics & Facts for 2023
上記のように、ユーザーはさまざまな理由で入力フォームから離脱しています。
フォームの入力項目数が6以上だと離脱率が高まる
入力フォームからの離脱で注目すべき点は、入力項目数が6以上だと離脱率が高まることです。
HubSpotが行った、自社の顧客のランディングページにおける入力フォームの項目数とコンバージョン率の関係の調査では、フォームの入力項目数が3つだとCVRがもっとも高くなり、6以上だと離脱率が高くなっています。
【参考資料】:入力フォームの離脱を防ぐEFOとは?7つの施策と事例、おすすめツール
「フォームの入力項目数が6以上だと離脱率が高まる」というのはHubSpotの調査結果にすぎないので、すべての入力フォームに当てはまるとは限りません。しかし、フォームの入力項目数がユーザーの離脱率に影響する可能性は高いと言えるでしょう。
EFOの具体的な改善ポイント
前述したように、ユーザーはさまざまな理由で入力フォームから離脱しており、離脱率を低下させるためには入力フォーム自体を改善する必要があります。
▼ EFOの具体的な施策は以下の通りです。
- 入力項目は最小限に絞る
- 入力項目は見やすく明記する
- 必須項目と任意項目を明確に分ける
- 質問項目はプルダウンではなくラジオボタンにする
- 住所やフリガナの自動入力機能を導入する
- 入力モードの切り替えを設定する
- 入力例の表示をする
- エラーの内容とエラー箇所を表示する
- 入力ステップを表示する
- フォームの入力内容を保存させる
- ヘッダーやフッターを削除して、不要なリンクを減らす
- 離脱防止のポップアップを導入する
- セキュリティに関する文言を表示する
入力項目は最小限に絞る
フォームページが長過ぎるという課題に対しては、入力項目を最小限に絞ることがEFOの重要なポイントです。ユーザーがフォームを見たときに入力項目が多く面倒だと感じれば、それだけ途中離脱の確率が高くなります。
できる限りユーザーの負担を軽減するためにも、氏名や電話番号、メールアドレスなど最低限必要な項目だけを残し、ふりがなやメールアドレスの再入力欄、FAX番号といった、必須ではない入力項目をなくすことが重要です。
どうしても入力項目が増えてしまう場合には、入力が必須の項目と任意の項目に分けるようにしましょう。また、入力項目が多くなりそうなときには、STEPごとに分けて各ページの入力項目を少なくすることも効果的です。
STEPで項目を分ける場合には、次の入力フォームに移動するまでの読み込み時間を減らす、入力完了までにかかる時間を明記するといった工夫をすることで、ユーザーの心理的な負担を減らすことができます。
入力項目は見やすく明記する
入力項目の分かりづらさを解消する場合は、それぞれの項目が必須項目であるのか任意項目であるかを見やすく明記することがEFOの重要なポイントです。
入力項目の横に必須・任意と表記したり、必須項目と任意項目を異なる文字の大きさや色で表示したりすることで、一目見ただけでも分かりやすいフォームになります。
必須項目と任意項目を明確に分ける
必須項目と任意項目を明確に分け、必須項目の入力漏れが発生しないようにすることも、EFOの重要なポイントです。
前述したように、必須項目と任意項目を分けることでユーザーの入力する負担は軽減されます。一方で、入力する項目としなくても良い項目が存在することから、必須項目に入力し忘れてしまうケースも発生するわけです。
必須項目への入力ができていないまま完了ボタンを押してしまうと、再度入力し直すことになったり、入力し忘れた項目まで戻って入力することになり、面倒に感じてしまうかもしれません。
入力するボックスに色を付けておき、入力が完了したら色が消えるようにするか、別の色に変化するようにしておくと、どこまで入力したかが一目瞭然となり、入力忘れを防止することができます。
また、必須項目をすべて入力するまでは完了ボタンを表示しないようにする、入力完了前にクリックした場合はボタンが機能しないようにするなどの対策も効果的です。
質問項目はプルダウンではなくラジオボタンにする
質問項目はプルダウンにするのではなくラジオボタンで選択できるようにすることも、EFOの重要なポイントです。
プルダウンの場合、一度ボックスをクリックし、表示された項目の中から該当する項目をクリックするという、2回のアクションが必要になります。省スペースで設置できる点がメリットです。
一方、ラジオボタンなら初めから項目が表示されているため、クリックするのは1回だけです。ただし、質問項目をすべて表示するスペースを確保する必要があります。
性別の選択など質問項目が少ない場合や、入力フォームとして確保できるスペースに余裕がある場合は、ユーザーの手間を減らせるラジオボタンがおすすめです。ただし、項目数が多い場合やスペースに余裕がない場合は、プルダウンの方が適しています。
入力フォームの形式や状況に合わせて、プルダウンとラジオボタンのどちらを選択すべきかを検討しましょう。
住所やフリガナの自動入力機能を導入する
住所やフリガナの自動入力機能を導入することも、効果的なEFOです。
多くのユーザーは入力フォームに住所やフリガナを入力することが面倒だと感じていますが、郵便番号を入力するだけで都道府県や市町村までを自動で入力してくれる自動入力機能は、ユーザーの負担を大きく軽減できます。
都道府県や市町村名には普段使用しないような漢字が使われていることも多く、入力ミスが発生しやすいポイントです。自動入力機能を導入しておけば、入力ミスを防止できるだけでなく、入力時間を短縮させる効果も期待できます。

入力モードの切り替えを設定する
スマートフォンやタブレットなど、モバイル端末からのアクセスが多い場合、自動的に入力モードが切り替わるように設定することも、EFOの重要なポイントです。
パソコンのキーボードを使って入力する場合と比べると、モバイル端末から入力する場合は、半角と全角の切り替えや文字と数字の切り替えは手間がかかります。
ユーザーが入力するボックスをタップした段階で自動的に入力モードが切り替わるようになっていれば、モバイル端末からでもスムーズに入力できるようになり、途中離脱を防止することができます。
また、スマートフォンでは小さい画面上で入力する必要があり、小さい文字だと読みづらく感じるかもしれません。モバイル端末からのアクセスに対しては、パソコンからアクセスした場合より文字を大きく表示したり、フォーム自体を大きく表示したりすることも効果的です。
入力例の表示をする
フォームへの入力に不慣れなユーザーからの利用が多い場合、下記画像のように入力例の表示をすることも、EFOの重要なポイントです。

氏名であれば苗字と名前の間にスペースを入れるべきか、電話番号にはハイフン(-)を入れる必要があるのかなど、悩む必要がなくなります。
エラーの内容とエラー箇所を表示する
エラーの内容とエラー箇所が分かるようにすることも、EFOの重要なポイントです。
フォームへの入力ミスでエラーが出ることはよくある話ですが、どこが間違っていたのか、なぜエラーになったのかが分からないと、ユーザが途中で入力を諦め、離脱する要因になります。

上記画像のように、入力方法が間違っているボックスの色を赤くしたり、「メールアドレスの形式が正しくありません。」「電話番号のフォーマットが間違っています。」といったように何が間違いなのかを表示したりすることで、どこを修正すれば良いのか、どのように修正すれば良いのかが分かりやすくなります。
入力ステップを表示する
入力する項目が1画面に納まりきらず、複数ページに分けて入力してもらう場合、下記画像のように入力ステップを表示し、入力完了までの時間をイメージしやすくすることも、EFOの重要なポイントです。

ゴールが分からないまま入力するのは、ユーザーにとって負担になる作業です。どこまで入力したのか、あとどのくらいで入力が完了するのかも分かるため、途中離脱の防止につながります。入力フォームに目安の時間を書いておくことも効果的です。
フォームの入力内容を保存させる
フォームの入力内容を保存する仕様に変更することも、EFOの具体的な施策です。ユーザーの中には、エントリーフォームに入力している途中で、一つ前の画面に戻りたいとBackspaceを押してしまうケースもあります。
Backspaceを押して前のページに戻ると入力した情報が消えてしまうため、ユーザーは再度入力し直す必要があり、面倒になって入力することを諦めてしまうことにつながります。
ユーザーが戻ってしまうことを防ぐのは困難なので、入力フォーム側で入力した内容が消えない仕様にすることが大切です。特に、入力項目が多いフォームでは、入力内容を保存する仕様は必要不可欠と言えるでしょう。
導入できない場合には、修正ボタンを設置するなどして、入力した情報が消えないようにする対策が必要です。
ヘッダーやフッターを削除して、不要なリンクを減らす
フォームへの入力とは関係のないヘッダーやフッターの表示をなくし、必要のないリンクを削除することも、途中離脱の防止に効果的なEFOです。
入力フォームにヘッダーやフッターが表示されていると、ユーザーが入力作業に集中できず、別のことに興味を持ってしまう恐れがあります。モバイル端末で入力する場合だと、リンクを誤タップしてしまうケースもあるでしょう。
設置されているリンクがクリックされれば入力フォームから途中離脱となってしまうため、必要のないリンクは設置しないようにするか、入力時には表示されないようにしておきましょう。
離脱防止のポップアップを導入する
離脱防止のポップアップを導入することも、途中離脱の防止に効果的なEFOです。入力フォームからユーザー離脱するケースとして、意図的な離脱だけでなく、誤操作で離脱するケースも想定できます。
「入力完了」のボタンをクリックするつもりで「戻る」ボタンをクリックしてしまったり、普段の癖でブラウザの戻るボタンをクリックしてしまったりすることもあるでしょう。スマートフォンでは、誤タップからの離脱もあります。
自分の手違いで入力フォームから離脱したからといって、すべてのユーザーが再度入力してくれるとは限りません。
上記のように、意図しない離脱を防止するには、離脱防止のポップアップ機能が効果的です。
ユーザーがページを閉じようとしたり、ブラウザの戻るボタンをクリックしたりしたタイミングでポップアップが表示されれば、入力フォームから離脱することなく入力操作を続けることができます。
セキュリティに関する文言を表示する
セキュリティに関する文言を表示することも、途中離脱の防止に効果的なEFOです。入力フォームには個人情報を入力するため、不審に感じたユーザーの多くは入力を避けています。
安全な入力フォームであることをアピールする場合、セキュリティに関する文言を表示すると効果的です。個人情報の扱いに関する同意を求めるとともに、プライバシーポリシーへのリンクを設置しておけば、プライバシーポリシーを確認したユーザーへ安心感を与えることができます。
また、サイトを常時SSL化しておくことも、入力フォームの信頼性向上に効果的です。
SSL化とは、インターネット上のデータ通信を暗号化することです。SSL証明書を取得し、サイトアドレスをhttpからhttpsへ変更することで、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信を用いた暗号化通信が可能になり、個人情報の漏えいを防ぐことができます。
SSL化については別記事で詳しく解説しているので、興味がある方は以下ページをご確認ください。
EFOを成功させるための3つのSTEP
▼ EFOを成功させるための手順は以下の通りです。
- 離脱につながりそうな箇所を見つける
- 仮説を立てながら対策を決定する
- 検証と改善を繰り返す
【STEP1】離脱につながりそうな箇所を見つける
EFOを成功させるためには、はじめに離脱につながりそうな箇所を見つける必要があります。なぜなら、原因が分からないまま対策しても効果が出るかどうか分からない上に、やみくもに対策するのは効率が悪いからです。
離脱につながりそうな箇所は、前述した「ユーザーがフォームから離脱する要因」と自社の入力フォームを確認することで発見できます。また、入力フォームからの離脱率をチェックし、そもそもEFOが必要な状態なのかを確認しておきましょう。
EFOはコンバージョン率を高めることが目的なので、離脱率が低い状態なら慌てて改善する必要はないかもしれません。
LPOについては別記事で詳しく解説しているので、興味がある方は以下ページをご確認ください。
【STEP2】仮説を立てながら対策を決定する
離脱につながりそうな箇所を発見できたら、次は仮説を立てながら取るべき対策を検討します。
例えば、入力する項目が多すぎることが原因だと想定した場合、以下のような対策を検討します。
- 入力項目は最小限に絞る
- 必須項目と任意項目を明確に分ける
- 入力ステップを表示する
必ずしもすべての対策が必要なわけではありません。自社の入力フォームを確認し、最も効果がでそうな対策から実施しましょう。
【STEP3】検証と改善を繰り返す
取るべき対策が決定したら、対策を実施し検証と改善を繰り返します。
入力フォームからの離脱率は数値で確認できますが、実際にどのような理由で離脱したのかは確認できないため、どのEFOが効果的だったのか、効果が出なかったEFOはどれなのかは分からないからです。
EFOの検証と改善を繰り返す場合は、ABテストを実施しましょう。「ABテスト」とは、2種類の施策をランダムに実施し、それぞれの結果を比較することで、どちらが効果的な施策なのかを確認する手法です。
例えば、質問項目をプルダウンにするパターンとラジオボタンにするパターンで離脱率にどのくらい変化があるかを確認し、効果が高かった方を正式なEFOとして採用します。
EFOに関するよくある質問
EFOに関するよくある質問と回答をご紹介します。
EFOの読み方は?
EFOの読み方は「イーエフオー」です。
入力フォームの離脱率はどのくらいでしょうか?
入力フォームの離脱率は、エントリーフォームから集客するユーザーの業種・業界やエントリーフォームの形式によって異なります。
「6 Steps For Avoiding Online Form Abandonment」の記事によれば、81%の人が離脱したことがあり、そのうち59%のユーザーが1ヵ月以内に離脱をしたそうです。
まとめ
今回は、EFOの概要から重要性、エントリーフォームから離脱する要因、EFOの具体的な施策、成功させるためのポイントについて解説しました。
商品・サービスの購入や資料請求、会員登録などをコンバージョンに設定してWEBビジネスを展開する場合、集客した見込み顧客を入力フォームへ誘導しても、入力途中で離脱されてしまうと、コンバージョンは獲得できません。
入力フォームから離脱される要因を特定し、適切なEFOを実施し、効果の検証と改善を繰り返すことで、離脱率を改善することが重要です。
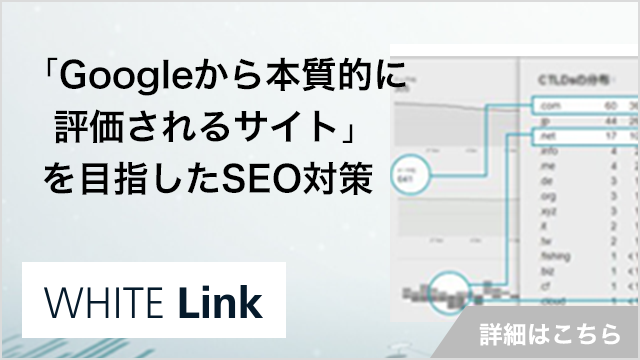
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事