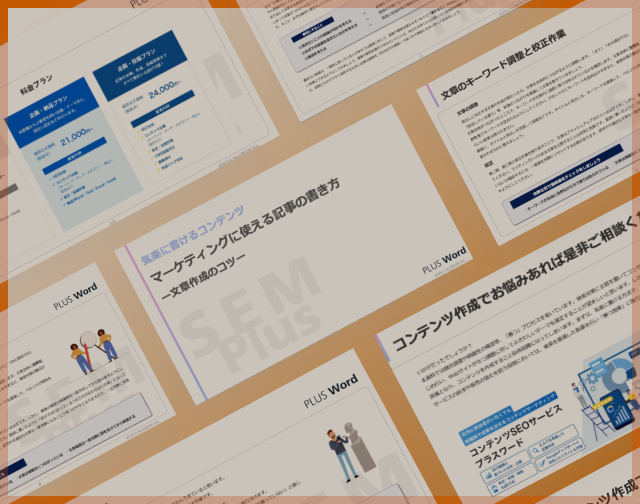リッチコンテンツとは?注目されている理由とメリットを事例付きで紹介

今回はリッチコンテンツについて解説します。「どのようなコンテンツがリッチコンテンツなのか」「なぜ注目されているのか」「SEO効果はあるのか」と疑問に感じたことがあるのではないでしょうか?本記事では、リッチコンテンツの概要から導入が進んでいる理由、効果、課題について初心者にも分かりやすく解説します。

リッチコンテンツとは?
リッチコンテンツとは、単なるテキストや画像ではなく動画や音声、CG、アニメーション、VR、ARなど、視覚的かつ動的な要素を含んだWEBコンテンツのことを指します。
以前は、手軽に埋め込み可能なFlash動画がリッチコンテンツの代表例とされていましたが、現在ではYouTubeやVimeoなどの動画プラットフォームを活用し、より多様な形式で動画を自社サイトに埋め込む手法が主流となっています。
また、インタラクティブなクイズや3Dモデルの表示、ライブストリーミングなど、ユーザー参加型のコンテンツも増加しており、これらはすべてリッチコンテンツの一部として位置付けられています。
WEBサイトに動画やアニメーション、漫画コンテンツ、インフォグラフィックス、パララックススクロールなどのリッチコンテンツを活用することで、ユーザーに対して視覚的に情報を効果的に伝えることができるため、ユーザーエクスペリエンスの向上やエンゲージメントの強化、ブランドイメージの向上が期待できます。
さらに、リッチコンテンツはユーザーの滞在時間を延ばし、直帰率を低下させるなど、間接的にSEO効果を向上させることができます。
リッチコンテンツが注目されている理由
近年ではWEBマーケティングや、WEB広告でリッチコンテンツを活用する企業が増加しています。テキストを中心としたWEBコンテンツは、競合他社から真似されやすく差別化が難しいほか、ユーザーへの印象が薄く成約や問い合わせが得られにくいという点が課題です。
上記のような課題を解決するために、リッチコンテンツが注目されるようになりました。
具体的に注目されている理由は、以下になります。
- 通信環境の向上
- スマートフォンの普及
- ソーシャルメディアの普及
- Google検索エンジンの進化
- コンテンツ制作ツールの普及
通信環境の向上
リッチコンテンツが注目された背景として、通信環境の向上が挙げられます。動画やアニメーションなどのリッチコンテンツは、テキストコンテンツと比較すると、データ通信量が圧倒的に大きく通信への負荷が掛かっていました。
その為、1990年代のダイヤルアップ接続(電話回線)を使ったインターネット期では、ほぼ使用されていませんでした。
また、当時は従量課金で接続されていることが多く、リッチコンテンツのようにデータ量が大きいコンテンツが敬遠されていたことも影響しています。

現在では、5Gといった通信システムの発展により、インターネット接続の高速化と大容量化が進んだことで、大きなデータ量を扱えるようになり、リッチコンテンツの利用が飛躍的に拡大しています。
スマートフォンの普及
2000年代後半から、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスの普及と性能向上に伴い、ユーザーは場所を問わずWEBコンテンツを閲覧できるようになりました。
総務省の令和5年通信利用動向調査によると、個人のスマートフォンの保有率は78.9%になり、全人口の8割がスマートフォンを所有しています。
その結果、現在ではパソコンでインターネットを利用する人よりモバイル端末から利用する人の方が多くなり、モバイルデバイスの小さい画面でも分かりやすく情報を伝えるための手段として、リッチコンテンツを使用する必要性が高まりました。
モバイルユーザーがより手軽に動画の視聴が可能になったことから、リッチコンテンツを提供する価値が高くなっていると言えるでしょう。
ソーシャルメディアの普及
ソーシャルメディア(YouTube・Instagram・TikTok)の台頭により、動画や画像などのリッチメディアが主要なコンテンツ形式となりました。
その結果、ユーザーの情報の取得方法が検索だけではなくソーシャルメディアを使った情報収集に変化しています。これに合わせてWEBサイトも動画などのリッチコンテンツをWEBサイトに埋め込むことで、ユーザーに情報を分かりやすく伝える企業が増えています。
また、ソーシャルメディアプラットフォームを活用することで動画の作成が容易になったことも、リッチコンテンツの普及に影響していると考えられます。
Google検索エンジンの進化
Googleの検索エンジンは、被リンクやコンテンツの品質だけではなく、ユーザーエクスペリエンスも重視するようになったため、リッチコンテンツを評価する傾向が強まりました。
2024年の5月にGoogleの内部から漏洩したドキュメントには、ユーザー行動が検索結果に影響することを示唆する内容も含まれていました。
動画やインタラクティブな要素を含むページは、ユーザーの満足度が高まるためページの離脱後に再検索をおこない、他サイトを閲覧する可能性が低くなり、ポゴスティッキングの発生率が減少します。
このようにユーザー行動が良いWEBページを評価するように、検索エンジンのアルゴリズムの進化が、リッチコンテンツの導入を促進する一因となっています。
コンテンツ制作ツールの普及
2023年にChat GPT等の生成AIが登場したことにより、誰でもAIを使って費用をかけずに簡単にコンテンツを作成できるようになり、他サイトとのコンテンツの差別化が難しくなっています。
また、多くのサイト運営者が顕在層だけではなく、潜在層にアプローチする目的でオウンドメディアの運用や、WEBサイト内でブログやコラムを運用しているため、類似するコンテンツが増えテキストコンテンツや画像だけでは差別化が難しい状況になっています。
そのため、サイト運営者はリッチコンテンツをページに追加することで、他サイトとの差別化を図るようになっています。動画やアニメーションによって商品やサービスを説明するリッチコンテンツは、生成AIでは簡単に作成することがまだ難しいため独自性を持たせやすくなります。
リッチコンテンツのメリット
リッチコンテンツを含んだ自社のWEBサイトが、ユーザーに提供するメリットは以下の4つです。
- テキストでは伝えにくいコンテンツの提供が可能
- 多彩な表現ができる
- サイトの滞在時間を延ばせる
- 企業イメージの向上に繋がる
テキストでは伝えにくいコンテンツの提供が可能
リッチコンテンツを活用することで、テキストでは伝えにくい商品やサービスについての詳細を分かりやすく伝えることができます。例えば、「母の日は何月何日なのか」「司法試験の平均合格率は何%なのか」といった情報であれば、文字や数字だけで十分に伝えることができます。
しかし、「手順が複雑なツールの使い方」「製品が完成するまでの工程」といった情報の場合、テキストデータや静止画像だけで表現しようとすると価値や魅力を伝えきれない場合があります。
テキストや静止画像だけで制作されたコンテンツと比較すると、動画コンテンツには5,000倍の情報を含めることができると言われており、たった1分の動画がWEBサイトの3,600ページに匹敵します。
使用方法の解説をテキストのみでするよりも、動画を使った解説をすることで、テキストデータでは表現しきれない動きや音をリアルに表現できるため、商品やサービスについてユーザーにとって直感的で分かりやすい説明ができます。
多彩な表現ができる
テキストや静止画像だけでは表現が限られますが、リッチコンテンツを活用することで、動画・音声・アニメーションなど、さまざまなメディア形式を組み合わせることができるため、多彩な表現ができます。
他サイトとは異なるクリエイティブを作成することで、ブランドの独自性を際立たせたり、商品やサービスの魅力をユーザーに強くアピールできます。
特に、競合と差別化しづらい商品やサービスを扱っている場合は、ユーザーの印象に残るようなマーケティング活動が必要になります。リッチコンテンツを活用して多彩な表現をすることで、競合他社と差別化ができます。
サイトの滞在時間を延ばせる
動画やアニメーションを活用したリッチコンテンツを使用することで、ユーザーの興味や関心を惹きつけることができるためWEBサイトの滞在時間を延ばすことができます。
多くのユーザーはWEBサイトのテキストを隅から隅まで読んでいるわけではなく、必要な情報が得られなかったり読んでもよく分からない場合は、ページやサイトからすぐに離脱してしまいます。
一方、多くのユーザーがYouTubeなどの動画を視聴していることから、動画に対する抵抗感を感じるケースは少ないことが想定できます。実際に、Wistiaがおこなった調査によれば、動画が含まれていないページよりも、含まれているページの方が滞在時間が長くなっています。

テキストだけで情報を伝えようとするより、リッチメディアを併用した方がより分かりやすい情報の取得に繋がるため、ユーザーの興味を引き滞在時間を伸ばすことができます。
企業イメージの向上に繋がる
リッチコンテンツを活用することで、企業や商品のイメージを短い時間で手軽に伝えることができるため、企業イメージの向上に繋がります。
例えば、採用サイトにオリジナルの動画コンテンツやアニメーションを使って、会社が掲げるミッションやバリューを表現することで、求職者に会社のイメージを分かりやすく伝えることができます。
近年は、YouTubeやTikTok経由での採用や商品の販売が増えているため、リッチコンテンツを使ったイメージ戦略が注目されています。今後は、企業のプロモーションでリッチコンテンツを使う企業は増えていくでしょう。
リッチコンテンツのデメリット
リッチコンテンツには前述したようなメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
- テキストコンテンツよりも作成コストがかかる
- ユーザーの通信環境によってはユーザビリティが低下する
それぞれ詳しく解説します。
テキストコンテンツよりも作成コストがかかる
リッチコンテンツは多彩な表現で高い訴求力を得られる一方、作成するのに専門的なスキルやリソースが必要となるため、相応のコストと時間がかかります。
ただ動画を撮影したり、音声を収録したりするだけではリッチコンテンツとは呼べません。例えば、動画を作成するのであれば「企画立案」「素材となる動画の撮影」「編集(テロップ・ナレーション追加)」など、テキストコンテンツの作成に比べて多くの工程が発生します。
また、動画の撮影や音声収録には、様々な機材と各工程を担当する専門スタッフを用意する必要があるため、完成までにかかる時間もトータルコストもかかります。
ユーザーの通信環境によってはユーザビリティが低下する
リッチコンテンツはデータ量が非常に大きいため、ユーザーの通信環境が悪い場合は、読み込みに時間がかかるためユーザビリティが低下する可能性があります。
表示速度が低下する状況であれば、ユーザーがストレスを感じ視聴途中で離脱してしまう場合も考えられます。
また、通信量の制限を設けたモバイル端末の契約をしているユーザーの場合は、通信量の上限を気にするため、せっかく発信した動画コンテンツを見てもらえない可能性もあります。
リッチコンテンツの種類
リッチコンテンツは、次のように大きく3つの種類があります。
- 動画コンテンツ
- 音声コンテンツ
- 漫画コンテンツ
それぞれ詳しく解説します。
動画コンテンツ
動画コンテンツとは、YouTubeやTikTokなどコンテンツを動画にしたものを指します。動画コンテンツはテキストや画像に比べてコンテンツの内容をユーザーに分かりやすく伝えることができるため、現在最も注目されているリッチコンテンツです。
動画コンテンツは、ページ内にリッチコンテンツとして埋め込むだけではなく、YouTubeにアップロードしたりSNSにアップロードするなど、テキストコンテンツよりも様々な活用方法があります。
また、動画コンテンツを入れることでページのSEO的な評価を高めることができるだけではなく、企業イメージをユーザーに伝えることができるため、ブランディングにも役立ちます。
これからリッチコンテンツの作成に取り組む方は、まず動画コンテンツから始めるのがオススメです。
| 活用事例 | ・レシピなどの作り方手順や解説 ・商品・サービス説明の解説 ・自社サイトが手掛けた事例の紹介 |
| メリット | ・直感的な理解に繋がる ・テキストより情報量が多い ・保存機能など2次利用がしやすい |
| デメリット | ・デジタル著作権の管理が必要 ・冒頭で視聴者の興味を引き付けなければ離脱されやすい |
音声コンテンツ
音声コンテンツとは、音声データのみで構成されたコンテンツです。音声コンテンツをリッチコンテンツとして活用するシーンでは、「Podcast」などの音声配信プラットフォームを利用しマーケティングに活用します。
音声コンテンツの最大の利点は、視覚に頼らずに情報やストーリーを伝えることができる点です。例えば、運動中や料理を作っている最中など、他の作業をおこなっているユーザーに対してもコンテンツを届けることができます。
音声コンテンツは、教育やビジネスの分野で専門的な知識をユーザーに共有したい場合や、インタビュー形式や対談形式の内容を届けたい場合に向いています。
| 活用事例 | ・自社に特化した専門性のある情報の発信 ・専門家同士の対談を配信 |
| メリット | ・画面を見なくても視聴できる ・トークによる商品紹介など親しみやすさがある ・動画コンテンツより安く制作できる |
| デメリット | ・スピーカー・ヘッドフォンがなければ視聴できない ・視覚的な情報を盛り込めない |
漫画コンテンツ
漫画コンテンツとは、漫画をブランディングやマーケティングに活用したコンテンツです。ストーリー性を持たせた情報発信が可能で、難しい内容をあえて漫画を使うことで、ユーザーに親しみやすく身近に感じてもらうことができます。
小学生のころ、進研ゼミの漫画を見てこの勉強方法なら「自分でもできそうだ」「自分もやってみたい」と思った方も多いのではないでしょうか?
漫画コンテンツは、動画コンテンツと同様に幅広い目的・用途で活用できますが、動画コンテンツに比べると普及は少ないです。
| 活用事例 | ・医療など難しく専門性の高い情報を漫画を取り入れ分かりやすく解説 ・塾や習い事などのPRが必要な場面でアニメーションを活用し親しみや興味を持たせる |
| メリット | ・閲覧してもらうハードルが低い ・幅広い世代になじみがある ・難しい問題も身近に感じやすい |
| デメリット | ・完成した後の修正が難しい ・動画より盛り込める情報量が少ない |
リッチコンテンツの活用事例
ユニクロ (UNIQLO):動画コンテンツ

ユニクロの商品ページを見ると、商品画像と一緒に動画コンテンツが埋め込まれています。商品説明に動画コンテンツを使うことで、商品の素材感やスタイリングイメージをユーザーに分かりやすく伝え、顧客の購買意欲を高めています。
ユニクロは、商品ページだけではなく公式YouTubeをおこなうなど、リッチコンテンツの活用に力を入れている代表的な企業です。
NHK for School:教育用動画コンテンツ

NHK for Schoolは、教育現場向けに多様な教育動画を提供してるWEBサイトです。
アニメーションや実写動画を組み合わせて、子供でも理解できるコンテンツが充実しており、教科ごとに生徒が授業や自学自習に活用できるようになっています。
視覚的に分かりやすい説明のため、難しい概念も理解しやすくなっています。
トヨタイムズ:音声コンテンツ

トヨタイムズは、音声データを活用したリッチコンテンツとしてポッドキャストを提供しています。
専門家やトヨタの社長や社員が出演し、車の設計や環境への配慮などトヨタの取組みについて詳しく語られています。
音声コンテンツを活用することで、車作りやトヨタが目指す姿についてリアルな情報を得ることができます。個人的には、「豊田章男が今伝えたいこと」が一般的なインタビューを記事にした内容よりも深い話が聞けるので好きです。
アンファー:漫画コンテンツ

薄毛や発毛に関するシャンプー、育毛剤「スカルプD」を販売しているアンファーは、「髪を鍛える」という新しい概念をユーザーに浸透させるために漫画コンテンツを活用しています。
また、格闘家の那須川天心選手とのコラボ漫画になっているため、(そういった意味でもリッチコンテンツですが)ユーザーにインパクトを与え記憶に残る漫画コンテンツとなっています。
リッチコンテンツに関するよくある質問
リッチコンテンツに関するよくある質問を解説します。
「リッチ化」とは何のことですか?
WEBコンテンツに、テキストだけでなく音声や動画、アニメーションなどの動的コンテンツを入れ込んで競合サイトと差別化させることをリッチ化と呼びます。
ユーザー満足度を高める効果にも繋がります。
リッチメディア広告はどのような広告?
動画やアニメーションなど、高度な機能を含んだWEB広告の1つでユーザーの印象が残りやすいメリットがあります。動画やアニメーションが自動で再生されるタイプと、バナー広告にメッセージが表示され、ユーザーが操作をすることで広告内容が切り替わるタイプがあります。
まとめ
今回は、リッチコンテンツとは何か、なぜ注目されているのか、どのような効果・リスクがあるのかについて解説しました。テキストコンテンツでは、十分に説明ができない情報を提供したい場合や、競合他社のサイトとの差別化を目指したりする場合には、リッチコンテンツの活用がおすすめです。
しかし、ただ制作しただけでは十分な効果が得られないことがあるため、どのような種類のリッチコンテンツが適しているのか、本当に制作する必要があるのかを検討した上で取り組みましょう。
なお、弊社では記事コンテンツ作成サービスをおこなっています。リッチコンテンツを使いたいけど予算やリソースがないため、記事コンテンツで競合サイトと差別化したいとお考えの方は気軽にお問合せくださいませ。

- 記事構成の作り方
- キーワード入れ方
- SEOライティング
- 記事リライト方法
- SEO記事作成代行
ぜひ、読んで欲しい記事
-
 コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/12
コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/12
コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/12
コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/09
コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/09
コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/092025/09/09
-
 コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/30
コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/302025/10/30