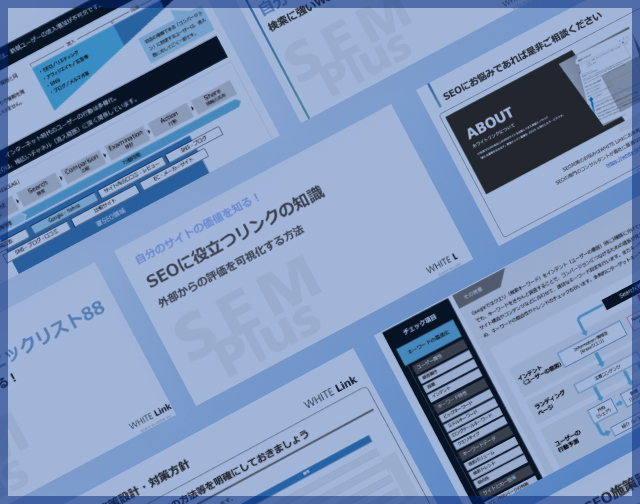パンくずリストとは?由来とSEO効果・設定のポイントを解説

パンくずリストとは、WEBサイトのナビゲーションの1つで、ユーザーがWEBサイト内でどの位置にいるかを視覚的に表示させる仕組みです。パンくずリストを活用することで、WEBサイトの利便性を向上させたり間接的にSEO効果を高めることが出来ます。本記事ではパンくずリストのメリットや種類、設定のポイントを詳しく解説します。
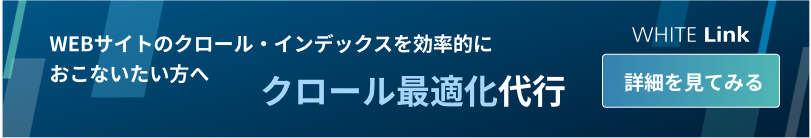
パンくずリストとは
「パンくずリスト」とは、WEBサイトの中で自分がどのページにいるのかを示す機能です。
英語で、「Breadcrumb Navigation」または「Breadcrumbs」と言います。
パンくずリストは、階層順にWEBページへのテキストリンクが表示されるため、ユーザーはリンクをクリックして、1つ上のカテゴリページやトップぺージに移動することができます。
また、ユーザーが過去に訪れたページに簡単に戻ることができるため、パンくずリストを設置することでユーザーエクスペリエンスを向上させる効果があります。
【パンくずリストの例】
- メディアサイトの例:TOP > SEO > パンくずリスト
- ポータルサイトの例:TOP > 土地 > 東京 > 渋谷区の土地
- ECサイトの例:ホーム > メンズ > アウター > コート一覧
そのため、一般的にはパンくずリストはユーザビリティを考え、視覚的に目立つページの上部(ヘッダー)にテキストリンクで設置します。

パンくずリストを設置すると、検索エンジンのクローラーがWEBサイトの構造を理解しやすくなるため、新しいページの発見がしやすくなります。
また、パンくずリストによって内部リンクが重要なページに向けて集中するため、特定のカテゴリページのPageRankが高まり検索順位が向上する可能性があります。
このように、パンくずリストを設置することで間接的なSEO効果も期待できます。
パンくずリストのメリット
パンくずリストをWEBサイトに導入するメリットは、以下の3点です。
- ユーザビリティの向上
- クローラビリティの向上
- SEO効果の向上
それぞれ詳しく解説します。
ユーザビリティの向上
パンくずリストを設置する1つ目のメリットは、WEBサイトのユーザビリティを大きく向上させる事です。
例えば、ECサイトやポータルサイトなどの大規模サイトでは、カテゴリページから詳細ページへサイト内を回遊するため、自分がWEBサイト内のどこにいるのかが分からなくなる事があります。
パンくずリストがあれば、ユーザーは自分がサイト内のどこにいるのか理解することができ、1つ前のカテゴリやTOPページへ戻ることができます。
【具体例】
「ホーム > メンズ > アウター > コート」というパンくずリストがある場合、ユーザーがコート以外のアウターを探したい時は、「アウター」をクリックすればアウターカテゴリから商品を探し直すことができます。
このように、パンくずリストを設置する事でユーザーはWEBサイト内で迷うことがなくなります。つまり、ユーザビリティが向上しページの離脱率や直帰率が低下します。
クローラビリティの向上
パンくずリストを設置する2つ目のメリットは、クローラビリティが向上することです。クローラビリティとは「Googleのクローラーがページを見つけやすい状態」のことを意味する用語です。
Googleのクローラーは、WEBページ内のリンクを辿ってサイト内のページを発見します。パンくずリストを設置して、内部リンクをサイト全体に張り巡らせれば、クローラーが新しいページを発見する可能性が高まり、クロール・インデックスされるページが増える可能性があります。
つまりGoogleのクローラーがサイト内をスムーズに巡回出来るようになり、クローラビリティが向上するというわけです。
SEO効果の向上
パンくずリストを設置する3つ目のメリットは、SEO効果が向上することです。
Googleの検索エンジンは内部リンクが多く集まっているページを、サイト内で重要なページと判断しアルゴリズムによって評価します。
【具体例】
ホーム > 矯正治療> マススピース矯正 >というパンくずリストがある場合、下の階層から内部リンクの集まる「矯正治療」のページやトップページがSEOで評価されます。
このように、パンくずリストは検索エンジンがサイト構造を理解するのに役立ちます。つまり、パンくずリストを設置することで内部リンクが集まるページのSEO評価が高くなると言うことです。

もちろん、検索順位を上げるには内部リンクだけを集めるだけではなく、高品質なコンテンツや被リンクも必要になりますが、関連するページからの内部リンクの数は評価に影響します。
パンくずリストの種類
パンくずリストには主に、
- 「位置型」
- 「属性型」
- 「パス型」
という3つの種類があります。
それぞれ異なる目的と機能を持ち、WEBサイトの構造に応じて選択します。
この項目では、パンくずリストの種類ごとに特徴と利用例を解説します。
位置型パンくずリスト
位置型パンくずリストは、WEBサイト内でユーザーが現在どの位置にいるかを示すために使用される一般的なタイプのパンくずリストです。
位置型パンくずリストはWEBサイトの階層構造を示し、その構造はユーザーのナビゲーションパスに依存せず、誰が見ても同じ構造を表示します。
【位置型パンくずリストの例】
「ホーム > メンズ服 > ジャケット > レザージャケット」
上記の例が位置型パンくずリストの場合、ユーザーがどのような経路を辿ったかに関わらず、レザージャケットの商品ページにアクセスした全てのユーザーに対して同じ形で表示されます。
アンカーテキストが静的に表示されるため、検索エンジンがサイト構造を理解しやすくSEOに最も適しているパンくずリストです。
また、位置型パンくずリストのもう一つの利点として、ユーザーがサイトの階層構造を直感的に理解できることと、ユーザーがサイト内で簡単に他の関連カテゴリーやページに遷移できるようになることです。
属性型パンくずリスト
属性型パンくずリストは、ユーザーがWEBサイト内で選択したカテゴリやフィルタに基づいて表示されるパンくずリストです。ユーザーが選択したカテゴリにあわせて動的にパンくずリストを表示します。
たとえば、求人情報サイトで同じ「Java開発者」の求人ページに異なるカテゴリを選択してアクセスしているケースを紹介します。
【例】
- ユーザーAが選択したカテゴリ:「ホーム」→ 「 ITエンジニア」→ 「ソフトウェア開発」 →「 Java開発者」
- ユーザーAのパンくずリスト:ホーム > IT・エンジニア > ソフトウェア開発 > Java開発者
- ユーザーBが選択したカテゴリ:「ホーム」→ 「東京 」→ 「 ITエンジニア」 → 「Java開発者」
- ユーザーBのパンくずリスト:ホーム > 東京 > IT・エンジニア > Java開発者
最終的にどちらも「Java開発者」の詳細ページに辿りついていますが、選択したカテゴリに合わせてパンくずリストが変化しています。
このように属性型パンくずリストの特徴は、ユーザーがサイト内で行った操作方法によってパンくずリストの表示内容が変化します。
パス型パンくずリスト
パス型パンくずリストは、ユーザーがWEBサイト内で実際に訪れたページの閲覧履歴を表示するタイプのパンくずリストです。
【例】
- ユーザー行動履歴:「ホームページ」→「ニュース記事」→「製品レビュー」→「製品購入ページ」
- 表示されるパンくずリスト:ホーム > ニュース記事 > 製品レビュー > 製品購入ページ
ユーザーごとに異なるパンくずリストが表示されるため、一見便利に見えますが、サイトの階層構造を直接反映するわけではないので、ブラウザの「戻る」ボタンと変わらないため、利用シーンは殆どありません。
パンくずリストを効果的に設定するポイント
パンくずリストをより効果的に設置するポイントを紹介します。
以下の6つのポイントを意識して設定することで、ユーザビリティとSEO効果を高めることができます。
- 分かりやすいサイト構造にしておく
- パンくずリストにキーワードを含める
- 階層の間には区切り文字を使用する
- パンくずリストに現在のページへのリンクを含めない
- パンくずリストは全てのページに設置する
- パンくずリストを構造化データでマークアップする
それぞれ詳しく解説します。
分かりやすいサイト構造にしておく
ユーザーにとって分かりやすいパンくずリストを設置するには、サイトの構造を明確にしておく必要があります。
サイト構造が複雑な場合、以下の例のようにパンくずリストを見ても自分がどの階層にいるのかが分かりづらくなります。
【サイト構造が明確ではない場合のパンくずリスト】
■ 例①:深すぎる階層構造の例
「ホーム > カテゴリー > サブカテゴリー1 > サブカテゴリー2 > サブカテゴリー3 > 製品ページ」
■ 例②:整合性の無い構造の例
パンくずリスト1:「ホーム > 家電製品 > 美容家電 > コーヒーメーカー」
■ 例③:断絶されたナビゲーションパスの例
「ホーム > 特別キャンペーンページ」
このように、サイト構造が論理的に整理されていない場合は、ユーザーにとって混乱を招くパンくずリストになります。パンくずリストを設置する場合は、予めサイトの構造を論理的に整理した上で作成しましょう。
パンくずリストにキーワードを含める
ユーザーにとって分かりやすいパンくずリストにするために、ぺージの内容を表すキーワードを含めましょう。パンくずリストにキーワードを含める事で、ユーザーは上下の階層がどのようなページなのかを、一目で理解することができます。
【キーワードを含めたパンくずの例】
【○】例1:SEOトップぺージ>SEOコンサルティング> 内部対策 >クローラビリティの改善
【×】例2:ホーム>サービス>サービス2>クローラビリティの改善
例1は前後の階層の内容がすぐに分かりますが、例2はパンくずを見ただけではページの内容が理解できません。また、パンくずリストにキーワードを入れることで、検索エンジンもページの内容やページ間の関係を正しく理解できるようになります。
ただし、キーワードを含む事を意識しすぎるあまり、不自然にキーワードを入れるのは逆効果になるためやめましょう。
階層の間には区切り文字を使用する
分かりやすいパンくずリストを作るためには、階層の間に区切り文字を使用しましょう。パンくずの間に区切り文字が無い場合は、文字が繋がって見えてしまいユーザビリティを低下させてしまう可能性があるため、「不等号」「スラッシュ」を使って見やすくします。
【区切り文字パターン① >(不等号)】

【区切り文字パターン② /(スラッシュ)】

区切り文字は「>」や「│」「/」などの文字を使用して、階層がユーザーに分かりやすく伝わるようにしましょう。
パンくずリストに現在のページへのリンクを含めない
分かりやすいパンくずリストにするためには、現在のページへのリンクを含めてはいけません。現在いるページへのリンクを含めた場合、ユーザーはパンくずを見てもどの階層にいるのか分からなくなってしまうためです。
また、リンクをクリックしても画面が変わらないため、サイトがエラーを起こしていると勘違いする可能性があります。

ユーザーが自分がどこにいるのかを把握できるように、現在いるページはリンクにせずに太文字にするなど、その他の階層と違いが分かるようにしておきましょう。
パンくずリストは全てのページに設置する
パンくずリストは、WEBサイトにある全ページに設定しましょう。
パンくずリストを設置する一番の目的はユーザビリティの向上です。ユーザーがどのページにいても、WEBサイト内で自身がいる場所を把握できるようにパンくずリストを全ぺージに設置します。
ただし、もともとWEBサイトの階層構造をユーザーに知らせる必要がないトップページ(ホーム)や、ランディングページのようなコンバージョン率の向上が優先されるページに対しては、パンくずリストを設定する必要はありません。
パンくずリストを構造化データでマークアップする
Googleは、パンくずリストを構造化データでマークアップすることを推奨しています。
理由は、以下の2点です。
- 検索エンジンがサイト構造をより正確に理解することができる
- 検索結果にリッチリザルトとして表示される
このように、パンくずリストを構造化データでマークアップすることで、インデックスの促進に繋がり間接的にSEO効果の向上と、検索結果画面のCTRを高めることができます。
パンくずリストの構造化データには、主にJSON-LD、Microdata、RDFaの三つの形式がありますが、GoogleはJSON-LDを推奨しています。
構造化マークアップのやり方は、Googleの公式ヘルプで詳しく解説してあるのでこちらを参考に進めてみてください。
【参考ページ】:Google検索セントラル:パンくずリスト(BreadcrumbList)の構造化データ
パンくずリストを構造化データでマークアップしたら、正しく設定できているかをGoogleの「リッチリザルト テスト」もしくは「スキーマ マークアップ検証ツール」を用いてチェックしましょう。
WordPressにパンくずリストを設定する方法
WordPressを使ってWEBサイトを運営している場合は、「Breadcrumb NavXT」というプラグインを使うと簡単にパンくずリストを設定することができます。

Breadcrumb NavXTの設置手順は、以下になります。
【パンくずリスト設置手順】
- WordPressにログインする
- 管理画面の【プラグイン】をクリック
- 【新規追加】をクリック
- 検索窓に「Breadcrumb NavXT」と入力して検索
- 【今すぐインストール】をクリック
- 【有効化】をクリック
- 【外観】>【テーマの編集】>画面右下の【ヘッダー(header.php)】をクリック

- パンくずリストを表示させたい位置に以下のコードを記述する
<div class=”breadcrumbs” typeof=”BreadcrumbList”
vocab=”https://schema.org/”>
<?php if(function_exists(‘bcn_display’))
{
bcn_display();
}?>
</div> - 「ファイルを更新」をクリック
- パンくずリストの設定完了
Breadcrumb NavXTの設定はデフォルトのままでも使用可能ですが、工夫次第でさまざまな設定を行うことができます。
例えば、管理画面の「Breadcrumb NavXT」をクリックすると、設定を変更することができます。初期設定では、パンくずリストの先頭がWEBサイト名になっているため、「ホーム」や「トップページ」などの表記に変更してみましょう。
やり方は、ホームページテンプレートという項目内の「%htitle%」部分を他の表記に変更します。

パンくずリストに関するよくある質問
パンくずリストの由来はなんですか?
パンくずリストの名前の由来は、ドイツの有名な童話「ヘンゼルとグレーテル」にあります。
この物語では、ヘンゼルとグレーテルが森の中で迷子にならないように、家から森に向かう途中でパンのくずを道に撒きます。この話を元に、WEBサイト上でユーザーが現在どの位置にいて、どのような経路でそのページにたどり着いたかを示す仕組みが「パンくずリスト」と名付けられました。
WEBサイトにパンくずリストは必須ですか?
必須ではありませんが、大規模なECサイトやポータルサイトなど情報が多く複雑なサイトでは、ユーザーの利便性の向上や、サイトの構造を検索エンジンに理解させることが出来るため有効です。
パンくずリストには、どのようなSEO効果がありますか?
パンくずリストを構造化データでマークアップすると、検索エンジンがサイトの構造を理解しやすくなるため、インデックスが促進される効果があります。
パンくずリストのデザインにおいて重要なポイントは何ですか?
パンくずリストはなるべく上部に配置し、目に留まるようにデザインすることが重要です。また、リンクは明確にし、ユーザーが前に戻りたい際に直感的に操作できるようにします。
モバイルサイトにもパンくずリストを表示するべきですか?
はい、モバイルサイトでもパンくずリストは有用です。デスクトップに比べて画面のサイズが小さいため、リンクの誤タップなどが発生しないように工夫して設置しましょう。
まとめ
今回は、WEBサイトのユーザビリティやSEO効果を高める上で重要な「パンくずリスト」について解説しました。「パンくずリスト」のメリットや種類を正しく理解した上で活用することで、離脱の防止やランキングの向上に繋がります。
パンくずリストをまだ設置できていないサイト運営者の方は、本記事を参考に是非パンくずリストを設置してみてください。
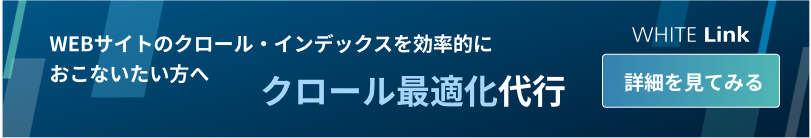
ぜひ、読んで欲しい記事
 SEO対策llms.txtとは?書き方やLLMOでの効果について解説2025/06/24
SEO対策llms.txtとは?書き方やLLMOでの効果について解説2025/06/242025/06/24
 SEO対策サイトリニューアルがSEOに与える影響│順位下落防止のポイントを解説2025/06/24
SEO対策サイトリニューアルがSEOに与える影響│順位下落防止のポイントを解説2025/06/242025/06/24
 SEO対策LLMO対策代行会社おすすめ9選│失敗しない外注業者の選び方を解説2025/06/20
SEO対策LLMO対策代行会社おすすめ9選│失敗しない外注業者の選び方を解説2025/06/202025/06/20
 SEO対策403(Forbidden)エラーの意味とは?発生する原因と解決方法を解説2025/06/13
SEO対策403(Forbidden)エラーの意味とは?発生する原因と解決方法を解説2025/06/132025/06/13
 SEO対策LLMOへの関心・取り組み状況に関する市場調査レポート2025/06/10
SEO対策LLMOへの関心・取り組み状況に関する市場調査レポート2025/06/102025/06/10
 SEO対策AI Overviewに関する利用実態レポート2025/06/10
SEO対策AI Overviewに関する利用実態レポート2025/06/102025/06/10