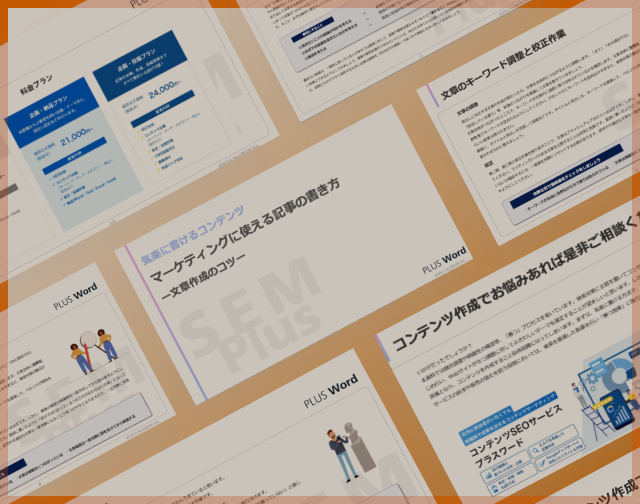BtoB企業のWEB集客における記事制作(コンテンツSEO)のポイント

「BtoB事業のWEB集客ではどのような記事を作成すれば良いのか」「どのように記事制作を進めれば良いのか」など、お悩みではないでしょうか?この記事では、BtoB事業のWEB集客において記事作成を行うメリットからキーワード選定の方法、記事作成の流れなど、初めてWEB集客に取り組むBtoB企業にも分かりやすく解説します。

BtoB事業が自社商材に関する記事制作(コンテンツSEO)をするべき理由
BtoB事業が、自社商材に関する記事制作をするべき理由は以下の6つです。
- オンラインで情報収集を行う顧客(潜在層)にアプローチできる
- サービス検討段階の見込み顧客へのアプローチができる
- 企業のブランディングになる
- 広告に頼らずにリード獲得が出来る
- 社内にサービス・製品についてのノウハウが貯まる
- 業界によっては競合サイトが少ないため上位表示の難易度が低い
それぞれの理由について詳しく解説します。
オンラインで情報収集を行う顧客(潜在層)にアプローチできる
BtoB事業が自社商材に関する記事作成をするべき理由の1つ目は、オンラインで情報収集を行う顧客(潜在層)にアプローチできるからです。インターネットが普及するまでは、サービスを提供する企業から見込み顧客へ向けて直接アプローチする手法が一般的でした。
営業担当者が企業へ電話でアポイントを取ったり直接出向いたりすることで商材を紹介し、興味を持つ企業から受注していたわけです。
インターネットが普及した現在では見込み顧客の購買行動が変化し、上記のような受け身の方法で情報を得るのではなく、自社で情報を収集し、どのサービスを利用するか比較・検討するようになりました。
上記の傾向は新型コロナウイルスの流行に伴い営業担当者の活動が制限された結果、更に加速しています。
見込み顧客の情報収集はオンライン中心で行われるようになったため、BtoB事業を営む企業が集客する場合には、検索エンジン経由でのアプローチがより重要になったわけです。
オンラインで情報収集を行う見込み顧客にアプローチするためには、自社でWEBサイトを運用し、検索結果に自社商材に関する記事を表示させる必要があります。
見込み顧客が知りたい情報は何か、どのような情報を届けるべきかを検討し、見込み顧客が検索時に使用するキーワードと検索意図を想定して記事を作成することで、見込み顧客に対して効率良くアプローチできます。
サービス検討段階の見込み顧客へのアプローチができる
BtoB事業が自社商材に関する記事作成をするべき理由の2つ目は、サービス検討段階の顕在顧客へ、アプローチできるからです。TVCM・新聞に代表されるオフライン広告やディスプレイ広告、SNS広告などで集客する場合、見込み顧客だけでなく、見込み顧客ではないユーザーも集客してしまいます。
一方、自社商材に関する記事を作成すれば、サービスを比較・検討している段階のユーザーだけを狙って集客することが可能です。
比較・検討段階の見込み顧客は自社にマッチするサービスを検索で探すケースが多いため、自社の記事を検索結果の上位に表示させることが出来れば、自社が提供する商品・サービスを比較・検討の候補として認識させることができ、問い合わせに繋がる機会を増やすことが出来ます。
企業のブランディングになる
BtoB事業が自社商材に関する記事作成をするべき理由の3つ目は、企業のブランディングになるからです。
自社が提供する商品やサービスが見込み顧客に認知されていても、自社がどのようなコンセプトで商品やサービスを提供しているのか、他社と何が違うのか、どのような経営方針の企業なのかまでは理解されているとは限りません。
広告などで認知度を高めたとしても、自社よりも安く商品・サービスを提供する競合他社や、自社よりも認知度が高い競合他社との競争に負けてしまうこともあるでしょう。
一方、自社商材に関する記事を作成すれば見込み顧客を自サイトへ誘導できるため、自社の強みや経営理念を具体的にアピールできます。
広告に頼らずにリード獲得が出来る
BtoB事業が自社商材に関する記事作成をするべき理由の4つ目は、広告に頼らずにリード獲得が出来るからです。
広告を出稿するためには広告を掲載する媒体への広告出稿費用がかかりますが、自社WEBサイトの記事がGoogleやYahoo!などの検索エンジンに表示されても費用がかかるわけではありません。
WEBサイトの運営や記事制作、SEO対策に一定の費用はかかるものの、広告に比べると低コストで見込み顧客を集客できます。自サイトへ集客した見込み顧客を問い合わせページやホワイトペーパーダウンロードページなどリードを獲得できるページへ誘導することで、広告に頼らないリード獲得が可能です。
社内にサービス・製品についてのノウハウが貯まる
BtoB事業が自社商材に関する記事作成をするべき理由の5つ目は、企業全体でサービス・製品についての理解度が高くなることです。入社したばかりの新入社員だけでなく、自社に所属する社員のすべてが自社が提供する商品やサービスを深く理解しているとは限りません。
自社が提供する商品・サービスに関する記事を新入社員に作成させることで、自社商品・サービスに対しての理解度を高めるとともに、社員としての教育や文章を書く訓練としても活用できます。
業界によっては競合サイトが少ないため上位表示の難易度が低い
BtoB事業が自社商材に関する記事作成をするべき理由の6つ目は、業界によっては競合サイトが少ないため上位表示の難易度が低いからです。
検索上位表示の難易度は、上位表示を狙うキーワードのジャンルにも大きく左右されます。保険業界や人材業界、美容業界などは競合する企業が非常に多いため、検索上位表示においても競合サイトが多いです。
たとえば、競合サイトが100サイト存在している場合、自サイトを検索結果の1ページ以内に表示させるためには少なくとも90サイトを追い越さなければいけません。一方、ニッチな商材を扱う企業やニッチなジャンルの企業の場合は競合企業が少ないため、相対的に見れば検索上位表示の難易度は低いです。
BtoBの記事制作ポイント
BtoB事業の記事制作ポイントは以下の通りです。
- 自社商材の印象にあわせたトーンで執筆する
- どのような分野でも読みやすい文章で作成する
- 様々な担当部門、役職の人が関わることを踏まえて作成する
- データやアンケートなどは一次情報を紹介する
- 情報を参照する場合は公的機関のサイトや信頼性のあるサイトを使用する
- データや集計結果は表形式で解説する
- コンバージョンに近いテーマで記事を作成する
- 記事の監修は必ず社内で専門知識のある人物が行う
- 記事を利用する目的によって内容を変える
- 事前のリサーチを徹底する
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
【ポイント1】自社商材の印象にあわせたトーンで執筆する
BtoB事業の記事作成ポイントの1つ目は、自社商材の印象にあわせたトーンで執筆することです。
専門性の高い業務に関わるサービスであればテクニカルな情報を盛り込む、カジュアルな商品の場合は親近感のある言葉を選んで執筆するといったように、提供する商品やサービスに対する印象に記事のトーンを合わせることで、ブランドの一貫性を保った印象付けができます。
【ポイント2】どのような分野でも読みやすい文章で作成する
BtoB事業の記事作成ポイントの2つ目は、どのような分野でも読みやすい文章で作成することです。
前述したようにサービスの専門性が高い場合にはテクニカルな情報を盛り込む場合がありますが、担当者にしか理解できない文章になっていると決裁権のある読者には理解できない恐れがあります。
たとえば、勤怠管理ツールを実際に使用する担当者は勤怠管理の専門家ですが、ツールを導入することを検討する立場の人が、勤怠管理に精通しているとは限りません。
また、担当者がツールを利用する際の利便性を具体的に解説しても、日常的に勤怠管理作業を行っていない責任者には上手く伝わらないこともあるでしょう。難易度が高い商品やサービスに関する記事であっても、初心者が読んで理解できるよう心がけて記事を作成することが重要です。
【ポイント3】様々な担当部門、役職の人が関わることを踏まえて作成する
BtoB事業の記事作成ポイントの3つ目は、様々な担当部門、役職の人が関わることを踏まえて作成することです。BtoB企業が提供する商品やサービスは、担当者が個人として購入したり導入したりするわけではありません。
商品の購入やサービスの導入を検討するのは、社長や部長、課長などの役職者、部門の責任者です。商品やサービスの導入には社内の稟議を通す必要があるため、さまざまな立場の人が記事を読むことを意識して記事を作成する必要があります。
【ポイント4】データやアンケートなどは一次情報を紹介する
BtoB事業の記事作成ポイントの4つ目は、データやアンケートなどは一次情報を紹介することです。BtoB記事に掲載するデータやアンケートは、基本的に自社で作成したものを掲載する必要があります。
なぜなら、商品やサービスの利用を検討している見込み顧客は、他の企業の情報ではなく商品やサービスを提供する企業が提供する情報に興味があるからです。他の企業が作成したデータやアンケートを記事に掲載しても、見込み顧客を納得させることは難しいでしょう。
データやアンケートの作成自体は専門の会社へ依頼しても問題ありませんが、自社が主導して作成することが重要です。
一方、記事の内容を補足する目的で他社が作成したデータやアンケートを記事で紹介する場合には、公的機関のサイトや信頼性のあるサイトが作成した一次情報を紹介する必要があります。
二次情報を紹介してしまうと、どこの会社がデータやアンケートを作成したのか分からず信頼されなかったり、一次情報を探すために記事から離脱されたりするかもしれません。
他社が作成したデータやアンケートを紹介する場合には、どこの会社が作成したのかを確認し、一次情報を紹介するようにしましょう。
【ポイント5】情報を参照する場合は公的機関のサイトや信頼性のあるサイトを使用する
BtoB事業の記事作成ポイントの5つ目は、情報を参照する場合は公的機関のサイトや信頼性のあるサイトを使用することです。掲載されている情報の根拠が明確でないサイトから情報を参照した場合、記事を読む読者から信用されなかったり、正しい情報なのか疑問に思われてしまったりする恐れがあります。
外部サイトから情報を参照する場合には、財務省や法務省といった公的機関が運営するサイトなど、信頼できる情報が掲載されているサイトを利用することが重要です。
【ポイント6】データや集計結果は表形式で解説をする
BtoB事業の記事作成ポイントの6つ目は、データや集計結果は表形式で解説することです。データや集計結果などの数値を中心とした情報は、文章にすると伝わりにくくなる場合がほとんどです。
<table>や<tr>、<th>、<td>などのテーブルタグで表を作成し、情報を表形式で表示するようにしましょう。一方、データや集計結果などを図や画像にして挿入した場合、見た目は同じなので読者の利便性は変わりませんが、検索エンジンは図や画像の内容を正確に理解できません。
明確な目的がない限り、テーブルタグを使用して表を作成することをおすすめします。
【ポイント7】コンバージョンに近いテーマで記事を作成する
BtoB事業の記事作成ポイントの7つ目は、コンバージョンが期待できるテーマで記事を作成することです。BtoBメディアの最終な目的は問い合わせなどのコンバージョンを獲得することなので、コンバージョンが期待できないテーマで記事を作成しても効果的ではありません。
検索ボリュームが多いキーワードで検索上位表示できればPV数は増加しますが、コンバージョンに繋がらないユーザーばかりを集客することになるからです。
BtoCメディアではPV数をKPIに設定し検索ボリュームが多いキーワードで記事を作成するケースが多いですが、BtoBメディアではPV数は増えますがコンバージョン数も増えるとは限りません。
インスタグラム運用会社の場合だと、「インスタグラム 広告 出し方」ではコンバージョンに繋がりますが、「インスタグラム見るだけ」ではコンバージョンには繋がりません。
一方、「インスタグラム 登録方法」の場合はインスタグラムアカウントを作成していない企業が参考にするケースも想定されるため、意味がないわけではありません。
【ポイント8】記事の監修は必ず社内で専門知識のある人物が行う
BtoB事業の記事作成ポイントの8つ目は、記事の監修は必ず社内で専門知識のある人物が行うことです。
一般的に記事の監修は専門家が行うため外部の専門家へ監修を依頼するケースが多いですが、BtoBメディアの場合は自社が提供する商品・サービスへの理解が求められるため、可能な限り自社で記事の監修を行うことをおすすめします。
たとえば、SNS広告運用会社がインスタグラム広告に関する記事を外注する場合、記事を監修するのは外部の専門家ではなく、インスタグラム広告に関して専門知識のある自社の担当者です。
インスタグラム広告に関する専門家は社外にもいるかもしれませんが、専門家であるSNS広告運用会社があえて外部へ監修を依頼する意味はありません。一方、記事の内容に関する監修ではなく校正・校閲が必要な場合には、校正・校閲の専門家へ依頼することをおすすめします。
なぜなら、BtoB企業は校正・校閲の専門家ではないからです。校正・校閲の専門家ではない人が文章をチェックしても、どこに問題があるのか、どのような表現が適切なのか正確に判断できません。
記事の監修と校正・校閲はそれぞれ別の人が行うようにしましょう。
【ポイント9】記事を利用する目的によって内容を変える
BtoB事業の記事作成ポイントの9つ目は、記事を利用する目的によって内容を変えることです。BtoB企業が作成するコンテンツには、オウンドメディアやメルマガ、ホワイトペーパーなど活用シーンが異なるケースが多くあります。
検索流入からの流入を狙う場合には検索ユーザーを意識して記事を作成しますが、メルマガやホワイトペーパーは特定のキーワードで検索した検索ユーザーだけが読むわけではないため、検索キーワードを意識した内容にする必要はありません。
コンテンツを作成する目的に合わせて、内容や文字数などを変更しましょう。
【ポイント10】事前のリサーチを徹底する
BtoB事業の記事作成ポイントの10つ目は、事前のリサーチを徹底することです。
BtoB企業のターゲットは特定の分野における専門家であるケースがほとんどなので、公的機関が発信している情報や業界のトレンド、専門書籍、海外の情報などをリサーチした上で役に立つ情報を提供しなければ満足させることはできません。
少し考えれば誰にでも分かることやネット検索で容易に入手できる情報を盛り込むだけでは、見込み顧客を納得させることは難しいでしょう。また、外部からの情報を提供するだけではなく、自社で調査・分析した情報を記事に盛り込むことも効果的です。
BtoB記事の推奨文字数と推奨記事作成数
BtoB事業記事の推奨文字数は3,000文字~5,000文字、推奨記事作成数は50ページ~100ページです。
検索意図に対する回答が一つだけの場合や限定される場合には少ない文字数の記事になりやすく、検索意図に幅がある場合や検索意図に対する回答が複数ある場合には、文字数が多くなる傾向にあります。
文字数を多くすれば検索順位が上がりやすくなるわけではなく、文字数が多すぎる記事は離脱されやすいため、読者の目的を意識して記事の文字数を設定することが重要です。
ラッコツールズ工房の「見出し(hタグ)抽出」やラッコキーワードの「見出し抽出」などのツールで検索上位記事の文字数を確認し、不足した情報はないかを確認したうえで文字数を決めるようにしましょう。
作成する記事数は基本的に検索意図の数と同じですが、選定したキーワードすべてに対して記事を作成するわけではありません。異なるキーワードでも検索意図が同じ場合や同じキーワードでも検索意図が異なる場合があるため、検索意図の数だけ記事を作成するようにしましょう。
BtoBの記事制作におけるキーワード選定の方法
BtoB事業の記事作成におけるキーワード選定の方法は、以下の通りです。
- ペルソナを設定する
- カスタマージャーニーマップを作成する
- カスタマージャーニーマップのフェーズに合わせてキーワードを選定する
それぞれの手順について詳しく解説します。
ペルソナを設定する
BtoB事業の記事作成におけるキーワード選定では、始めにターゲットユーザーを設定します。前述したように特定のキーワードに関連したキーワードの中には、自社のターゲットユーザーが使用しないキーワードも存在するからです。
ターゲットユーザーを設定することで、どのキーワードが問い合わせに繋がるのか、上位表示を狙う必要のないキーワードはどれなのかを分類しやすくなります。ターゲットユーザーを設定したら、記事を読むユーザーのペルソナを設定します。
ペルソナとは、ターゲットユーザーを明確にイメージできるようにした、具体的な人物像です。
【ターゲットユーザーとペルソナの例】
| ターゲットユーザー | 健康食品を販売する会社 |
| ペルソナ | 健康食品を販売する会社に勤務 WEBマーケティング担当者 千葉県習志野市に在住 30代男性 既婚 子どもは5歳の男の子と2歳の女の子 |
上記のように具体的な人物像をペルソナとして設定することで、どのような課題を抱えているのか、どのようなキーワードで検索するかを想定しやすくなります。
カスタマージャーニーマップを作成する
次に、カスタマージャーニーマップを作成します。
カスタマージャーニーマップとは、見込み顧客の思考の変化を図や表で表現したものです。
見込み顧客が商品・サービスの購入に至るまでの思考の流れは以下の通りです。
| フェーズ | 見込み顧客の思考 |
|---|---|
| 課題が潜在している状態 | 何が課題なのか認識できていない |
| 課題の顕在化 | 課題があることを認識 |
| 情報収集 | 課題を解決するためにはどうすればよいのか |
| 比較・検討 | 課題を解決する手段として何が最適なのか |
| 購入 | 自社にとって最適なサービスを決定 |
カスタマージャーニーマップを作成することで、見込み顧客が現在抱えている課題は何か、どのような行動を取るかを可視化でき、社内で方向性を共有できるようになります。
カスタマージャーニーマップのフェーズに合わせてキーワードを選定する
最後に、カスタマージャーニーマップのフェーズに合わせてキーワードを選定します。
| カスタマージャーニーマップのフェーズ | キーワード例 |
|---|---|
| 情報収集段階 | SEO対策とは SEO対策 メリット |
| 比較・検討段階 | SEO対策 会社 SEO対策 おすすめ |
上記のように、カスタマージャーニーマップにおいてどのフェーズにいるかによって、見込み顧客が使用する検索キーワードは変化します。
集客したユーザーを見込み顧客から顧客へと変化させるためには、カスタマージャーニーマップのフェーズに応じた記事を作成し、リードナーチャリングを実施することが重要です。
BtoB事業のWEB集客における記事制作の流れ
BtoB事業のWEB集客における記事作成の手順は、以下の通りです。
- 記事作成の目的とゴールを明確に決める
- キーワードと記事テーマを選定する
- 記事の構成を作成する
- 執筆をする
- 関連する画像を用意する
- title・Descriptionの設定を行う
- 記事を公開する
それぞれの手順について詳しく解説します。
STEP1. 記事作成の目的とゴールを明確に決める
BtoB事業のWEB集客における記事作成では、始めに記事作成の目的とゴールを明確に決めます。自社のWEBサイトを運営する目的が問い合わせを獲得することである場合でも、すべての記事が問い合わせに直結するわけではありません。
一般的にサービスページは比較・検討段階の見込み顧客から問い合わせを獲得することが目的ですが、情報収集している見込み顧客に向けた記事はリードナーチャリングが目的の場合もあります。
記事を作成することで読者に取ってもらいたい具体的な行動は何か、何をKPIとするのかを明確にすることが重要です。
STEP2. キーワードと記事テーマを選定する
次に、キーワードと記事テーマを選定します。
BtoB事業の記事制作においてキーワード選定が必要な理由は、検索ユーザーが使用するキーワードの中には、見込み顧客ではないユーザーしか使用しないキーワードもあるからです。
たとえば、「YouTube 動画 作り方」と検索するユーザーはYouTube動画の制作会社の見込み顧客である可能性はありますが、「YouTube 稼ぎ方」と検索するユーザーは見込み顧客ではありません。
同様に、オンラインアシスタントサービスを提供する企業の見込み顧客は「オンラインアシスタントになるには」と検索することはありませんが、「オンラインアシスタント 比較」と検索するユーザーは見込み顧客である可能性が高いです。
記事を作成する前にキーワードを選定することで、誰が使用するキーワードなのか、検索意図は何か、記事を読む読者にとってのゴールは何か、自社の問い合わせに繋がる見込みはどのくらいあるのかを確認できます。
キーワードの選定方法については、前述した「BtoB事業の記事作成におけるキーワード選定の方法」を参考にしてください。
STEP3. 記事の構成を作成する
次に、キーワードと記事テーマに合わせて記事の構成を作成します。
記事の構成を作成せずに執筆すると、読者にとって必要のない情報を盛り込んでしまったり、優先順位が低い情報を記事の前半に配置してしまったりする恐れがあります。
検索エンジンから流入するユーザーは自身が抱える問題を解決するために記事を読むため、記事の冒頭部分に余計な情報が書かれていると、最後まで読まずに離脱するかもしれません。
たとえば、ターゲットキーワードが「検索順位 上げる方法」の場合、ユーザーは検索順位をどうすれば上げられるのかを知りたいわけです。検索順位とはなにか、検索順位を上げるとどのような効果が期待できるのかについてはすでに理解している可能性が高いため、あえて書く必要はありません。
検索ユーザーの検索意図は何かを検討し、すべての検索意図が網羅された構成を作成することが重要です。
STEP4. 執筆をする
次に、作成した構成に従って執筆をします。
BtoB記事の執筆では、一般消費者や利用者に向けて執筆するのではなく、企業において決裁権のある役職者や担当者に向けて執筆することが重要です。たとえば、「勤怠管理システム」というキーワードで記事を作成する場合、企業の経営者層や勤怠管理に関わる部署の責任者に向けて、記事を作成します。
勤怠管理システムを導入することで担当者の勤怠管理作業が楽になるとアピールするのではなく、企業としてどのようなメリットがあるのかを解説しなければいけません。
STEP5. 関連する画像を用意する
次に、記事の内容に関連する画像を用意し、記事に設置します。
BtoB記事に関連する画像は以下の通りです。
- 会社の外観
- 経営者・社員の画像
- 提供する商品・サービスの特徴が分かる実際の画像
BtoC記事ではフリー画像サイトから画像を入手するケースがありますが、BtoB記事では自社で用意した画像を使用することが重要です。
BtoB事業では競合他社と比較されるケースが多いため、自社とは関係のない画像や架空の画像を使用しても効果的ではありません。
たとえば、小売店に向けて冷蔵ケースを製造・販売している企業の場合、冷蔵ケースのフリー画像を用意するのではなく、自社が製造・販売する冷蔵ケースを撮影して画像を用意する必要があります。
また、フリー画像サイトで入手できる画像はネット記事や広告などで全く同じ画像を目にする機会が多いため、記事に使用しているとフリー画像だとすぐに分かってしまいます。
競合サイトと同じ画像を使用してしまうことを避けるために、できるだけ自社でオリジナル画像を用意するようにしましょう。
STEP6. title・Descriptionの設定を行う
次に、タイトルタグや見出しタグ、ディスクリプションタグなどのmetaタグを設定します。
| metaタグ | 設定する目的 |
|---|---|
| タイトルタグ | 検索ユーザーと検索エンジンに記事の概要を端的に伝える |
| 見出しタグ | 記事の主要なテーマを検索ユーザーと検索エンジンに伝える |
| ディスクリプションタグ | 検索結果に記事の概要文を表示させる |
metaタグには記事の内容やターゲットキーワードを伝える効果があるため、適切な方法で設定することが重要です。
STEP7. 記事を公開する
最後に、WEBサイトへ記事を公開します。
記事を公開する間に確認する項目は以下の通りです。
- 誤字脱字はないか
- 見込み顧客へ向けた文章・文脈になっているか
- 検索意図は網羅されているか
- スマホからでも読みやすくなっているか
- 記事の表示速度に問題はないか
- パーマリンクの設定は適切に行われているか
上記の中でも、パーマリンク設定については後から変更すると問題が発生する恐れがあるため、公開時にチェックしておく必要があります。
また、コンテンツSEOにおいては記事を作成することがゴールではありません。
ターゲットキーワードで記事が上位表示されているか、検索順位が低下していないか、情報は最新のものか、問い合わせなどのコンバージョンに繋がっているかなど効果を定期的に検証し、課題がある場合にはリライトすることが重要です。
BtoBに関する記事制作例
【 株式会社ガイアックス】

株式会社ガイアックスは、SNSマーケティングからインフルエンサーマーケティングに至るまで、幅広いマーケティング支援を行う企業です。
ソーシャルメディアの管理を得意とし、顧客に最適な戦略を提供しています。オウンドメディアでは、ターゲットオーディエンスに合わせた価値あるコンテンツを提供し、ブランドの信頼性と認知度を高めています。
このサイトは、プラットフォームや施策内容、業種別にタグが設定されており、ユーザーが求める情報に容易にアクセスできる設計となっています。
SEO戦略やデータ分析を活用し、コンテンツ配信とターゲティングを効果的に行うことで、エンゲージメントと顧客ロイヤルティの向上に貢献しています。
まとめ
今回は、BtoB事業のWEB集客において記事作成を行うメリットからキーワード選定の方法、記事作成ポイント、推奨文字数と推奨記事作成数、記事作成の流れまでを解説しました。
BtoB記事作成においては、問い合わせに繋がる見込み顧客にアプローチできる記事を作成することが重要です。一般消費者ではなく、企業の担当者が読むことを意識して記事を執筆する必要があります。
また、記事の最後に、問い合わせページやホワイトペーパーダウンロードページへのリンクを設置することも重要です。
検索意図を満たす記事を作成するだけでなく、問い合わせに繋がる文脈になっているかを意識して記事を作成しましょう。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
 コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/12
コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/12
コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/12
コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/09
コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/09
コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/092025/09/09
-
 コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/30
コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/302025/10/30