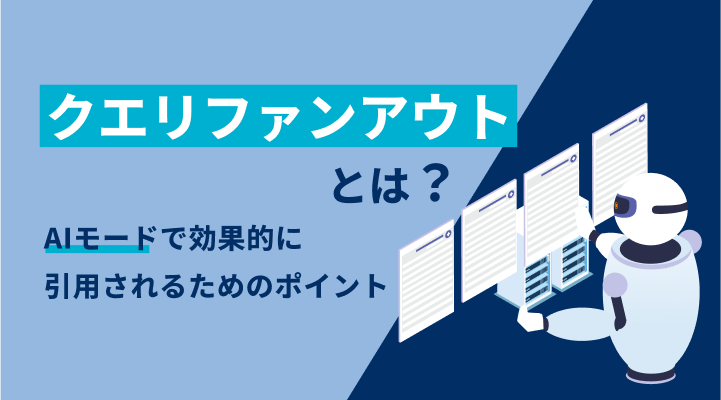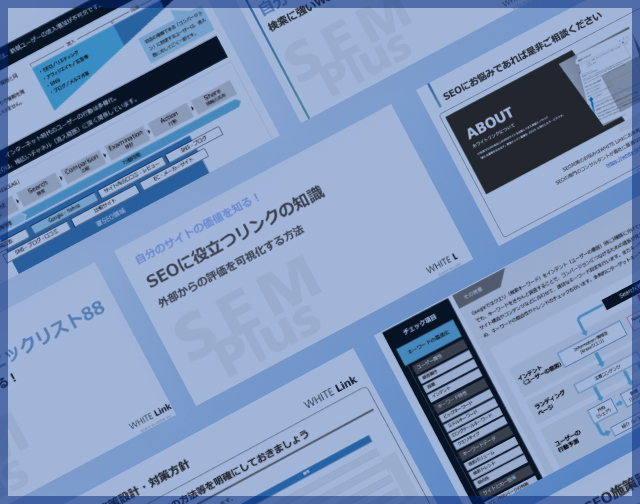E-E-A-Tとは?GoogleのSEOで重要な評価概念と対策方法を解説

SEOを行っていると「E-E-A-T」をよく耳にすると思いますが、概要は理解していても具体的な内容や何をすればE-E-A-Tの評価が高くなるのか分からない方も多いかと思います。今回は、Google検索品質評価ガイドラインの翻訳と実際の経験を元に、E-E-A-Tについてと評価を高める方法を完全解説します。
E-E-A-Tとは
E-E-A-Tとは、「経験、専門性、権威性、信頼」の4つの観点からGoogleがページやWebサイトの信頼性や品質を評価するためのコンセプトのことで、「イーイーエーティー」もしくは「ダブルイーエーティー」と読みます。
E-E-A-Tは、次の4つの単語の頭文字を取っています。
- Experience
-
経験
- Expertise
-
専門性
- Authoritativeness
-
権威性
- Trust
-
信頼
【参考】品質評価ガイドライン
Googleはユーザーが検索したキーワードと関連性が高く、最も役に立つと判断されたコンテンツを提供するために、日々アルゴリズムを改良しています。
E-E-A-Tは直接的なランキングアルゴリズムではありませんが、E-E-A-Tを意識したコンテンツ作成はGoogleが評価する高品質で信頼性のあるコンテンツにつながるため、検索結果の上位表示につながります。
Google の自動システムは、さまざまな要因に基づいて優れたコンテンツをランク付けするように設計されています。関連するコンテンツを特定した後、最も役に立つと判断されたコンテンツに高い優先順位を付けます。そのために、どのコンテンツが、エクスペリエンス(Experience)、高い専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)、すなわち E-E-A-T の面で優れているかを判断するための要素の組み合わせを特定します。
E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて
中略
E-E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありませんが、E-E-A-T が優れているコンテンツを特定できる要素の組み合わせを使用することは有効です。

経験(Experience)
経験(Experience)とは、コンテンツ制作者が実際にそのテーマを体験したことがあるかどうかを評価する指標です。Googleは、実体験に基づいたコンテンツを信頼性が高いものと判断する傾向にあります。
例えば、以下のような2つのサイトがあったとします。
- サイトA
-
観光地の基本情報のみ掲載
- サイトB
-
基本情報に加え、実際に訪れた人の写真・感想・注意点なども記載
この場合、経験が反映されているサイトBの方がGoogleから評価されやすくなります。
その他にも、「経験」として評価されやすい具体例は以下になります。
| 例 | 経験の内容 | 評価されやすい理由 |
|---|---|---|
| 商品レビュー | 実際に商品を購入し、使用感や効果を記載 | 体験ベースのため、信頼性が高い |
| ソフトウェアの体験談 | 長年の開発経験者によるツール使用レビュー | 熟練者の意見に重みがある |
| サービス導入体験 | サービスを試した経緯や得られた結果を解説 | ユーザーの判断材料になる |
経験をコンテンツに明確に反映させるためには、具体的な体験談や経験談と合わせて、写真や動画などの体験を裏付ける証拠を添えることで、ユーザーにとって信頼性の高い情報として伝わりやすくなります。
専門性(Expertise)
専門性(Expertise)は、コンテンツ制作者やWebサイトが、その分野で専門的な知識やスキルを持っているかどうかを評価する指標です。
特定のジャンルに精通している専門家が作成したコンテンツは、ユーザーにとって信頼できるものと見なされやすくなります。
例えば、以下のようにサッカー用品を紹介する2つのメディアがあったとします。
- サイトA
-
趣味でサッカーをしている一般人が運営
- サイトB
-
サッカー連盟が運営
この場合、サッカーに関する専門性の高いサイトBの方がGoogleから評価されやすくなります。
その他にも、「専門性」として評価されやすい具体例は以下になります。
| 例 | 専門性の内容 | 評価されやすい理由 |
|---|---|---|
| SEOのメディア | SEO会社が運営:SEOに特化したテーマを扱っている | 実務経験に基づいた知識だから信頼性が高い |
| 医療情報サイト | 病院が運営:医師・薬剤師など医療従事者が執筆・監修 | 専門資格があり、誤情報のリスクが低い |
| 法律に関する記事 | 法律事務所が運営:弁護士が書いた解説記事 | 法律知識が求められる分野のため専門性が重要 |
専門性の評価を高めるためには、サイト全体で扱うトピックを絞って専門性を高めたり、資格情報の掲載を行うなど、ユーザーから見て専門家が作成したコンテンツであることを示す必要があります。
権威性(Authoritativeness)
権威性(Authoritativeness)は、コンテンツ制作者やWebサイト、運営者が業界や分野でどれだけ認知・評価されているかを示す指標です。
Googleは、その分野における「公的な信頼」や「業界内での認知度」を重要視しており、「この人/この会社が言っているなら間違いない」と判断することができるWebサイトを評価します。
例えば、「トレーニング」に関する記事を比較した場合
- サイトA
-
設立して1ヵ月のトレーニングジム(被リンクは少ない)
- サイトB
-
大会で受賞歴のある人物が10年以上運営しているトレーニングジム(被リンクも多い)
この場合、サイトBの方がGoogleから「権威性が高い情報源」として評価されやすくなります。
その他にも、「権威性」として評価されやすい具体例は以下になります。
| 評価要素 | 権威性の内容 | 評価されやすい理由 |
|---|---|---|
| 被リンク | 権威のあるサイトからのリンク | 人気のページであるという客観的証明になる |
| 外部からの引用・掲載 | メディア・ニュースで紹介されている | 多数の人に信頼されている証拠となる |
| 著者の資格・肩書 | 医師、弁護士などのプロフィール情報 | 信頼できる知見を持っている証拠となる |
| 高評価のクチコミ | ビジネスに関する口コミ | 第三者のポジティブな評価は社会的信用になる |
| 賞の受賞歴 | 業界団体や第三者機関からの表彰 | 専門分野での実績がある証拠となる |
| 書籍や論文の執筆 | トピックに関する出版物がある | 専門家としての知識・認知度の証明になる |
Googleは、過去にコンテンツ作成者を評価する「Agent Rank」という特許を出願しているなど、「誰が作成者なのか」や「どのような組織が運営しているのか」といった権威性を、SEOの評価で重視しています。
信頼(Trust)
信頼(Trust)とは、コンテンツ制作者やWebサイト、運営者が発信する情報がどれだけ正確で、安心して参照できるかを示す指標です。
どれだけ専門知識があり、豊富な実体験を語っていても、その情報が詐欺的だったり、虚偽を含んでいたり、運営元が不透明な場合は、ユーザーに悪影響を与える恐れがあるため、Googleはそのページを評価しません。
| 項目 | サイトA(信頼性が低い) | サイトB(信頼性が高い) |
|---|---|---|
| 運営者情報 | 不明/記載なし | 企業情報・連絡先・責任者を記載 |
| SSL対応 | http(非SSL) | https(SSL対応) |
| ポリシー | 見当たらない | 返金・返品・プライバシーのポリシーがある |
| 著者情報 | 誰が書いたか不明 | 専門家プロフィールあり/監修付き |
| 外部評価 | クチコミなし/低評価 | 高評価のクチコミ・外部からの引用あり |
特にユーザーの生活や人生に関わるYMYL領域では、「信頼」は厳格に評価されGoogleから高い水準が求められます。
信頼性の低いWebサイトは、ページがインデックスされても上位表示されなかったり、強調スニペットやAIによる概要(AI Overviews)に選ばれにくくなります。そのため、ユーザーから信頼されるWebサイトとは何か考えて取り組みましょう。
E-E-A-Tの中で最も重要な項目は信頼
ここまでE-E-A-Tの4つの項目について解説しましたが、この中で最も重要な項目は「信頼」です。
なぜなら、E-E-A-Tの「信頼」は独立した評価指標であると同時に、「経験」「専門性」「権威性」3つの要素が積み上がった結果として評価される要素だからです。
例えば、
コンテンツ作成者がその分野での深い知識を持ち(専門性)
実際にそのテーマに関連する体験や経験をしており(経験)
他者からの評価や引用、社会的な実績も備えている(権威性)
このように3つの項目を満たして、初めて「この情報は信頼できる」とGoogleに評価され、検索順位の上昇につながります。
Google検索品質評価ガイドラインにおいても、「Trust」は 189回「Experience」は115回「Expertise」は78回「Authoritativeness」は9回記載されており、Googleが「信頼」を特に重視していることがわかります。
GoogleはE-E-A-Tをどのように使用しているのか?
Googleは毎年、世界中で1万人以上の「検索品質評価者」に対してトレーニングを行い、38万件以上の検索結果に対する評価を実施しています。
この評価プロセスの中で中心的に用いられている概念が 、「E-E-A-T」です。
検索品質評価者は、Googleが公開している「検索品質評価ガイドライン」に沿って、検索結果に表示されたページがユーザーの検索意図に合致しているか、そしてそのコンテンツが誰によって、どのような立場・経験・専門性のもとで作られたものかをE-E-A-Tの観点から人の目で評価します。
ただし、ここでの評価自体が検索順位に直接的な影響を与えることはありません。
評価者のスコアはあくまでGoogleがアルゴリズムを調整・改善する際の参考データとして活用され、最終的に「人間が高品質と感じる結果と、機械が導き出す結果が一致するかどうか」を検証するために使われます。
E-E-A-T評価を高める方法
E-E-A-Tは、一つの技術や要素で簡単に高められるものではなく、コンテンツの質、発信者の信頼性、外部からの評価、そしてサイト全体の設計や体制まで、幅広い観点から総合的に評価されます。
本記事では、E-E-A-Tの4つの要素それぞれに対して、具体的にどのような対策を行えば良いのか項目ごとに解説します。
| 項目 | E-E-A-T | |
|---|---|---|
| 1 | 経験や体験をもとにしたコンテンツを制作する | 経験・体験 |
| 2 | サイトのテーマを特化させる | 専門性 |
| 3 | 専門家が作成・監修を行う | 専門性 |
| 4 | 信頼性の高い情報やデータを引用元として記載する | 専門性 |
| 5 | 被リンクを獲得する | 権威性 |
| 6 | サイテーションを獲得する | 権威性 |
| 7 | 受賞歴や表彰歴を掲載する | 権威性 |
| 8 | Wikipediaに掲載される | 権威性 |
| 9 | 運営者情報・会社概要を充実させる | 信頼 |
| 10 | SSL化対応を行う | 信頼 |
| 11 | Whois情報を公開する | 信頼 |
| 12 | 評判の良いクチコミを増やす | 信頼 |
それぞれ詳しく解説します。
経験や体験を元にしたコンテンツを制作する
経験(Experience)の評価を高めるためには、著者自身が実際に体験・経験した内容をコンテンツに盛り込むことが重要です。
実体験を元にしたコンテンツとは、以下のように実際に行動・体験したことを元に構成された情報を指します。
実際にその場所に行って体験した旅行記やレビュー
実際に製品・サービスを使った感想
自分自身で施策を実行した際の結果や考察
現場での実務経験に基づいたノウハウや成功事例
どのような体験や経験が評価されるかは、コンテンツのテーマによって異なります。
例えば、本メディアのようにSEOに関するメディアであれば、ユーザーは「実践的なノウハウ」や「成果につながる事例」を求めているので、クライアントに対して実際に施策を行った施策やその結果を経験談としてコンテンツに反映させます。
サイトのテーマを特化させる
サイトのテーマやジャンルを特定のトピックに絞り特化することで、専門性を高めることができます。複数のテーマを扱うサイトの場合、トピックごとの専門性が薄くなりやすく、ユーザーにもGoogleにも「このサイトは何に詳しいのか」が伝わりにくくなります。
一方、特定のトピックに特化したサイトは、ユーザーとGoogleに「このサイトはこの分野の専門家である」と認識されやすくなり、E-E-A-Tの評価に良い影響を与えます。
| 項目 | サイトA(テーマ特化型) | サイトB(雑記型) |
|---|---|---|
| テーマ | 「敏感肌スキンケア」に特化 | 美容・ガジェット・旅行など雑多な話題 |
| コンテンツ内容 | 著者の肌トラブル体験、特定商品の長期使用レビュー、専門家監修あり | 流行に合わせて様々な商品や話題を広く浅く紹介 |
| 専門性 | 同じテーマで多角的な情報を網羅。専門サイトとして認識されやすい | 各ジャンルの情報量が少なく、専門性が伝わりにくい |
特定トピックに特化したサイトAのような構成を目指すことで、E-E-A-Tの「専門性」を高めることができます。
特に競合性の高い業界ジャンルにおいては、「このテーマならこのサイト」と認識される状態を作ることがSEO成功の鍵となります。
専門家が作成・監修を行う
専門性を高めるために、専門家の監修やインタビューの実施を検討しましょう。特に医療・法律・お金などのYMYLに関するジャンルでは、専門家の関与が評価に大きく影響します。
Googleは「信頼できる情報源からの情報」を重視しているため、誰が書いたのか・監修したのかをGoogleに伝えることが大切です。
以下のように専門家としての実在性をGoogleに伝えた上で、コンテンツの作成や監修を行いE-E-A-Tを高めましょう。
| 対応項目 | 内容 |
|---|---|
| 構造化データ | PersonやMedicalBusinessなどの構造化データを使って、監修者の氏名・資格・所属などをマークアップする |
| 監修者プロフィールページの作成 | 経歴・保有資格・所属団体・外部での活動実績(書籍、登壇、論文、SNSなど)を記載 |
| メディアへの露出 | 様々なメディアに寄稿したり、イベントに登壇する |
信頼性の高い情報やデータを引用元として記載する
情報の信頼性を担保するために、信頼できる情報源からのデータや根拠を引用元として記載することは、E-E-A-Tの「信頼性」を高める上で重要です。
信頼性が高い引用元の例は、以下の通りです。
行政・国会・司法などを含む公的機関
メーカーの公式ページ
研究機関や企業の調査結果・統計データ・公式発表
論文
大手新聞社・メディアの報道
このように、政府機関、大学、研究機関、業界団体、信頼性のある報道機関など、信頼性の高い出典を明示して引用することで、ユーザーに対して「この情報は信頼できる根拠に基づいている」と伝えることができます。
正確な情報を引用することは、ユーザーが信頼できる情報源としてページを安心して利用することにも繋がります。
被リンクを獲得する
権威性を高めるためには、被リンクの獲得が効果的です。
Googleは被リンクが集まっているWebサイトを、「人気のサイト」として扱っています。そのため、人気のサイトや信頼性の高いサイトから多くリンクされているページは、「第三者からも信頼されている情報源」と見なされます。
公的機関・大学からのリンク
大手メディア 同業界のメディアからのリンク
多くの被リンクを獲得しているサイトからのリンク
上記のように、知名度の高いサイトや公的機関からリンクされているWebサイトは、E-E-A-Tの評価においても高評価につながります。また、同じ業界の専門家からリンクされているということは、その業界において権威があるという証明となります。
被リンクを集めるのは簡単ではなく、時間もかかりますが中長期的に見ると効果の高い施策になるためぜひ取り組んでみてください。
被リンクの獲得方法については、別の記事で詳しく解説しています。
サイテーションを獲得する
Googleは、サイテーションを「認知度」の証拠とみなしており、被リンクと同じようにE-E-A-Tの中の「権威性」に影響します。
サイテーションとは、自社のサービス名やブランド名、コンテンツ作成者の名前などが他のサイトで言及されることを指します。複数のサイトで言及されることで、「人気である」「信頼されている」サイトとして判断されます。
サイテーションを増やすためには、自社の情報を第三者メディアに掲載してもらう機会を増やすことが重要です。
例えば、プレスリリースを活用して様々なメディアに転載されるように情報発信を行ったり、ニュースメディアに記事を寄稿することで、取材される仕組みを作ることなどが挙げられます。
被リンクと同様、サイテーションも増やすのが難しいですが、継続して取り組むことで権威性を高めましょう。
受賞歴や表彰歴を掲載する
Webサイトに権威性の高い団体や行政機関による受賞歴や表彰歴を掲載することで、E‑E‑A‑Tの権威性と信頼性を高めることができます。
Googleの検索品質評価ガイドラインの中でも、業界の賞は「信頼できる証」として言及されています。そのため受賞歴や表彰歴がある場合は、自社のホームページに記載するのがおすすめです。
掲載する項目は、「賞の名称」「授与元の団体名/主催者」「受賞時期(年・月)」「賞の内容や選考の概要」「写真、表彰式の様子」を掲載すると、ユーザーにもどのような賞を受賞したのかわかりやすく伝えることができます。
また、検索エンジンが理解しやすいように以下2点を意識してWebサイトに掲載しましょう。
- 受賞実績を写真・ロゴ付きで魅せる
-
受賞トロフィーや授賞式の写真、賞のロゴを掲載することで「実在する公式の賞」であることが伝わります。
- 受賞を裏付ける第三者ソースへのリンク
-
公式プレスリリースや表彰団体サイト、報道記事などへのリンクを付けることで、実際に存在する賞であること・実際に受賞したことを伝えることができます。
また、受賞までの活動や取り組み、評価された理由などを記事にしておくことで、ユーザーに自社の取り組みについて伝えることができます。
Wikipediaに掲載される
Wikipediaは、Google検索品質評価ガイドラインで176回も言及されていることから、Googleが信頼している参照元の1つだと考えられます。
Wikipediaは、Googleから「高品質かつ中立的な第三者情報源」として特別に扱われているWebサイトです。そのため、Wikipediaの中で会社名やサービス名、人物名などが記載されていれば、「この会社は社会的にも認知されており、信頼できる存在である」という証拠となります。
ただし、Wikipediaに掲載するのは簡単ではありません。Wikipediaは誰でも編集可能な一方で、商業目的の編集行為や中立性に欠ける投稿はすぐに削除される傾向があります。
また、企業ページやサービスページを新規作成する場合も、「信頼できる二次情報源によってすでに広く言及されている」ことが掲載の前提条件とされています。
そのため、Wikipediaに掲載されるようにプレスリリース・メディア掲載・受賞歴などを積み重ねながら知名度を高めていきましょう。
運営者情報・会社概要を充実させる
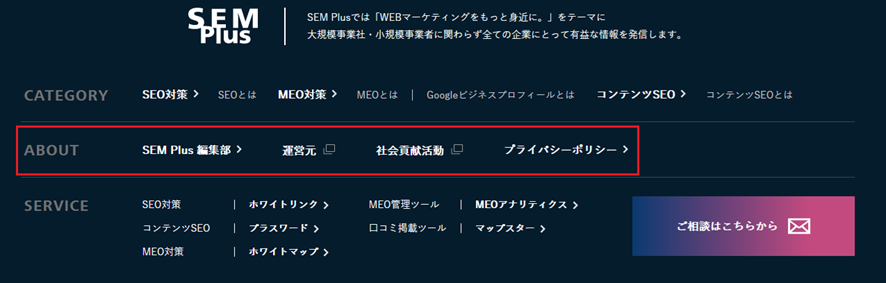
Webサイトの運営者情報・著者情報・会社概要を充実させることで、サイトの信頼性を高めることができます。
設立年月日
取得資格・加盟団体
返品返金ポリシー
プライバシーポリシーの明記
コンテンツ制作方針・ガイドライン
Q&A
このように、ユーザーがサービスの導入や商品を購入するにあたって、会社やサイトを信頼するための情報をしっかりと記述して会社情報を充実させましょう。
会社概要に記載する情報は構造化データを使ってマークアップすると、より検索エンジンが情報を理解しやすくなります。
SSL化対応を行う
SSL化対応とは、Webサイトとユーザー間の通信を暗号化する仕組みのことで、URLを「http://」から「https://」に変える対応のことを指します。
SSL化されたサイトであれば、第三者による情報の盗聴や改ざんを防ぐことができるため、ユーザーは安全にWebサイトを利用できます。
Googleは2014年に、SSL化が検索順位を決定する1つの要素だと発表しており、SSL化されたサイトを優遇しているため必ず対応する必要があります。
なお、SSLには3つの認証レベルがあります。
無料のドメイン認証(DV)
企業実在認証(OV)
拡張認証(EV)
SSL化するなら無料のドメイン認証でも問題ありませんが、信頼性に重点を置くなら企業実在認証(OV)以上がおすすめです。
Whois情報を公開する
Whois情報を公開すれば、「誰がこのサイトを運営しているのか?」を示すことができるためE-E-A-Tの信頼性の向上に繋がります。Whoisとは、ドメインの登録者情報をインターネット上で確認できる仕組みで、通常は登録ドメイン名、登録者の名前や組織名、住所、電話番号、メールアドレスなどが含まれます。
Whois情報が公開されていれば、検索エンジンやユーザーに対して「実在する運営者が責任を持ってサイトを管理している」という印象を与えることができます。
Whois情報を公開するかしないかは細かい施策ではありますが、Whois情報を公開することで、誰がドメインの登録者なのかをユーザーと検索エンジンに伝えることができるため、信頼性を高めることができます。
評判の良いクチコミを増やす
「評判の良いクチコミを増やす」ことで、E-E-A-Tの中の信頼性を向上させることができます。
Googleは品質評価ガイドラインの中で「第三者からの評価や評判を参考にして、コンテンツや運営者の信頼性を判断する」と明言しており、クチコミ(レビュー)はその代表的な指標となっています。
そのため、Googleビジネスプロフィールや業界特化型のレビューサイトなどで高評価の口コミが多い企業は、Googleからもユーザーからも信頼できる企業とみなされます。
また、口コミの数が競合他社よりも大幅に少ない場合は、競合他社のほうが権威性が高いサイトと判断されている可能性があるため、オンライン上にある自社の口コミを増やすための広報・PR活動に力を入れていきましょう。
高いE-E-A-Tが必要になるYMYLジャンル
YMYLとは、「Your Money or Your Life」の頭文字を取った言葉で、ユーザーの健康・お金・安全など、人生に重大な影響を及ぼす可能性のあるテーマのことです。
YMYLに該当するジャンルでは、Googleは特にE-E-A-Tを厳しく評価しています。というのも、YMYLジャンルで誤った情報が提供されると、ユーザーが直接的に被害を受ける可能性があるからです。
例えば、医療サイトで誤った治療法を紹介していたり、金融サイトで根拠のない投資話を薦めていた場合、ユーザーは健康やお金に損害を受けることになります。
Googleはこのようなリスクを避けるため、YMYLジャンルにおいては、専門家によるサイトの運営や執筆・監修、運営者の権威性などを厳密に評価し、E-E-A-Tの基準を満たすWebサイトだけを上位表示するようにしています。
実際に、Googleは検索品質評価ガイドラインの中で「YMYLに関するトピックのページでは、「信頼性」により一層の注意を払い、E-E-A-T の評価にもより慎重さが求められます。」と明記しており、かなり厳しくサイトを見ています。
Pages on YMYL topics require more attention to Trust and more care in the assessment of E-E-A-T.
General Guidelines
そのため、YMYLジャンルに該当するWebサイトを運営する場合は、E-E-A-Tの評価を高めるように注意してサイト運営を行ってください。
YMYLについては、別の記事で詳しく解説します。どのようなジャンルがYMYLに該当するのか確認してみてください。
E-E-A-Tの評価が高いサイトの例
E-E-A-Tは抽象的な概念のため、「実際にどのようなサイトが高く評価されているのか」を知ることが大切です。
本記事では事例として、経験・専門性・権威性・信頼の各観点で優れていると考えられる以下2つのWebサイトで、それぞれがどのような点でGoogleから高い評価を受けているのかを分析していきます。
国立研究開発法人国立がん研究センター
e☆イヤホン
自社のWebサイトと照らし合わせながら、どのような要素を取り入れればE-E-A-Tを強化できるかを考えるヒントにしてください。
事例①:国立研究開発法人国立がん研究センター

がん患者や家族向けの体験談や支援事例の掲載があり、患者視点や医療現場の一次情報を含んでいます。
国立がん研究センターに所属している医師や、がん医療の第一人者や専門機関によって監修・作成された情報が中心。記事ごとに専門医・看護師・薬剤師などが分野別に執筆・監修している。また、診療ガイドラインやエビデンスに基づく科学的情報を公開しています。
運営主体が、国立研究開発法人(厚労省所管の公的研究機関)医療機関・報道機関・行政機関のWebサイトからも頻繁に参照されています。
長年にわたる運営実績(1997年〜)がある。また、編集方針・監修体制・利用規約・問い合わせ先・プライバシーポリシーなどが明示されている。出典の明記(診療ガイドライン、論文など)により、ファクト確認が可能です。
事例②:e☆イヤホン

実際に商品を使用したスタッフによるレビューや、試聴記事が数多く掲載されており、単なるスペック紹介にとどまらないリアルな使用感や音質について詳しく解説されています。
取り扱っている商品が、イヤホン・ヘッドホンに特化しているWebサイトのため高い専門性があります。また、用途別・ジャンル別にわかりやすく作られており、イヤホンやヘッドフォンに関する専門知識が感じられます。
e☆イヤホンはオーディオファンの間で広く認知されている老舗専門店であり、多くのメディアやメーカーとも連携しています。実際、メーカーとのコラボ商品や限定モデルの開発に関わるなど、業界内での認知度も非常に高く、専門メディアやイベントにも度々登場しています。
会社概要、住所、電話番号、問い合わせ先、返品・交換の規定などが記載されています。レビューや比較記事においてもPR・非PRの明示や根拠ある情報提供を行っています。
E-E-A-Tが導入された2つの背景
GoogleがE-E-A-Tを評価基準に導入した背景には、次の2つの理由があります。
検索体験の質向上のためのGoogleの方針
フェイクニュースや誤情報の排除
それぞれ詳しく解説します。
検索体験の質向上のためのGoogleの方針
Googleは常に、「ユーザーにとって有益な検索結果を提供すること」を最優先にしています。その一環として、検索結果の品質を評価する指標として導入されたのがE-A-T、そして現在のE-E-A-Tです。
2000年代~2010年前半の検索では、キーワードの詰め込みや被リンクの数など、技術的なSEOテクニックによって「検索上位に表示されてしまう質の低いページ」が多く存在していました。
しかし、Googleのアルゴリズムも進化し「検索意図に正確に応え、信頼できる情報を提供するコンテンツ」を高く評価できるようになっています。
現在では、コンテンツそのものの内容だけでなく「この情報は誰が書いているのか?」「どのような経験・専門性・立場に基づいたものなのか?」といった背景まで含めて評価されるようになっており、それを正しく判断するための軸としてE-E-A-Tが不可欠な存在となっています。
フェイクニュースや誤情報の排除
インターネット上には膨大な情報がありますが、その中には誤った情報、意図的なフェイクニュースも含まれています。その中で、Googleは検索エンジンの責任として「正確で信頼できる情報を優先表示する」アルゴリズムへと進化させてきました。その進化の一環として導入されたのが、E-E-A-Tの概念です。
Googleは、単に情報が多く掲載されているだけのページや、話題性・感情的な表現に頼ったコンテンツよりも、実際の経験に基づいて書かれた内容や、専門的な知見に裏付けられた情報を評価する方向へとシフトしています。
特に医療、法律、金融といったYMYLの分野においては、誤情報がユーザーの健康や生活、財産に深刻な影響を与える可能性があるため、情報の質や発信者の信頼性が従来以上に厳しく問われます。
E-E-A-Tは、こうしたリスクの高い領域で情報の正確性と信頼性を担保するための「品質フィルター」として機能しており、検索結果に表示されるページの選定に大きな影響を与えています。
E-E-A-Tに関するよくある質問
E-E-A-Tに関するよくある質問を解説します。前もって疑問を解消し、高品質でユーザーに役立つコンテンツを制作しましょう。
E-E-A-Tはスコア化されている?
GoogleはE-E-A-Tを「アルゴリズム上の直接的な評価指標」としてスコア化しているわけではありません。ただし、E-E-A-Tに関連するさまざまなシグナルをもとに、検索アルゴリズム全体として「品質の高いページかどうか」を判断しています。
E-E-A-T(E-A-T)はいつから導入された?
E-A-Tという概念は2014年にGoogleの検索品質評価ガイドラインで初めて導入されました。
その後、2022年12月のガイドライン改訂で、E-A-Tの最初に「Experience(経験)」が追加され、現在のE-E-A-Tという形になりました。
E-E-A-TはすべてのWebサイトに適用される?
Googleは、全てのジャンルのWebサイトにおいてE-E-A-Tを評価の参考にしていると明言しています。 そのため、どのようなサイトであっても、「経験・専門性・権威性・信頼性」が求められます。ただし、ジャンルによって評価の「厳しさ」や「求められる水準」は異なります。
E-E-A-Tの評価が低いWebサイトはどうなるの?
E-E-A-Tの評価が低いWebサイトは、Google検索において「信頼性の低い情報源」と判断され、検索順位が下がったり、上位表示されにくくなったりする可能性があります。
評価が低いということは、Googleから「そのページはユーザーのニーズや信頼を十分に満たしていない」と判断されているということです。
まとめ|E-E-A-Tを意識した高品質コンテンツで上位表示を目指そう
E-E-A-Tは検索品質評価者が、コンテンツ作成者やサイト運営者が信頼できるかどうかを判断するための指標です。そのため、E-E-A-Tはランキングには直接関係する指標ではありません。
しかしながら、自サイトのE-E-A-Tを評価することで、Googleが重視する「ユーザーにとって有益で信頼できる情報かどうか」という観点に沿った改善ポイントが明確になります。
そのため、E-E-A-Tの評価を元にWebサイトを改善し続ければ、結果的に検索順位の向上や、信頼性のあるサイトとしてのブランド価値向上につながります。
E-E-A-Tは一朝一夕で改善できるものではありませんが、継続的に取り組むことでGoogleとユーザーの双方から評価される「本質的に価値のあるWebサイト」を構築できるため、ぜひ取り組んでみてください。
以上、E-E-A-Tについての解説でした。
なお、弊社ではE-E-A-Tの評価を元にWebサイトのSEO上の課題を解決するためのコンサルティングサービスを行っています。ノウハウやリソースがなく中々SEOに取り組めていない方は、ぜひお問合せくださいませ。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
 SEO対策リッチリザルトとは?種類と表示のさせ方・表示されない原因を解説2026/02/03
SEO対策リッチリザルトとは?種類と表示のさせ方・表示されない原因を解説2026/02/032026/02/03
-
 SEO対策【2026最新版】検索順位チェックツールおすすめ10選!無料・有料それぞれ紹介2026/02/03
SEO対策【2026最新版】検索順位チェックツールおすすめ10選!無料・有料それぞれ紹介2026/02/032026/02/03
-
 SEO対策Googleクローラーとは?仕組みと申請方法・巡回頻度を高めるやり方2026/02/02
SEO対策Googleクローラーとは?仕組みと申請方法・巡回頻度を高めるやり方2026/02/022026/02/02
-
 SEO対策h1タグとは?初心者向けにSEO効果と正しい使い方を徹底解説2026/01/16
SEO対策h1タグとは?初心者向けにSEO効果と正しい使い方を徹底解説2026/01/162026/01/16
-
 SEO対策YMYLとは?対象ジャンルやSEOを成功させるためのポイントを解説2025/12/19
SEO対策YMYLとは?対象ジャンルやSEOを成功させるためのポイントを解説2025/12/192025/12/19
-
 SEO対策キーワード選定のやり方・コツを初心者向けに徹底解説2025/11/20
SEO対策キーワード選定のやり方・コツを初心者向けに徹底解説2025/11/202025/11/20