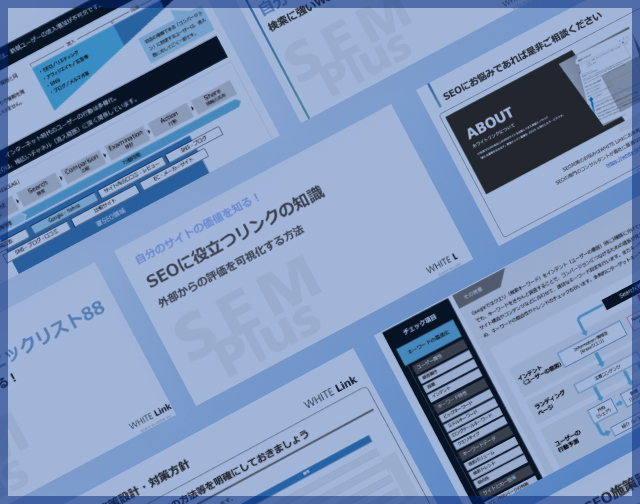LLMO診断・無料でできるチェックリスト40項目【2025最新版】

本記事では、自サイトが生成AIから引用参照されやすい状態になっているかを確認するためのLLMO診断の方法を解説しています。チェックリストを自分で診断できるように、解説とチェック方法を記載しています。本記事を参考に、自社サイトが生成AIから選ばれる情報源となるよう、Webサイトの最適化を進めてみてください。

LLMO診断を始める前に
LLMO診断を始める前に、LLMOとは何か、生成AIがどのように情報を収集しているか理解しておきましょう。
そもそも、LLMOとは、GoogleのAI OverviewやChatGPTが回答を生成する際に、自社名やブランド名について言及したり、自社のコンテンツが引用されるようにする対策のことです。
各社の生成AIは大きく次の2つの方法を使って情報を収集し、最適な回答を生成しています。
事前学習:書籍・Webページ・ニュースなど、公開情報を広く学習
検索拡張生成(RAG):リアルタイムの検索結果を取得し、それを元に回答を生成
そのため、LLMO診断では以下の視点でチェックを行います。
自社のコンテンツが、生成AIにとって収集・理解されやすい構造になっているか
自社サイトが、信頼できる情報源(エンティティ)として認識されているか
なお、各チェック項目を見ていくとわかる通り、LLMOはSEOの延長線上にある施策です。
確かに生成AIに引用されやすくするためのテクニックや工夫はありますが、基本的にはGoogleのガイドラインに沿った正しいWebサイト運営をしていれば、特別な対策は必要ありません。
▼ LLMOについて詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください。
→LLMOとは?対策方法と最適化の手順・自分で計測するやり方を解説
自分でできるLLMO診断チェックリスト一覧
LLMO診断は、以下のチェックリストを元に行います。
| カテゴリ | チェック項目 | 影響度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | クローラビリティ | llms.txtがルート直下に設置されているか | 【★☆☆】 |
| 2 | robots.txtとllms.txtの内容が矛盾していないか | 【★★★】 | |
| 3 | GPTBot(OpenAI)のクロールを許可 | 【★★★】 | |
| 4 | Google-Extendedのクロールを許可する | 【★★★】 | |
| 5 | クロールバジェットを最適化する | 【★☆☆】 | |
| 6 | レンダリング | SSR(サーバーサイドレンダリング)を利用する | 【★★★】 |
| 7 | JS遅延読込(LCP後に非必須JSを読み込む) | 【★★☆】 | |
| 8 | ハイドレーション失敗で本文が空になるページがないか | 【★☆☆】 | |
| 9 | CLS(レイアウトシフトの抑制) | 【★☆☆】 | |
| 10 | ページの表示速度 | 【★★☆】 | |
| 11 | 構造化データ | 記事の構造化データの追加 | 【★★☆】 |
| 12 | FAQ構造化データの追加 | 【★★★】 | |
| 13 | HowTo構造化データの追加 | 【★★☆】 | |
| 14 | 組織の構造化データの追加 | 【★★☆】 | |
| 15 | プロフィールページの構造化データの追加 | 【★★☆】 | |
| 16 | 一次ソースを明示する | 【★☆☆】 | |
| 17 | 根拠・情報源 | DOI / ISBN の記載 | 【★☆☆】 |
| 18 | 日時の記載 | 【★☆☆】 | |
| 19 | アップデート履歴の記載 | 【★☆☆】 | |
| 20 | 発リンク一次引用率 | 【★☆☆】 | |
| 21 | E-E-A-T | Knowledge Panel もしくはGBPの出現 | 【★★★】 |
| 22 | Wikipedia の掲載 | 【★★★】 | |
| 23 | ブランド名や企業名の引用数 | 【★★★】 | |
| 24 | 自社名やブランド名を含むアンカーテキストの数 | 【★★★】 | |
| 25 | 指名検索の数 | 【★★☆】 | |
| 26 | 著者経歴の構造化データ | 【★☆☆】 | |
| 27 | 権威性の高い受賞歴の記載 | 【★☆☆】 | |
| 28 | 会社概要・Aboutページの作成 | 【★★★】 | |
| 29 | 関連サイトからの被リンク | 【★★☆】 | |
| 30 | コンテンツ | 結論ファースト | 【★★★】 |
| 31 | FAQ形式 | 【★★★】 | |
| 32 | 1見出し1メッセージの構成 | 【★★☆】 | |
| 33 | ページ冒頭にページ全体の要約があるか | 【★☆☆】 | |
| 34 | サイト全体のテーマを絞る | 【★★☆】 | |
| 35 | 古くなった情報を書き換える | 【★★☆】 | |
| 36 | その他 | AIが学習するプラットフォームへの参加 | 【★☆☆】 |
| 37 | ソーシャルシグナルの獲得 | 【★☆☆】 | |
| 38 | カスタマージャーニーの段階に合わせたコンテンツ作成 | 【★★★】 | |
| 39 | リスト記事の作成 | 【★★★】 | |
| 40 | BingWebマスターツールの登録 | 【★☆☆】 |

【LLMO診断項目①】クローラビリティ
llms.txtがルート直下に設置されているか【★☆☆】
llms.txtとは、AIのクローラーに「このサイトの情報をAIに使ってほしいかどうか」や「ページの概要」を伝えるためのファイルです。検索エンジン向けのrobots.txt に似ていますが、対象はChatGPT、Gemini、Perplexityなどの生成AIクローラーです。
各生成AIの会社が正式に仕様として採用しているわけではありませんが、記述することで生成AIにぺージの概要を伝えることができます。Webサイトの一番上の階層(例:https://example.com/llms.txt)に設置します。
ブラウザを開き、アドレスバーにhttps://あなたのドメイン/llms.txt を入力してアクセス。
例:https://example.com/llms.txt内容が表示されればOK。llms.txt が正しく配置されています。
「404 Not Found」などが出た場合は、まだ設置されていない状態です。
→ llms.txtをテキストエディタや専用のツールで作成し、FTPやサーバー管理画面を使ってルートにアップロードしてください。
robots.txtとllms.txtの内容が矛盾していないか【★★★】
robots.txtはGoogleの検索エンジンに、llms.txtはAIに、それぞれWebページを見せる・見せないの指示を出すファイルです。これらが矛盾していないか確認します。
2つのファイルが同じディレクトリやページに対して、矛盾する指示を出していると、生成AIは混乱する可能性があります。例えば、llms.txt では「見ていい」と書かれているのにrobots.txt では「見ないで」と書いてある場合は、AIは見てはいけないと判断してしまう可能性があります。
robots.txtファイル、llms.txtファイル両方のファイルを開いて見比べます。
例えば、robots.txtで/blog/をDisallowしているのにllms.txtで/blog/をAllowしていたら、指示が矛盾している状態です。AIに見せたいなら、両方で「Allow」にしておく必要があります。
AIによっては、robots.txt 側に強く影響されることがあります。
GPTBot(OpenAI)のクロールを許可 【★★★】
GPTBotは、OpenAI(ChatGPT)に情報を提供するためのクローラーです。ChatGPT がWebから情報を収集するために利用しているGPTBotがWebサイトを読めないと、自サイトが引用の候補になりません。
llms.txt やrobots.txtを開き、以下のようにgptbotのクロールをブロックする記述がないか確認します。
User-agent: gptbot
Disallow: /念のため、サーバーログでgptbotのアクセス記録があるか確認してみましょう。(アクセス元IPやUser-Agentが「GPTBot」になっているもの)
▼ OpenAIのクローラーについては、以下の公式ページをご確認ください。
→https://platform.openai.com/docs/bots/
Google-Extendedのクロールを許可する 【★★★】
Google-Extendedとは、WebサイトのコンテンツをGoogleの生成AIに使わせるかどうかを制御する仕組みのことです。
Google-Extendedをrobots.txtで拒否している場合は、Geminiなどで自社のコンテンツが利用されなくなります。つまり、Google検索の上位には出るのに、AIが生成する回答の中には一切出てこないという状態になります。
robots.txtを開き、以下のようにGoogle-Extendedをブロックする記述がないか確認します。
User-agent: Google-Extended
Disallow: /なお、Google-Extendedを拒否しても、Google検索のインデックス登録や順位には影響しません。
クロールバジェットを最適化する 【★☆☆】
クロールバジェットとは、検索エンジンや生成AIが1つのサイトに対してクロールしてくれる上限のことです。
Googleが1つのWebサイトをクロールする回数には上限があるため、ページ数が多すぎたり、読み込みに時間がかかりすぎたりすると、全部のページを見てもらえなくなる可能性があります。
生成AIのクローラも同じように、通信エラーが多いWebサイトやレスポンスが遅いサイトは「途中でクロールするのをやめる」可能性があるため、重要なページをちゃんとクロールしてもらえるように整備しておくことが大切です。
Google Search Console の「クロールの統計情報」から「500エラー」が発生していないか、クロールの平均応答時間が長すぎないか確認する
CloudflareやWAF(セキュリティ)でAIをブロックしていないか確認
PageSpeed Insightsなどを使ってサイトの速度を確認する
【LLMO診断項目②】レンダリング
SSR(サーバーサイドレンダリング)を利用する【★★★】
JavaScript(JS)によって画面が後から作られる仕組み「クライアントサイドレンダリング(CSR)」だと、生成AI がコンテンツを読み取れないケースがあるため、注意が必要です。
一方で、サーバーサイドレンダリング(SSR)を使うと、最初からHTML内に本文が含まれているため、生成AIのクローラーにとって「読みやすいページ」になります。
そのため、AIによる引用数を増やすLLMOでは、サーバーサイドレンダリングの採用がベストプラクティスとなります。
ブラウザで対象ページを開き、右クリック →「ページのソースを表示」をクリック
表示されたHTML内に、<h1>や本文テキストが最初から記述されているか確認します。
もしHTML内が空で、JSの読み込みタグだけがあるようなら、それはCSR依存の構成です。
JS遅延読込(LCP後に非必須JSを読み込む)【★★☆】
必要のないJavaScriptを最初に読み込んでいるとページの表示が遅くなり、生成AIのクローラーがテキストを読み込めない可能性があります。
特にLCP(メインコンテンツや見出しなど)より先に非必須JSを読み込むと、表示が遅くなり読み込みが途中で終わってしまう恐れがあります。(※今はあまりないかもしれません)
そこで、すぐ使わないJSはdeferを使って後回しにして読み込むようにします。
ページを開いてF12 →「Performance」で記録し、LCP前後のJS読み込みを確認
重要でないJS(例:アクセス解析、チャットなど)が早く読み込まれていれば、遅延対象
HTML内の <script> タグを確認し、非必須なものは defer を追加
<script src="/example.js" defer></script>ハイドレーション失敗で本文が空になるページがないか【★☆☆】
ReactやVueなどJSフレームワークでは、サーバーサイトレンダリング後に「ハイドレーション」が上手くいかないと、本文が空白になることがあります。
ハイドレーションが失敗すると、ユーザーにもAIにも本文が表示されず、AIの参照に悪影響が出る可能性が高くなります。
ページを開き、F12でコンソールエラーを確認
※ hydrationやmismatchの文字があると注意「ページのソースを表示」でHTMLに本文があるか確認
表示されない場合は、ハイドレーション失敗の可能性大
静的要素なのに動的レンダリングをしている部分が原因になることも多く、AI対応やSEOのためには修正が必要です。
CLS(レイアウトシフトの抑制)【★☆☆】
CLS(Cumulative Layout Shift)は、Webページの表示中にレイアウトがどれだけ大きく変化したかを数値化した指標です。例えば、画像の読み込み時に本文の位置がずれるなどが該当します。
生成AIは、ページをレンダリングして本文を読み取る際、初期に表示されたテキストを優先的に取得する傾向があります。
そのため、CLSの値が高いページは、本文や見出しがAIに認識される前にずれたり非表示になったりして、コンテンツを正しく読み取られないリスクがあります。
PageSpeed InsightsやLighthouseでCLSスコアを確認(0.1未満が目標)
ページ表示時に、見出しや本文が動いていないか目視で確認
ページの表示速度【★★☆】
表示が遅いページは、ユーザーだけでなくAIにも読み込みエラーや離脱を招き、引用される可能性を低下させます。
生成AIもページを読み込むリソースには限りがあります。生成AIは、ページを「クロール → 読み込み → 要約→ 引用」という手順で処理するため、表示速度が遅くメインコンテンツを読み取る前にタイムアウトしてしまう場合は改善が必要です。
PageSpeed InsightsにURLを入力し、モバイルの表示速度が極端に遅くないか確認します。
表示速度に問題がある場合は「画像サイズを最適化する」「CSSとJavaScriptファイルを最小化する」「ブラウザキャッシュやCDNを活用する」といった方法を行います。
AIにも「早く読み取れるページ」が好まれる時代です。SEOと同じくLLMOでも、表示速度の最適化も重要です。
【LLMO診断③】構造化データ
記事の構造化データの追加【★★☆】
記事の構造化データ(Article schema)は、ページが「記事」であることを検索エンジンやAIに伝える構造化データです。ニュースやブログのページに記事の構造化データが入っていれば、Googleや生成AIがそのページを正しく理解できるため引用しやすくなります。
生成AIは、信頼できる構造化された情報を優先的に参照・引用します。
著者情報や作成日などの構造化データが正しく設定されていれば、AIはいつ誰が書いたのかを理解しやすくなるため、AI概要や引用元に選ばれる可能性が高まります。
構造化データテストツールでURLを確認します。
記事の構造化データが <head> 内に含まれているか確認します。
FAQ構造化データの追加【★★★】
FAQ構造化データ(FAQ schema)は、ページ内の質問と回答をAIや検索エンジンに伝える構造化データです。LLMOでFAQ構造化データが重要な理由は、生成AIが「質問とその答え」という形で情報を探し、引用することが多いためです。
構造化されたFAQがあると、AIはページ内の情報を正確に理解しやすくなり、AI overviewsや回答文で引用される可能性が高くなります。
GoogleリッチリザルトテストツールでURLまたはコードを入力し、FAQ構造化データが実装されているか確認
Googleサーチコンソールの「拡張」機能でFAQ構造化データが有効になっているか確認
HowTo構造化データの追加【★★☆】
HowTo構造化データは、「やり方」「手順」「方法」などを説明するページに使う構造化データです。HowTo構造化データを設定すると、検索エンジンや生成AIに対して「このページは手順を説明している」と示すことができます。
生成AIは、ユーザーの質問に「手順ベースで答える」ことが非常に多いため、HowTo構造化データがあると、AIは手順の区切りや順番を正しく理解でき、回答文としてそのまま引用される確率が高まります。
FAQ構造化データと同じように、Googleリッチリザルトテストツールで正しく実装できているか確認しましょう。
組織の構造化データの追加【★★☆】
組織(Organization)の構造化データは、企業や団体の基本情報(名前、ロゴ、所在地、連絡先など)を、検索エンジンやAIに正確に伝えるための構造化データです。
組織の構造化データを実装することで、生成AIが「このサイトはどの会社が運営しているのか」「どんな会社なのか」を認識しやすくなります。
生成AIは、間違った回答を生成しないように、情報の出どころ(発信元の信頼性)を重要視します。組織の構造化データがあると、AIがそのページの情報提供元を把握でき、信頼できる情報か判断しやすくなります。
▼ 組織の構造化データは、Googleの公式ページを参考に実装してみてください。
→https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization?hl=ja
プロフィールページの構造化データの追加【★★☆】
プロフィールぺージ(ProfilePage)の構造化データは、個人プロフィール(著者・専門家・代表者など)の紹介ページで使う構造化データです。
プロフィールぺージの構造化データを入れることで、GoogleやAIはコンテンツ作成者がどのような人物なのかを正確に理解できるようになります。
また、検索エンジンやAIがその著者をエンティティ(実在する人物)として認識し、その分野の専門家として評価している場合、信頼できる情報源として引用される可能性が高まります。
そのため、プロフィールページに構造化データを設定しておくことで、著者の専門性・実在性がエンティティとして明確に伝わり、LLMOにおいて効果的となります。
一次ソースを明示する【★☆☆】
記事内で他のサイトや文献を引用している場合、isBasedOn を使って、「この情報はどこに基づいているか」=一次ソースのURLを明示できます。
生成AIは、信頼性を重要視するため、情報の出典が明確なコンテンツを優先的に参照・引用する傾向があります。
isBasedOnを使って一次ソースであることを明示しておくと、AIは情報の根拠を認識しやすくなり、「引用元が明確な情報」として評価されやすくなります。
ページのソース内にisBasedOnという文字があるか検索
あれば引用元のURLが書かれていることを確認
【LLMO診断項目④】根拠・情報源
DOI / ISBN の記載【★☆☆】
DOI(論文の識別子)や ISBN(書籍の識別子)は、論文や書籍の出典を正確に特定できるIDです。引用するだけでなく、構造化データや<meta>タグで機械的に補完しておくと、AIが情報源を正しく認識しやすくなります。
生成AIは、信頼できる一次情報に基づく情報を重視すると言われています。DOIやISBNを明記しておくことで、出典が正式な情報源であるとAIが認識しやすくなり、引用される可能性が高くなります。
ページ内にDOIやISBNの記載があるか確認(例 DOI:10.1000/xyz123)
HTMLソースに <meta> タグで記述されているか確認
【例】
<meta name="citation_doi" content="10.1000/xyz123">
<meta name="citation_isbn" content="9784001156782">日時の記載【★☆☆】
データや統計値をページに載せるときは、「いつのデータか」を明記することが重要です。
例:※2024年3月時点の情報です。変更されている可能性があります。
いつのデータなのか日付が明記されていると、AIが「この数値は過去のもの」と正しく理解できるようになります。生成AIは、数値やデータをそのまま引用してユーザーに表示することが多いため、古い情報を「最新」と誤って扱うリスクがあります。
そのため、「○年○月時点」と書いておくことで、AIがいつの情報なのか判断しやすくなり引用間違いを防ぐことができます。
アップデート履歴の記載【★☆☆】
記事内に、「いつ・どこを・なにを更新したか」を箇条書きで記録するアップデート履歴を記載しておくと、AIが「更新履歴や最新情報か」判断しやすくなります。
生成AIは、情報の鮮度や更新履歴を元に、信頼性や引用価値を判断すると言われています。アップデート履歴があることで、「このページは継続的にメンテナンスされている」とAIが認識しやすくなり、引用対象としての信頼度が向上する可能性があります。
記事の最後に以下のような「更新履歴」があるか確認します。
【更新履歴】
・2024年6月:見出し2-2に最新の調査データを追加
・2023年12月:見出し1-3 ○○についてを追加
発リンク一次引用率【★☆☆】
記事内で使っている外部サイトへの発リンク(参考資料や出典)の半分以上が、「一次情報(公式統計・論文・政府資料など)」かどうかを確認します。
引用元が明記されている方がAIに引用されやすいですが、他サイトのまとめ記事や二次情報ばかりを参照している場合は、信頼性が高いとは言えないため注意が必要です。
AIが引用元として扱う際に出典元が信頼できる一次情報であることが、LLMOでの評価に直結します。
ページ内にある外部リンクを一覧で確認し、出典が以下のような一次情報にあたるかチェックします。「政府・自治体の公式サイト」「学術論文」「公的研究機関・業界団体の資料」「企業の公式発表や統計PDF」
全出典リンクのうち、50%以上が一次ソースならOKです。
【LLMO診断項目⑤】E-E-A-T
Knowledge Panel もしくはGBPの出現【★★★】
ナレッジパネルが出ている=そのブランドや人物がGoogleに公式エンティティとして認識されているという証拠であり、信頼できる発信元としてAIに引用されやすくなる可能性があります。
Knowledge Panel(ナレッジパネル)とは、Google検索でブランド名や企業名・人物名を調べたときに、検索結果の右側に表示される情報枠のことです。
例えば、「会社名」や「ブランド名」で検索したときに、 会社概要・ロゴ・SNSリンクなどが右側に表示されていれば、Googleがそのブランドや企業を「エンティティ」として認識している状態です。
Knowledge PanelはGoogleの仕組みになるため、AI Overviewsやgeminiで引用されるためには重要となります。
Wikipediaの掲載【★★★】
Wikipediaに掲載されるということは、その企業・人物・サービスが「公的に認知されている存在」であると見なされている状態です。Googleの検索品質評価ガイドラインには、Wikipediaに関する記載が何度も出てきており、信頼できる情報源と認識していることがわかります。
つまり、WikipediaはGoogleやAIにとって、「信頼できるエンティティ情報のデータソース」です。掲載されていることで、AI Overviewsやgeminiでの引用が増加する可能性があります。
Wikipedia内で「会社名」「サービス名」「代表者名」などを検索
該当ページが存在するかを確認
Wikipediaに掲載されることは、LLMOで「実在している存在だ」とAIに示す最強の証となります。
ブランド名や企業名の引用数【★★★】
自社のブランド名や企業名が、他のサイト・ニュース・ブログ・SNSなどで何度言及されているかを確認します。つまり、「外部サイトにどれだけ自社名やサービス名が掲載されているか」です。
また、 引用数が多いと、AIはその企業を「有名で信頼できる存在」と判断するため、情報源として優先的に引用する可能性が高くなります。
Google検索で"企業名"-site:自社ドメインを検索して、自社サイト以外での言及数を把握
例:"株式会社〇〇" -site:yourdomain.co.jp
競合サイトと比較して、どのくらい他サイトで言及されているか比較してみましょう。
自社名やブランド名を含むアンカーテキストの数【★★★】
アンカーテキストとは、リンクになっている青字の文言のことです。
詳しくはMEOアナリティクス公式サイトをご覧ください。
上記のように、自社名やブランド名がアンカーテキストになって多くのサイトに貼られていれば、生成AIは一般的に広く知られている企業名・ブランド名だと判断し、引用元として表示数が増加する可能性があります。
被リンク分析ツール(Ahrefs、SEMrush、Majesticなど)で、アンカーテキストに自社名・ブランド名が使われているリンク数を確認できます。
競合サイトと比較して、どのくらい被リンクのアンカーテキストに自社に関する名前が入っているか比較してみましょう。
指名検索の数【★★☆】
指名検索とは、「株式会社〇〇」「〇〇とは」「〇〇 評判」など、自社名やサービス名を直接検索されることを指します。指名検索が多いということは、ブランドが一般的に知れ渡っており認知度が高いと言えます。
生成AIは認知度が低いブランドよりも、高いブランドの方を優先して引用・参照する傾向があると言われているため、競合よりも多く指名検索されていることが大切です。
Google広告を出しているのであれば、Googleキーワードプランナーを使って月間検索ボリュームを調べることができます。
※ Google広告を出していない場合でも利用できますが、0-100などアバウトな数値が表示されます。
著者経歴の構造化データ【★☆☆】
生成AIは、引用する際に「誰が書いたか」「その著者に専門性があるか」を重要視している可能性があります。hasCredentialやaffiliationを使って、著者の専門性や実在性を構造的に示すことで、AIに「信頼できるエンティティ」として認識されやすくなるため、引用対象やAI概要の表示で有利になる可能性があります。
著者(Author)の構造化データには、以下のように資格や肩書、所属している団体の情報を追加できます。
- hasCredential
-
資格や専門分野(例:管理栄養士、SEO検定1級)
- affiliation
-
所属団体・会社(例:株式会社〇〇、日本内科学会)
権威性の高い受賞歴の記載【★☆☆】
企業や個人が何かの賞を受賞した場合、その情報が外部メディアで紹介されている記事と相互リンクしておくことで、「実績の裏付け」が外部からも確認できるようになります。
受賞歴を記載することで、企業のエンティティにその分野についての情報が加えられ、その分野での専門性や権威性が高くなります。
生成AIは、ハルシネーションを防ぐため、信頼性を重要視しています。そのため、自社が権威性が高く信頼できる情報源であることを示した方が引用される可能性が高くなります。
自社サイトに「受賞歴」や「プレスリリース」の記載があるか確認
その実績を紹介している外部メディア記事があるか探す(PR TIMESなど)
会社概要・Aboutページの作成【★★★】
生成AIから信頼され引用元として自社を表示させるには、誰が運営しているのかを明示する「会社概要・Aboutページ」の設置が必須です。
前述した通り、生成AIは、情報の発信元が信頼できる人物・組織かどうか(エンティティ)を重視しています。会社概要ページがあることで、その情報が「実在する法人・事業者による発信」であるとAIに認識されやすくなり、引用されやすくなります。
ただ単に、企業情報を入れるだけではなく、取得している資格や受賞歴なども合わせて記載するようにしましょう。
関連サイトからの被リンク【★★☆】
同じ業界や専門分野の信頼できるサイトからリンクされていると、AIはそのページや発信元を人気の情報源として認識しやすくなります。
被リンクとは、他のサイトから自社サイトへ向けて貼られたリンクのことです。自社と関連性の高いテーマや業界のサイトから被リンクを多く獲得することで、Googleの検索エンジンは信頼できるサイトと判断します。
SEOほどの影響力はないものの、生成AIも被リンクが多いページを引用元として選択する可能性があります。
Googleサーチコンソールから被リンクを確認
ahrefsなどのツールを使って確認
【LLMO診断項目⑥】コンテンツ
結論ファースト【★★★】
生成AIは、段落の最初の文を重視して要約や引用に使います。そのため、結論が冒頭に書かれているかどうかで、引用される可能性が変わります。
生成AIに引用されやすくするには、「結論→理由→補足」の順で書く「結論ファースト」が最も効果的と言われています。
各見出しの直後に、質問の回答となる結論が来ているかを確認
「~です。なぜなら~だからです。」の順で書かれているかをチェック
「結論が最後」になっている場合は、構成を逆にします。
結論ファーストで文章構成にすることで、生成AIに引用されるだけではなく、強調スニペットに引用される可能性も高くなるため、結論ファーストで文章を書く方法を身に付けておきましょう。
FAQ形式【★★★】
FAQ形式のコンテンツは、質問と回答が分かれているため、AIが情報を抽出しやすい形になっています。
例えば、次のような形でコンテンツを作成した場合、ユーザーの質問に対しての回答であるということがすぐに理解できます。
送料はかかりますか?
全国一律500円です。
生成AIは、ユーザーの質問に対して答えを返す構造のため、Q&A形式の文章の方が理解しやすく、回答をそのまま活用しやすいという特徴があります。
記事やLPに、「Q:〜?」「A:〜です。」のように明確なQ&A形式のブロックがあるかを確認
FAQ構造化データがマークアップされているかもセットでチェックすると◎
1見出し1メッセージの構成【★★☆】
h2やh3の見出しごとに、1つのテーマだけを解説すると、AIが内容を理解しやすくなるため引用されやすくなります。
一方で、1つの見出しの中に複数のテーマが入っていると、主旨が何なのかAIが判断しづらくなります。
例えば、「h2:SEO対策とアクセス解析の重要性」このような見出しの場合は、SEOとアクセス解析について2つのテーマを扱っているため、AI生成が何についてのコンテンツなのか迷ってしまいます。
各h2やh3の見出しを読んで、1つのトピックだけを扱っているかを確認
段落内で「ちなみに〜」や「一方〜」など、別の話題にずれていないかをチェック
見出しごとにトピックを明確にして、AIに「この段落は何について書かれているか」を把握しやすくするようにしましょう。
ページ冒頭にページ全体の要約があるか【★☆☆】
ページの最初に「この記事でわかること」など、要約を入れると生成AIに正しく要点が伝わり、引用や要約に選ばれる可能性が高くなります。
生成AIは、ユーザーの質問に対する回答が記載されているページをリアルタイムで検索する場合があります。その際、ページの冒頭で 要点が整理されていれば、AIは「このページは質問の回答に関する情報がある」と判断しやすくなり、回答や引用に優先して使われやすくなります。
ページの冒頭に、「この記事でわかること」や「要点まとめ」などの記載があるか
要点の下に、3~5個程度の箇条書きでページの内容を簡潔に整理して記載しているか
サイト全体のテーマを絞る【★★☆】
サイト全体で扱うテーマが統一されているほど、生成AIは「専門性が高く、その分野において信頼できるサイト」として認識しやすくなります。
例えば、「SEO対策」に関するページだけで構成されているサイトと、「SEO」「web広告」「オフライン広告」が混在しているサイトがあった場合、AIやGoogleは前者を「SEOの専門サイト」として認識します。
サイト全体で扱うテーマが統一されているサイトは、その分野における専門家と認識されやすく、AIの引用や要約の対象としてコンテンツが利用される可能性があります。
サイト内の記事が、ひとつの主要テーマに集中しているか確認
サイトのメインテーマとと関連が低いカテゴリやトピックがあれば、削除・統合・別ドメイン化などを検討
古くなった情報を書き換える【★★☆】
コンテンツの情報を定期的に最新の情報にアップデートしておくことで、生成AIに「最新の情報源」として認識され、引用される可能性が高くなります。
一方で、定期的に更新されて「更新日」も表示されているページは、ユーザーが「最新のSEO対策を教えて」と質問した際に、AIから引用される可能性が高くなります。
特に、以下のような分野では必ず最新の情報に更新するようにしましょう。
YMYL(医療・金融・法律など)に関する情報
自社サービスや自社商品に関する紹介:価格・内容・注意点など
技術に関する情報
【LLMO診断項目⑦】その他
AIが学習するプラットフォームへの参加【★☆☆】
Reddit・Quora・LinkedIn など、AIが参考にしていると思われる情報源に参加・発信しておくことで、生成AIに自社や著者が認識されやすくなります。
例えば、プラットフォームごとに以下のように利用します。
-
自社サービスに関するQ&Aに専門的に回答する
- Quora
-
専門分野の質問に丁寧な解説を投稿する
-
受賞歴・登壇・ホワイトペーパーなどを公開する
LLMO対策では、AIが情報収集を行う外部プラットフォームでの発信も、引用を増やすチャンスとなります。
ソーシャルシグナルの獲得【★☆☆】
ソーシャルシグナルとは、SNSでの「いいね」「シェア」「コメント」など、外部ユーザーからの反応のことです。
ソーシャルシグナルが増えたからと言って、AIに引用されるわけではありませんが、ブランドの認知度が高くなることで間接的な効果が期待できます。
各SNS内で社名・ブランド名を検索し、どれだけ言及されているか反応があるかをチェック
自サイト内にOGP設定、シェアボタンの設置などを行いシェアされやすいようにする
今後は、ソーシャルシグナルが強いコンテンツは、ユーザーにとって「有用」と判断されていると判断され、AIの引用率に影響を与える可能性があります。
カスタマージャーニーの段階に合わせたコンテンツ作成【★★★】
「認知 → 興味 → 比較検討 → 購入 → 継続」の各段階に対応したコンテンツを揃えることで、幅広いユーザーの質問に対して自社のコンテンツが引用される可能性が高くなります。
ユーザーは、商品やサービスを知ってすぐに購入するわけではありません。
次のように、段階を経て購入を決定します。
| 段階 | ユーザーの気持ち | 有効なコンテンツ例 |
|---|---|---|
| 認知 | 「こんな課題があるかも?」 | ○○とは?/入門ガイド/課題の背景解説 |
| 興味・関心 | 「もっと詳しく知りたい」 | メリット・デメリット/成功事例 |
| 比較・検討 | 「他と何が違うの?」 | 他社比較/価格・機能一覧/FAQ |
| 購入 | 「購入しようかな」 | 購入手順/購入までの流れ/口コミ |
| 継続・ファン化 | 「さらに便利に使いたい」 | 応用テクニック/活用事例/アップデート情報 |
LLMOは、AIの回答内で自社の引用数を増やすための施策です。各段階に対応したコンテンツを用意することで、引用数が増える可能性が高くなります。
また、自社の商品やサービスについて質問があった場合に、誤情報なく生成AIが回答を作成できるようになります。
リスト記事の作成【★★★】
「おすすめ○○選」や「おすすめランキング」といったリスト記事は、生成AIにとって引用しやすいため、LLMOで自社名についての引用を増やす上で重要です。
ユーザーが「おすすめの○○を教えて」とAIに質問をした場合、現時点ではリスト記事が引用元として多く表示されています。

そのため、自社内でリスト記事を作成したり、他社が作成しているリスト記事に、自社のサービスや商品を紹介してもらえるように営業するなど行うのが効果的です。
どのようなキーワードでAIにリスト記事がよく引用されているか確認します。
競合と比較して自社がリスト記事に掲載されている数を比較します。
BingWebマスターツールの登録【★☆☆】
Bing Webmaster Toolsに登録することで、Copilotでの露出や引用が増える可能性があります。
Bing Webmaster Toolsは、Google Search ConsoleのBing版ともいえる無料ツールで、登録してサイトマップを送信することでBing検索エンジンでインデックスされやすくなります。
生成AI Copilot は、Bing検索をベースに情報を集めていると言われており、Bingに適切にインデックスされていないと、そもそもCopilotのAIに自社のコンテンツを見つけてもらえない可能性があります。(Bing検索以外の情報源も参照している可能性があります。)
Bing Webmaster Tools にアクセスしてサイトを追加します。
サイトマップを送信して、クロール状況やインデックス状態をチェックします。
まとめ
LLMO(大規模言語モデル最適化)は、生成AI時代の検索対策として注目を集めている取り組みです。
本記事で紹介したLLMO診断チェックリストは、生成AIに自社の情報を「正しく・信頼できる形」で伝えるための基本項目を網羅したものです。
LLMO診断のポイントをまとめると、次の項目が大切です。
構造化データを活用し、AIがコンテンツの内容を理解しやすくすること
FAQ形式や結論ファーストなど、AIが理解・引用しやすい文章構造にすること
指名検索や被リンク、ソーシャルシグナルなど、外部からの評価も意識すること
情報の鮮度・正確性を保ち、信頼できる情報源として認識されるようにすること
ただし、記事の冒頭でも述べたようにLLMOはSEOの延長線上にある施策であるため、まずはユーザーが自社のサービスや商品を選ぶ上で必要となるコンテンツを用意するなど、Webサイトの基本を固めることが大切です。
なお、弊社のSEOサービスでは、LLMOを考慮した対策も含めて実施しています。検索エンジンと生成AIの両方から評価されるWebサイトを目指す方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
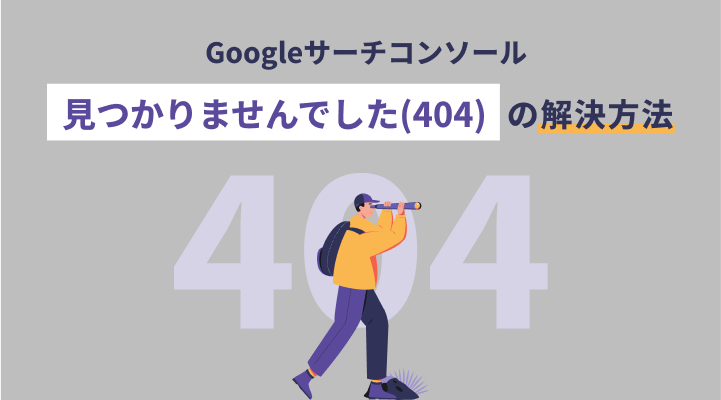 SEO対策「見つかりませんでした(404)」とは?サーチコンソールに表示された場合の解決方法を解説2025/10/03
SEO対策「見つかりませんでした(404)」とは?サーチコンソールに表示された場合の解決方法を解説2025/10/032025/10/03
-
 SEO対策クロールバジェットとは?定義と上限・最適化の方法を解説2025/10/03
SEO対策クロールバジェットとは?定義と上限・最適化の方法を解説2025/10/032025/10/03
-
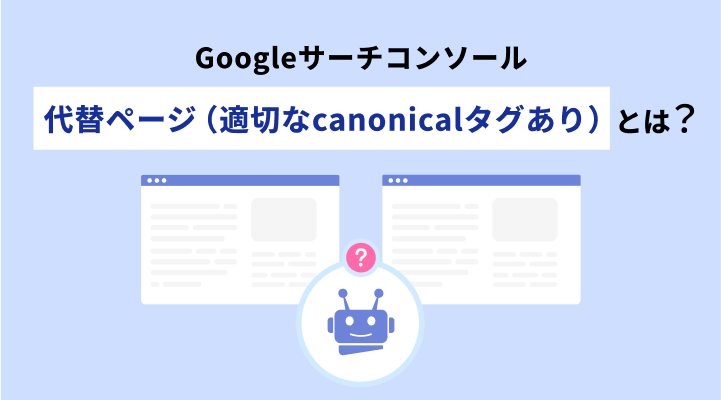 SEO対策「代替ページ(適切なcanonicalタグあり)」の意味と解決方法を解説2025/09/17
SEO対策「代替ページ(適切なcanonicalタグあり)」の意味と解決方法を解説2025/09/172025/09/17
-
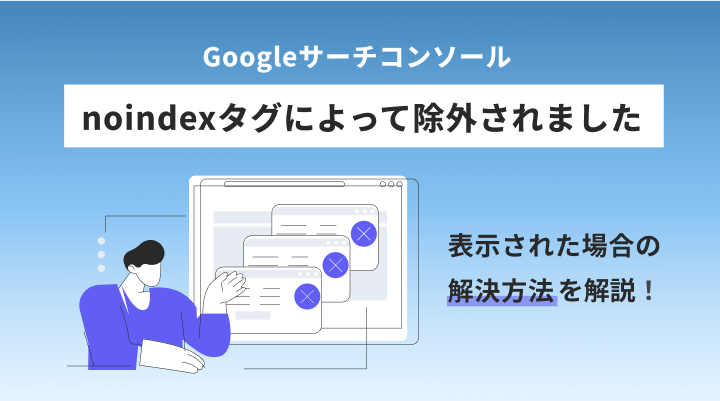 SEO対策「noindexタグによって除外されました」とは?解決方法について解説2025/09/12
SEO対策「noindexタグによって除外されました」とは?解決方法について解説2025/09/122025/09/12
-
 SEO対策SEOの勉強法|SEOコンサルがオススメする勉強方法と学ぶべき内容2025/09/12
SEO対策SEOの勉強法|SEOコンサルがオススメする勉強方法と学ぶべき内容2025/09/122025/09/12
-
 SEO対策強調スニペットとは?出し方やAIによる概要との違い・非表示にする方法を解説2025/09/09
SEO対策強調スニペットとは?出し方やAIによる概要との違い・非表示にする方法を解説2025/09/092025/09/09