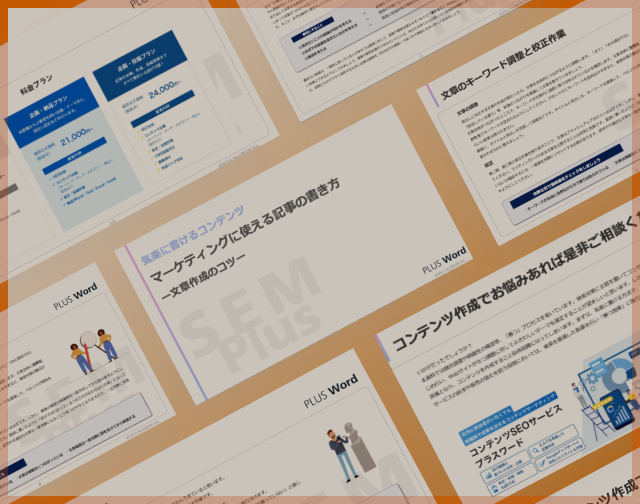Webライティングとは?手順やポイントを初心者向けに解説

Webライティングとは、Web媒体のコンテンツに文章を執筆する技術です。仕事としてWebライティングを行う場合は、新聞や書籍、雑誌に文章を書く場合との違いを意識して執筆する必要があります。この記事では、Webライティングとは何か、紙媒体・SEOライティングとの違い、やり方、注意点、勉強方法について解説します。
本記事では、Webライティングの基本から効果的な手法までを、初心者でも分かりやすく解説しています。
Webライティングの特徴や手順が明確になる
ユーザーにとって読みやすく、Webライティングの方法が分かる
SEOに効果的なWebライティングの方法が分かる
ぜひ本記事を参考に、Webライティングの知識を深め、Webサイトからの集客を強化しましょう。

Webライティングとは
Webライティングとは、パソコンやスマホなどのデバイスからインターネットを経由して表示されるブログやメディア、Webサイト内のコラムに掲載する文章を書くことです。
Webライティングでは、検索エンジンでキーワード検索したユーザーが知りたい情報を、分かりやすく正確に伝えることが求められます。ユーザーの疑問を解決するコンテンツは検索エンジンから評価され検索順位が向上するためです。
また、Web媒体のコンテンツによって誰が読むのか、どのようなデバイスで読まれるのか、ユーザーがどうやってWeb媒体にアプローチしたのかなどはさまざまです。Web媒体の特徴に合わせてライティングする必要があります。
インタビュー記事やSNS投稿文の作成も広義ではWebライティングになりますが、本記事ではSEOでの上位表示を目的としたWebライティングに限定して解説します。なお、Webライティングをおこなう人をWebライターと呼びます。
なお、Webライティングを使うコンテンツには、以下のような種類があります。
- Webメディアの記事
- ランディングページ(LP)
- ホームページ
- Web広告
Webライティングの特徴
Webライティングには、以下のような特徴があります。
- ユーザーと検索エンジン両方に評価される必要がある
- ユーザーの検索意図を考慮した内容を書く必要がある
- 検索結果からの流入を想定して書く必要がある
- 紙媒体と比べて文字数の制限がない
Webライティングの特徴を理解しましょう。
ユーザーと検索エンジン両方に評価される必要がある
Webライティングでは、ユーザーにとって価値の高い情報を提供しつつ、検索エンジンが求めるクオリティのコンテンツを提供する必要があります。
多くのユーザーにページを見てもらうためには、Google検索で上位に表示させて自然検索からの流入を増やすことが大切です。
検索エンジンに評価され上位表示させるためには、検索結果の分析が必要です。「こういう検索結果になっているから、こういう情報が必要」という考えに基づき、そのキーワードの検索結果でどんなコンテンツが求められているのかを勘案しましょう。
ユーザーからの評価を獲得するための考え方は、大きく分けて以下の2点です。
- 検索ニーズを満たす
- 使いやすさを提供する
Webライティングで向上させられるのは、主に検索ニーズの部分です。情報の分かりやすさ・伝わりやすさを意識して文章を作成しましょう。
ユーザーの検索意図を考慮した内容を書く必要がある
Googleはユーザーの検索意図を満たすページを評価するため、Webライティングでは、ユーザーの検索意図を考慮した内容を書く必要があります。
ユーザーの検索意図を満たすことで、検索順位の向上やコアファンの獲得につながるためです。
検索意図には、以下の種類があります。
- knowクエリ(知りたい)
- buyクエリ(買いたい)
- doクエリ(したい)
- goクエリ(行きたい)
これらを意識することで、検索意図を満たす良質なコンテンツの作成をおこなえます。
検索意図の捉え方については、『検索意図とは?考え方と種類について解説』を参考にしてください。
検索意図を意識すると、おのずとコンテンツの内容も変わってきます。ユーザーの検索意図を捉えて、効果的なWebライティングがおこなえるようにしましょう。
検索結果からの流入を想定して書く必要がある
Webライティングでは、検索結果からの流入を想定して書く必要があります。
SEOにおける流入の多くは、検索からのアクセスが大部分を占めています。そのため、検索をするユーザー視点に立ち、いかに記事を読んでもらうかを考えることが重要です。
ここで意識すべき考え方として、「3つのnot」という概念があります。
- 読まない
- 信じない
- 行動しない(※セールスライティングの領域なのでこの記事では触れません)
「3つのnot」は、本来コピーライティングの領域で提唱されている概念ですが、Webライティングにも応用できる考え方です。
検索をしたユーザーがページを見つけても、タイトルが魅力的でなければクリックされることはありません。さらにページを訪れたとしても、導入文の文章が稚拙だと感じさせてしまえばその時点で離脱されてしまいます。そのため、これらの壁を突破するためのライティングが重要なのです。
「読まない」「信じない」の壁を突破するためのポイントについては、後述する『Webライティングのポイント12選』で紹介します。
紙媒体と比べて文字数の制限がない
Webライティングは、紙媒体と異なり文字数の制限がありません。CMS(サイト管理システム)によっては文字数制限がある場合もありますが、自社メディアでのコンテンツ制作では、特に意識する必要はないでしょう。
ただし、文字数の制限がないからといって必要以上にボリュームの大きいコンテンツを作るのはおすすめできません。長文コンテンツはユーザーが欲しい情報を見つけられず、結果として体験を阻害する可能性もあります。
Webライティングの手順
Webライティングは、次の手順で進めるのがポイントです。
- 目的・ターゲットを明確にする
- リサーチをおこなう
- 記事構成を作成する
- タイトルの設定
- 執筆
- 推敲・校正をおこなう
各手順について詳しく解説します。
目的・ターゲットを明確にする
執筆する前に、記事を作成する目的やターゲットを明確にします。
趣味でブログを作るのであれば好きなことを書けば良いと思いますが、企業として記事を作るということは、商品・サービスの購入促進や自社の認知度の向上など何かしらの目的があるはずです。また、ページにアクセスしたユーザーは何かしらの疑問や悩みを解決するために情報収集をおこなっています。
そのため、WEBライティングでは記事を作る前に『解決したいユーザーの悩み』と『解決後にユーザーにとって欲しいアクション』を明確に決めておくことが重要です。
そうすることで、ユーザーにとって満足度の高い記事を作成し、自社の目的を達成するコンテンツを作成できます。一方、目的が曖昧なままだと、情報の取捨選択が難しくなり、最終的な文章の方向性がぶれてしまいます。
リサーチをおこなう
Webライティングの目的のひとつに、SEOでの上位表示が挙げられます。
そのため、執筆をおこなう前に競合サイトや1ページ目に表示される上位サイトに書かれている内容や見出し、全体の文字数などを調査し、どのようなコンテンツが検索エンジンから評価されているか事前にリサーチをおこないます。
例えば、上位サイトが共通して使っている見出しは、テーマに対してユーザーが求めている回答に近い内容の見出しの可能性があるため、自社の記事構成を作成する際に参考になります。
また、全体の文字数を把握することで、ユーザーの課題を解決するために必要な記事のボリューム感を執筆前に把握できます。
ただし、事前のリサーチはあくまで傾向を掴むためのものであり、上位サイトのマネをするためではありません。リサーチで大切なことはユーザーの検索意図を把握することと、上位サイトでは解決しきれていないユーザーの課題を見つけることです。
Googleのアルゴリズムは、検索意図にマッチする回答を提供する関連性の高いコンテンツや、独自性の高いコンテンツを評価しているため、ただ単に上位サイトと同じような内容の記事構成や内容をマネて作っても評価されず検索順位が上がりません。
Webライティングをおこなう際は、上位サイトよりも良いコンテンツを作成するために事前リサーチをしっかりとおこないましょう。
記事構成を作成する
リサーチが完了したら、記事の骨格となる記事構成を作成します。記事構成とはページの設計図のようなもので、執筆前に記事の内容やどのような順番で伝えるのか考えて見出しを作ります。
記事構成は、読み手がどのような流れで情報を得ると負担なく理解を深められるかをイメージして作成することが重要です。
前述した通り、ユーザーは疑問や悩みを解決するために検索をおこないページに流入しているため、顕在化されたニーズを解決する内容の見出しを上部に配置することでページの離脱を減らし、滞在時間を増やすことができます。
また、Webライティングで記事構成を作成する際は、h2(大見出し)、h3(中見出し)、h4(小見出し)などの見出しタグの使い方も大きなポイントです。
H2は記事における主要なトピックで使い、H3はH2で示したトピックの中にあるサブトピックや詳細項目を、さらに分かりやすくまとめるために利用します。
H4以降の階層は、H3よりもさらに深い説明が必要になった場合に使うのが一般的ですが、あまり見出しを細分化しすぎると読みづらくなるため、基本的にはh3、深くてもh4までで構成された記事構成にするのが一般的です。
なお、Googleの検索エンジンはページの内容を理解するのに見出しタグも参考にするため、見出しタグにはページのテーマを表すキーワードを入れるようにしましょう。
記事構成の作り方については別の記事で詳しく解説していますので、そちらも合わせてご確認ください。
タイトルの設定
記事構成が完成したら、ページのタイトルを作成します。ページタイトルは検索結果画面に表示されるため、ユーザーがクリックしたくなるような魅力的なタイトルを作成することで、検索結果画面上のCTRが高まりページへの流入を増やすことができます。
ページタイトルを作成する際の主なポイントは、次の3点です。
- ページの主題となるキーワードを含める
- なるべく30文字以内に納める
- 具体性や数字を入れて分かりやすくする
タイトルの中に主題となるキーワードを入れることで、ユーザーが検索結果画面でページタイトルを見た際に、ページの内容を理解しやすくなります。
例えば、被リンクについての記事を作成した際に次の2つのタイトルであれば、
①『被リンクとは?獲得するメリットやSEO効果・被リンクの増やし方について解説』
②『SEO対策は被リンクが大切です』
①の方が被リンクについてどのようなことが記載されているのがすぐに伝わります。
また、人間と同じようにGoogleの検索エンジンもページのテーマを理解する上でページタイトルを参考にします。Googleは検索キーワードと関連性が高いページを検索結果に表示させるため、キーワードを入れることで、関連性が高いページと判断され上位表示されやすくなります。
執筆
実際に記事を書き始める段階では、まずあらかじめ作成しておいた記事構成をもとに、見出しごとに内容を執筆していきます。
事前に調査した競合記事の内容や、社内のノウハウやデータを元にユーザーの疑問や悩みを解決するためのコンテンツを執筆しますが、Webライティングの場合は結論から先に書くことを意識して執筆する必要があります。
何故かと言うと、Web媒体に書かれた文章は無料で読める上に、複数のサイトが同じテーマを扱っていることが多いためです。分かりづらかったり読みづらければ、途中で読むことをやめてしまう可能性があります。
PREP法とは、物事を分かりやすく伝えるために用いられる文章構成の型です。文章を「結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→再度結論(Point)」という流れで組み立てることで、読み手が内容を理解しやすくなります。
PREP法は要点をつかんだ状態で本文を読み進めるため、途中の理由や具体例がより説得力を持つと同時に、最後に結論を繰り返すことで「結局何が言いたいのか」が明確に伝わりやすくなります。
SEOで成果を出すためには、コンテンツの独自性や専門性が必要になるため、PREP法で書いたからといって検索順位が上がる訳ではありませんが、最初は読みやすいコンテンツを意識してWebライティングに取り組みましょう。
推敲・校正をおこなう
文章が完成した段階でそのまま公開してしまうのではなく、まずは推敲と校正を丁寧におこない記事全体の品質を高めましょう。
推敲とは、作成した文章を見直して修正しながら更に良いコンテンツにすることです。文章の流れや構成、言葉の選び方などをチェックして、ユーザーにとって分かりやすく、伝えたい内容が的確に記載されているか確認します。
校正とは、誤字脱字や表記揺れ、文法の誤りをチェックして修正する作業のことです。誤字脱字が多い場合や、文法に誤りがあると検索エンジンが正しく文章を理解できなくなるため、SEOでマイナスとなります。
自分で書いた文章を自分で校正するのは意外と難しいため、最初は第三者に校正をおこなってもらうと見落としが少なくなります。
ここまでがWebライティングの手順となります。ひとつひとつの手順を丁寧におこなうことで、完成度の高いコンテンツを作成できるようになります。
Webライティングで意識する12のポイント
Webライティングでは、意識すべき12のポイントが存在します。
- 誰にでも分かる表現を心掛ける
- トンマナを統一する
- 箇条書き・表・画像を活用する
- 要点に装飾(太字・色文字)を入れる
- 一文一義を意識する
- 主語と述語を近づける
- 正しい接続詞を使用する
- 形容詞を使い過ぎない
- 漢字を使い過ぎない
- 指示語はできるだけ使用しない
- 冗長表現を避ける
- 適切に句読点を打つ
それぞれ詳しく解説します。
誰にでも分かる表現を心掛ける
Webページの目的は、ユーザーの疑問や悩みを解決することです。分かりづらい表現や専門用語を多様して難しい内容になってしまうと、ユーザーが理解できずに別のサイトを探してしまう可能性があります。
特に幅広いユーザーを対象にしている場合は、難しい漢字や聞きなれない表現、言い回しは避けるようにしましょう。また、専門用語を使う必要がある場合は、注釈を入れることでユーザーの理解を助けることができます。
自分では分かりやすいと思っていても、第三者が見ると分かりづらい可能性があります。記事を公開する前に想定読者に近い人に読んでもらい、分かりやすく読みやすい表現・文章になっているか確認しておきましょう。
トンマナを統一する
Webライティングでは、文章を書く媒体に合わせたトンマナを意識する必要があります。トンマナとは、トーン&マナーを略したもので、表現に一貫性を持たせるためのルールです。
例えば、文末表現は、「です・ます」と「だ・である」の2種類が混在しないようにしたり、次の用な表記揺れなどが起きないように注意します。
- 表記統一(例:〇 Webサイト ✕ ホームページ)
- 数値(例:〇 1,000円 ✕ 1000円)
- 漢字の開く閉じる(例:〇 わかる ✕ 分かる)
こうしたルールを明確に決め、Webライティングをおこなう執筆者全員が守ることで、文章全体のトーンが安定し、読み手にとって分かりやすいコンテンツになります。
箇条書き・表・画像を活用する
文章だけでは説明が難しい場合には、箇条書き・表・画像を積極的に活用しましょう。
数値やデータを比較する際は表にまとめることで、情報が整理され分かりやすくなります。また、専門的な内容や難しい内容でも画像を使って補足することで、文章だけで説明する場合よりもユーザーが理解しやすくなります。
表や画像を適度に使った読みやすいページはユーザーの印象に残りやすいため、覚えてもらい指名検索やブックマークにも繋がります。一方で、小説のように画面の大半が文字で埋め尽くされていると、どれだけ有益な内容だったとしても読み進める気力が低下する人がほとんどです。
箇条書きや表を文中に差し込むことでアクセントになり、最後まで読んでもらえるでしょう。
要点に装飾(太字・色文字)を入れる
要点に装飾(太字・色文字)を入れることで、流し読みをするユーザーにも伝えたいことを強調できます。
- 太字
-
サンプルテキスト
- 赤文字
-
サンプルテキスト
- 背景色
-
サンプルテキスト
- 下線
-
サンプルテキスト
太文字や色文字を入れる箇所は、ユーザーに読んでもらいたい箇所や、その見出しの中で重要な点です。 文字装飾を使い分けることで、視覚的なメリハリが出るため文書を読みやすくなります。
また、文字自体の装飾以外にも、文章の区切りの部分で改行を入れることで長い文章でも読みやすくできます。
ただし、装飾が多すぎると、読みづらくなったり、何を強調したいのか分かりにくくなったりします。装飾過剰にならないことを意識し、要点のみに絞って使用するとより効果的です。
一文一義を意識する
Webライティングでは、一文一義を守ることを意識します。
一文一義とは、「ひとつの文にひとつの情報だけを盛り込む」という考え方です。もし一文に複数の情報を詰め込んでしまうと、ユーザーにとって読みづらく、要点もつかみにくくなります。
以下の文章を例に見てみましょう。
「一文一義とはひとつの文章にひとつの情報を書くことであり、ひとつの文章に複数の情報を盛り込んでしまうと読みづらい文章になるため、一文一義の文章にすることで伝えたい情報を明確にすることが重要です。」
これは同じ内容を詰め込みすぎた結果、要点が分かりにくくなっています。
▼ 一文一義を意識すると次のような文章になります。
一文一義とは、ひとつの文章にひとつの情報を書くことです。
ひとつの文章に複数の情報を盛り込むと、読みづらい文章になってしまいます。
そのため一文一義で書くことで、伝えたい情報を明確にできます。
このように、一文を必要に応じて分割し、何を一番伝えたいのかを意識して執筆することで、文章は読み手にとって分かりやすく整理されたものになります。
Webライティングでは文章を長くすること自体が目的にならないようにし、「この一文でどんな情報を伝えたいのか」を意識して書くようにしましょう。
主語と述語を近づける
主語と述語が離れすぎると、文章が読みにくくなったり、理解しづらい文章になります。
たとえば、
「WEB媒体とは、企業が運営しているオウンドメディアやキュレーションサイト、個人が運営しているブログなど、インターネット上に存在する媒体です。」
という文は、一文で多くの情報を伝えようとした結果、主語の「WEB媒体」と述語の「媒体です」が遠くなっています。
このように主語と述語が隔たりすぎると、要点がぼやけてしまうため注意が必要です。一方で主語と述語を近づけて文章を作成すると、次のようになります。
「WEB媒体とは、インターネット上に存在する媒体です。代表的な例としては、企業が運営しているオウンドメディア、キュレーションサイト、個人が運営しているブログなどが挙げられます。」
いかがでしょうか?主語と述語を近づけつつ文を分割したことで、一文が短くまとまり、読み手にとって理解しやすい文章になります。Webライティングでは離脱をさせないために、読みやすい文書を作成する必要があります。
正しい接続詞を使用する
Webライティングに限らず文章を作成する際は、正しい接続詞を選び文章の繋がりを分かりやすく示す必要があります。
接続詞とは、文と文、あるいは文中の語句や節をつないで意味や流れを明確にする言葉です。
接続詞には、以下の6つの種類があります。
| 【順接】 | だから・すると・よって |
| 【逆説】 | しかし・けれども・ところが |
| 【並列・添加】 | そして・また・なお |
| 【対比・選択】 | または・それとも・あるいは |
| 【説明・補足】 | つまり・なぜなら・すなわち |
| 【転換】 | ところで・では・さて |
接続詞を間違って使った場合、以下のように意味が伝わりにくくなります。
- 誤
-
私は主婦です。しかし母でもあります。
- 正
-
私は主婦です。そして母でもあります。
- 誤
-
彼は試験勉強を頑張った。だから試験に落ちた。
- 正
-
彼は試験勉強を頑張った。けれども試験に落ちた。
たとえば「私は主婦です。しかし母でもあります。」という例は、一見自然に思えるかもしれませんが、逆説を表す「しかし」を使ってしまうことで、主婦であることと母であることが対立する関係にあるように伝わりかねません。
Webライティングではユーザーが短い時間で情報を読み取ろうとするため、適切な接続詞を使って文脈を分かりやすくつなぎ、ユーザーに誤解を与えないように心掛けることが大切です。
形容詞を使い過ぎない
形容詞を使い過ぎると、文章の印象がぼんやりしてしまい、具体的なイメージを伝えづらくなります。
例えば、「すごく効果がある」や「短い時間でできる」といった形容詞を多用すると、ユーザーが具体的なイメージを持ちづらくなります。
一方で「すごく効果がある」と書く代わりに、「〇〇を使ったところ、売上が20%伸びた」と数値化すると、読み手はどれだけの成果を得られるのかをイメージしやすくなります。
同じように「短い時間でできる作業」という表現を「5分で完了する作業」と書き換えれば、具体的なイメージが掴みやすくなるでしょう。
Webライティングでは、形容詞を数値化することで文章に説得力が増し、読み手に明確なメリットを伝えやすくなります。
漢字を使い過ぎない
Webライティングでは漢字を使い過ぎないようにするのがポイントです。Webコンテンツは専門的な内容や長文を扱う場合も多いため、漢字を使い過ぎると、文章が必要以上に硬い印象になったり、読む人によってはスムーズに理解できなくなったりします。
そのため副詞や接続詞、形式名詞、補助動詞などは、できるだけ漢字をひらがなに変えて書くまたはひらがなで書くように心掛けると、読みやすい文章になります。
「このツールを導入する上で大切な事があります。何故なら、例えトラブルが発生した時でも、すぐに対処するためには事前の準備が欠かせないからです。」
漢字を開いた例「このツールを導入するうえで大切なことがあります。なぜなら、たとえトラブルが発生したときでも、すぐに対処するためには事前の準備が欠かせないからです。」
上記のように、形式名詞や副詞・接続詞などをひらがなにすることで、文章全体がやわらかく読みやすい印象になります。
どこまで漢字を開くかは媒体やユーザー層によって異なりますが、Webライティングでは「読む人がスムーズに意味を理解できるか」を基準に判断しましょう。
指示語はできるだけ使用しない
不適切な指示語の使い方をすると、ユーザーに誤解を与える恐れがあるため注意が必要です。指示語とは、文中で使用した品詞の代わりに使用されるものです。同じ単語の繰り返しを避けるために使用されます。
代表的な指示語は、「これ」「それ」「あれ」「どれ」などです。こそあど言葉と呼ばれることもあります。
お店に並んでいた青いジャケットと赤いジャケットを試着した。
結局、そのジャケットを購入した。
上記の文章だと、「その」が指しているのは「青いジャケット」なのか「赤いジャケット」なのか分かりません。
指示語は直前の文章で使用された品詞に対して使用されますが、文章のなかに複数の品詞が書かれていると、指示語がどちらの品詞を指すのか分かりにくくなります。
指示語を使う必要があるのか、指示語を使うことで誤解を与えないかを意識して指示語を使いましょう。
冗長表現を避ける
Webライティングでは、無駄に同じことを繰り返したり、不必要に言葉を長くしたりする冗長表現を避けることが重要です。
冗長表現とは、不必要な語句が含まれた表現です。冗長表現を多用すると、無駄に文章が長くなり、意図が伝わりにくくなります。
Webライティングで見かけることが多い冗長表現は、以下の通りです。
- 誤
-
読みやすい文章を書くことができます。
- 正
-
読みやすい文章が書けます。
- 誤
-
重要な責任があることである。
- 正
-
重要な責任がある。
- 誤
-
努力すれば毎日運動できないわけではない
- 正
-
努力すれば毎日運動できる
- 誤
-
食事をしない人はいない
- 正
-
誰でも食事する
- 誤
-
ダイエットで重要なことは、ダイエットを途中でやめないことだ。
- 正
-
ダイエットで重要なことは、途中でやめないことだ。
上記例のように、余計な文を削ぎ落とし読みやすい文章を作成しましょう。
適切に句読点を打つ
適切に句読点を打つことで、文章の読みやすさが格段に上がります。句点と読点の違いは混同しやすいので、しっかり区別して覚えておきましょう。
- 句点:「。」
- 読点:「、」
まずは句点ですが、先述の通り一つの文章の意味が通じる部分に配置しましょう。長い文章の場合は、読点の部分に句点をおいて文章を一度切れないか考えてみるのもおすすめです。
読点を打つ場所は、主に以下の通りです。
- 主語や接続詞の後
- 音読したときに息継ぎをする場所
- 強調したい箇所の手前
- 係り受けの関係が明確になる場所
読点は、なんとなく打つものではありません。良い文章を仕上げるためには、句点の配置の上手さが鍵と言えるでしょう。
句読点の配置を意識して、文章の精度を上げていきましょう。
Webライティングの初心者が意識すべき7つのこと
Webライティングの初心者は次の7つのポイントを意識して執筆することで、ユーザーと検索エンジンから評価されるコンテンツを作成できます。
- 情報の鮮度と正確性に気を付ける
- 誤字や脱字をチェックする
- 結論ファーストを心掛ける
- 見出しを使って記事の内容を見やすくする
- 分かりやすくて論理的な構成にすること
- スマートフォンページの読みやすさを意識する
- 他サイトの文章をコピペしない
それぞれ詳しく解説します。
情報の鮮度と正確性に気を付ける
Webライティングでは、取り扱っている情報の鮮度と正確性に注意して執筆する必要があります。
書籍であれば、その時の最新情報を掲載すれば良いですが、Webページは簡単に更新できるため、ユーザーは最新かつ正確な情報が掲載されているという前提でぺージを閲覧します。
情報が古かったり、間違っている場合は、ユーザーは離脱して別のページを探してしまいます。そのため、記事を執筆する際は、インターネット上にある情報を鵜呑みにするのではなく、実際に自分で使ってみて正しい情報なのか判断した上で執筆するようにします。
特に、YMYLに該当する健康やお金といったユーザーの生活に関するテーマを扱う場合は、最新の注意が必要です。
最初はファストチェックや第三者に監修してもらい、正確な内容になっているかどうかしっかり確認しましょう。
誤字や脱字をチェックする
誤字や脱字をチェックすることは、Webライティングにおいて基本中の基本です。どんなに文章が優れていても、誤字脱字が多いとユーザーは読みにくく感じたり、メディアの信頼が低下します。また、誤字脱字は検索エンジンにも悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。
執筆が完了したら、投稿前には必ず見直しをおこない誤字脱字がないか確認します。案外自分が書いた文章の誤字脱字を見つけるのは大変なので、ツールを活用するのがおすすめです。
例えば、ChatGPTに執筆した文章を入力して「誤字脱字を見つけてください。」とプロンプトを入れると、すぐに誤字脱字と修正案を提示してくれます。
無料でできるうえに、時間も5分程度で誤字脱字チェックができるため是非試してみてください。
このように、ツールを利用することで、Webライティング初心者でも、誤字脱字を防ぐことができるので必ず誤字脱字がないようにしましょう。
結論ファーストを心掛ける
Webライティングでは、「結論ファースト」を心掛けることが重要です。
インターネットを閲覧しているユーザーは書籍を見ているユーザーと違い、すぐに別のページを見ることができます。結論がなかなか出てこない文章は、ユーザーがストレスを感じるため、内容を理解する前にページから離脱して、検索結果から競合他社のページに遷移してしまう原因になります。
そのため、記事の冒頭に結論を記載して、最初に要点を伝えることが大切です。また、ユーザーは自分が気になる見出ししか読まない傾向があるため、見出しごとに結論ファーストでコンテンツを作成します。
見出しを使って記事の内容を見やすくする
見出しを整理することも、Webライティングにおける重要な作業のひとつです。記事の内容を簡潔にまとめた見出しを作ることで、ユーザーが知りたい情報に辿りつきやすくなります。
見出し構成を作るときは、「MECEフレームワーク」を活用するのがおすすめです。以下の頭文字をとったものです。
- Mutually (お互いに)
- Exclusive(重複せず)
- Collectively(全体的に)
- Exhaustive(漏れがない)
簡単にいえば、「モレなくダブりなく」という考え方のことです。論理的思考の一環としておこなわれる思考法であり、Webライティングにも活用できます。
MECEを意識して見出しを作れば、整理された状態で情報をユーザーに届けられるでしょう。見出しを作るときは、ぜひMECEを意識してみてください。
分かりやすくて論理的な構成にすること
Webライティングでは、分かりやすくて論理的な構成にすることが重要です。論理的な文章を作成するなら、論理的思考(ロジカルシンキング)を活用するのがおすすめです。
本文の執筆で活用できる論理的思考のフレームワークには、以下の2種類があります。
- MECEフレームワーク
- ピラミッド構造
見出しの執筆ではMECEフレームワークの活用をおすすめしましたが、本文ではピラミッド構造が活用しやすいでしょう。
結論をピラミッドの頂点におくWebライティングでは、以下のような構造にすると分かりやすくなります。
● 結論
〇 理由
■ 理由①
■ 理由②
■ 理由③
〇 ポイント
■ ポイント①
■ ポイント②
■ ポイント③
〇 具体例
■ 具体例①
■ 具体例②
■ 具体例③
〇 関連するサービス
■ 関連するサービス①
■ 関連するサービス②
スマートフォンページの読みやすさを意識する
Webライティングでは、スマートフォンで読まれることを意識した構成や執筆が重要です。
デスクトップで執筆している場合、デスクトップでは読みやすくても、スマートフォンで閲覧すると読みづらいコンテンツになっている場合があります。
特に一文が長い場合や、装飾がないと文字が詰まって見づらくなる場合があるため、一文を短くしたり、強調したい箇所は適切にマーカーや太字を使い、必要最低限の情報を伝えることが大切です。
こうしたポイントを意識すれば、スマートフォン上でもスムーズに読み進められる文章になり、結果としてWebライティングのクオリティも向上します。
他サイトの文章をコピペしない
Webライティングでは、他サイトを参考に文章を書くことが多いですが、他のサイトに書かれた文章をそのままコピペしてはいけません。
他サイトの文章をコピペして自サイトに使った場合は、Googleからコピーコンテンツとして判断されるため、コンテンツとしての評価は0です。そのため、検索順位は上がらず最悪の場合はペナルティになる可能性があります。
そもそも、著作物を無断で使用することは違法です。他のサイトに書かれた文章を記事で使用する場合には、引用元を明記する必要があります。
また、そのままコピペで利用していなかったとしても、文章の一部だけを変えたり、言い回しを変えた場合も、Googleからコピーコンテンツと判断されます。
【中級者向け】SEOに効果的なWebライティングのポイント
中級者以上のWebライティングでは、SEOを意識して執筆しましょう。
SEOに効果的なWebライティングは、以下のポイントを意識しておこないます。
- 独自性を意識して執筆する
- 専門性を意識して執筆する
- 検索意図に沿った内容を書く
それぞれ詳しく解説します。
独自性を意識して執筆する
SEOで重視される要素が「独自性」です。オリジナリティのある情報を記事内に入れることで、独自性の高いコンテンツとして評価されやすくなります。
SEOで独自性が重視される理由は、より信頼性の高い検索結果を検索エンジン全体で作り出すためです。独自の研究や体験・経験から得られた情報は、一次情報として扱われます。ユーザーからすれば、何か知りたい情報があった時に、すでに実践した結果があれば有益な情報として役に立つでしょう。
Webライティングでは、このような独自性を担保する内容を入れると効果的です。ユニークな解釈や論理展開、他の記事に記載されていない新しい情報などを記載して、独自性を高めていきましょう。
専門性を意識して執筆する
SEOでは専門性の高さも重要な項目です。専門性とは、「そのジャンルに関してどれだけ深い知識を持っているか」という指標と考えておくと分かりやすいでしょう。
発信する内容をひとつに絞っておき、同ジャンルでたくさんの記事を出しているサイトは専門性が高いサイトと評価されやすくなります。
例えば「SEO」というジャンルで情報を発信していくのであれば、SEOの基礎的な知識やコアアップデートの最新情報、SEOで成果を出すためにおこなった施策の事例などのコンテンツを出していくことで専門性を高められます。
ただし、いくら専門性を出したいからといって専門用語を多用するのは避けましょう。あくまでも立ち位置としての専門性であり、コンテンツの内容は初心者が参考にしても分かりやすい状態に整えることが大切です。
検索意図に沿った内容を書く
Webライティングでは、検索意図に沿った内容を記載することが重要です。
検索意図を満たすためには、以下のポイントを意識しましょう。
- キーワードに対する回答を記事の冒頭や序盤に配置する
- キーワードに対する回答以外のニーズを満たす内容を記載する
- 一次情報や体験談を含めて独自性を高める
- 見出し構成を整理して分かりやすい内容にする
検索意図を掴むためには、5W1Hで深掘りしていくのがおすすめです。記事のペルソナを決めて、検索キーワードからどんなニーズを抱えているのかを読み解きます。
検索結果を深掘りしていくと、記事の中に反映すべき内容やどのようなライティングが効果的なのかが見えてくるでしょう。
執筆の際は、NeedsMetの概念を意識するのがおすすめです。Needs Metについては、Google検索品質評価ガイドラインを参考にすると分かりやすいでしょう。
Webライティングを上達させる方法
Webライティングを早く上達させるには、成功例や成功者から学ぶのが一番効果的です。
そこで次の2つの方法を実践します。
- 上位表示されているサイトを参考にする
- 書籍を読んで勉強する
上位表示されているサイトを参考にする
よく上位に表示されている競合サイトを参考にすることで、Webライティングを上達させることができます。
上位に表示されているWebサイトは、ユーザーからも検索エンジンからも評価されているページです。そのため、1位や2位のページの文章はどういった点が読みやすく、どのような書き方をしているのか注力して見てみましょう。
また、書き方だけではなく次の点も参考にします。
- 記事構成
- 記事の独自性
- 検索意図への回答方法
- 読みやすくするための工夫
上位に表示されているサイトは、業界歴の長いライターが執筆している事が多いため、さまざまな点で参考になる情報が多くあります。
自身が読みやすいと感じるサイトがあれば、どのような部分が読みやすいのかまとめて自身のライティングに活かせるようにしておきましょう。
書籍を読んで勉強する
Webライティングに関する書籍を読むことで、プロのWebライターが意識していることを学ぶことができます。書籍を通じて学ぶ最大のメリットは、体系的に学習できることです。
プロのWebライターが長年の経験をもとに書き下ろした内容は、文章構成やキーワード選定、ユーザーに伝わりやすい表現などWebライティングの基礎がまとめられているため、一通り読み進めれば自分のスキルを高めることができます。
書籍一冊あたりの価格はさほど高くないことが多いため、まずは一冊読んでみることをおすすめします。Webライティングを始めたばかりの方や、Webライティングの経験が全くない人は書籍を読んでスキルを高めましょう。
まとめ
Webライティングでは、Web媒体特有のルールに従って文章を書くことが重要です。また、ユーザー・検索エンジン双方からの評価を得るために、読みやすさだけではなく、独自性や専門性も考慮してライティングをおこなうのがポイントです。
最初は、うまく書けなかったり成果が上がらないことが多いと思いますが、本記事で解説したひとつひとつのポイントを抑えながらライティングを続けることで、良いコンテンツを作成できるようになります。
なお、社内にリソースがなくWebライティングを外注したい場合は、弊社まで気軽にお問い合せください。SEOの知見をもったプロのライターがコンテンツを作成いたします。
また、Webライターとして執筆に関する仕事をお探しの方は、気軽に弊社までご応募ください。

ぜひ、読んで欲しい記事
-
 コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/12
コンテンツSEOSEOリライトのやり方とは?効果を高めるコツを徹底解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/12
コンテンツSEO記事作成代行サービスおすすめ19選│相場やSEOに強い会社の選び方を解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/12
コンテンツSEOトピッククラスターとは│作り方・SEO効果とメリットを事例付きで解説2025/12/122025/12/12
-
 コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/09
コンテンツSEOコンテンツマーケティングとSEOの違いを徹底比較!7つの違いを解説2025/06/092025/06/09
-
 コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/09
コンテンツSEOAIライティングツールおすすめ15選│比較表付きで紹介2025/09/092025/09/09
-
 コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/30
コンテンツSEO検索意図とは?種類と調べ方・SEOで重要な理由を解説2025/10/302025/10/30