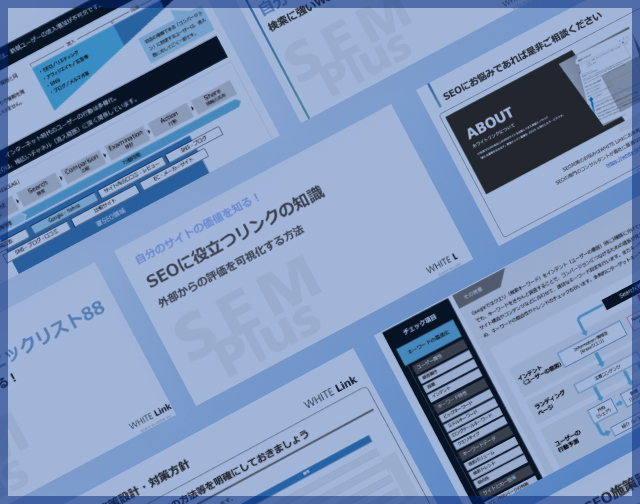【SEOイベント報告】SEOCON 2020

本記事は、2020/2/26,27にインドネシアのジャカルタで開催された「SEOCON 2020」のイベント参加レポートです。全部で14セッション構成のイベントで、マーケティングやSEOのプロであるプレゼンテーター達から様々な情報が発信されました。以下、全14セッションのアジェンダと会場の雰囲気をご紹介します。
SEOの考え方とビジネスの成長
【SEOCON 2020】1日目、第1セッションは「SEOの考え方とビジネスの成長」というテーマでTOFFEEDEVのRyan Kristo Muljono氏からプレゼンテーションがありました。
SEOフレームワーク

第1セッションでは、SEOCON 2020の主催者であるRyan Kristo Muljono氏から「SEOの考え方」についてプレゼンテーションがありました。
Ryan Kristo Muljono氏は「TOFFEEDEV」というWEBマーケティングのコンサルティングを行う会社を経営しており、自身で培ってきた経験も交えながらSEOのフレームワーク(SEOをどのように進めれば良いか)について解説していました。

▼ TOFFEEのSEOフレームワークでは、下記3つの段階に分けて考えるSEOの取り組みについて説明していました。
- サイト構築段階
- コンテンツ作成段階
- コンテンツ拡散・計測段階
「初めてSEOを行う人が、どのようにSEOを進行すれば良いか」を分かりやすくまとめていました。
第一段階ではサイト構造の確立などについて、第二段階ではコンテンツの作成やキーワード調査について述べていました。

第三段階では、コンテンツの拡散や計測が必要になってくること等について述べていました。
SEO対策のロードマップ

フレームワークの後は、SEO対策を進行する際のロードマップについても述べていました。シンプトム・ビジネスステータス・ストラテジー・ステップの4項目を挙げて、各項目ごとにSEO進行の流れをまとめていました。
SEOでのビジネス成長を実現させていくために必要なステップなので、「これから初めてSEOに取り組む人は、全体のロードマップを把握しておくことをおすすめします。」と強調していました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「SEOの考え方とビジネスの成長」ということで、SEOのフレームワークやフレームワークに沿ったSEOロードマップについて学ぶことができたセッションでした。初めてSEOを行う方にとって、SEOの骨格を知っておくことはとても重要なことなので、弊社でもしっかりとフレームワークの共有を行っていきたいと思いました。
ホリスティックSEO
【SEOCON 2020】1日目第2セッションは、「ホリスティックSEO」というテーマでTokopediaのReza Putra氏からプレゼンテーションがありました。
「Tokopedia」は、2009年に創業されたインドネシアのオンラインショッピングサイトです。企業などがオンラインストア開設などをすることができる巨大なプラットフォームで、多くの人々に利用されています。
ホリスティックSEOとは

Reza Putra氏のプレゼンテーションでは、ホリスティックSEOということで、現代のSEOの在り方について説明していました。
タイトルにあるホリスティックとは「全体像」という意味です。WEBサイトのランキング改善等を進めていくためには旧来のSEO対策ではなく、サイト全体を見たSEO対策が必要になっているとReza Putra氏は強調していました。

Reza Putra氏は、ホリスティックSEOを説明するにあたり、従来のSEOとホリスティックSEOの違いについて説明していました。
▼ 従来のSEO対策に関しては以下の特徴を述べていました。
- キーワードランクにフォーカスしている
- 検索ボリューム数の多いキーワードを狙っている
- 特定のランディングページにのみフォーカスしている

▼ ホリスティックSEOについては以下の特徴があると述べていました。
- 可能性のあるキーワードを狙う
- ランキングだけでなく、クロールや表示スピード全体を監査する
- Googleのアップデートなどにしっかりとアンテナを張る
ホリスティックSEOの重要性

Reza Putra氏は「旧来のSEO対策ではなく全体を見たSEO対策が必要になっている」と強調していました。
クロール・エラーページ・サーバーエラー・AMP・ストラクチャーデータなど様々な点からWEBサイトを管理・マネジメントしていかなければならなくなっています。

また、新しいアップデート等の情報を取得していくことの重要性についても触れており、Danny Sullivan氏のツイッターを引用し、「旧来の方法だけでのSEO対策を行わないようにしましょう」と述べていました。

最後にSEOに投資する価値についても触れており、お金・時間・サイトの成長にしっかりと投資を行い、SEOを成功させましょうと述べていました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「ホリスティックSEO」ということで、旧来のSEO対策ではなく、サイト全体をしっかりとマネジメントしていく「ホリスティックSEO」の重要性について学ぶことができたセッションでした。SEO対策は、昔よりも確実に複雑化しているので、しっかりと最新情報を確認していく必要があると感じました。
KumparanのSEO対策
【SEOCON 2020】1日目第3セッションは、「KumparanにおけるSEO」というテーマでKumparanのThomas Diong氏からプレゼンテーションがありました。

Kumparanとは、インドネシアで有名なニュースメディアのことです。
Thomas Diong氏は、「Kumparanに対してどのようにSEO対策を進めていったか」について説明していました。
以下、Kumparanで行ってきたSEO対策のまとめです。
コンテンツ作り

KumparanのSEO対策は大きく2点紹介されていました。
1点目は「コンテンツ作り」についてです。
ニュースメディアということもあり、コンテンツ作りにはかなり力をいれてきたようで、情報の正確性やスピード・更新頻度を徹底してきたようです。昨今、SEOではコンテンツが最も重要であると言われておりますが、Kumparanは徹底したコンテンツ作りに取り組んでいるようです。
キーワード調査の徹底

2点目は「キーワード調査の徹底」です。
Kumparanでは、キーワード調査やキーワード戦略にもかなり力を入れているようです。
▼ 具体的には、キーワードを以下の3つの種類に分類し、キーワード戦略を練っているようです。
- 自社で高ランクに位置しているキーワード
- 他社が高ランクに位置しているキーワード
- その他マーケットキーワード
競合サイトのランクインキーワードやマーケットキーワードなどをしっかりと把握することにより、SEO対策が必要なキーワードを探ることができ、対策を練りやすいと述べていました。

KumparanではSEO対策等の努力の結果、毎年アクセスを伸ばしているそうです。
SEOの計測について

Thomas Diong氏は、先程のキーワード調査と併せて、キーワードのランクイン状況等の計測について述べていました。
各キーワードのパフォーマンスをしっかりと把握することで、サイトの成長をしっかりと管理しているようです。

また、キーワード戦略のための競合サイト流入キーワード調査やソーシャルメディアのモニタリング・把握なども管理して行っているようです。

SEM Plus編集部からのコメント
今回は「KumparanのSEO対策」ということで、ニュースメディアのSEO対策について学ぶことができたセッションでした。徹底したコンテンツ作りとキーワード調査によって徐々にサイトを成長させていくことが大事であると、改めて感じたセッションでした。
Googleの現状と未来について
【SEOCON 2020】1日目第4セッションは、「Googleの現状と未来について」というテーマでYoast.comのJono Alderson氏からプレゼンテーションがありました。
「Yoast」はオランダにある会社で、SEOのプラグイン開発やSEO情報発信などをしています。特にワードプレスのプラグイン「Yoast SEO」は世界的に有名で、多くの人に利用されています。
プラットフォーム化するGoogle

Jono Alderson氏はGoogleが世界的な巨大プラットフォームとなりつつあると述べており、Googleの現状を説明していました。
現在、世界の消費者の70%以上もの人が、新製品やサービスの発見用にGoogleを使っているようで、とてつもない数の人たちがGoogleの検索エンジンを使っている状況となっています。

また、多くの人たちにリーチできるGoogle広告を使用する会社も増えており、今後も増えていくであろう述べていました。
検索エンジンの進化とゼロクリックサーチ

Jono Alderson氏は、検索エンジンがどんどん進化している現状とゼロクリックサーチについても述べていました。
検索エンジンが進化することによって、検索ユーザーはリッチ・エクスペリエンスをするできるようになり、様々なことをGoogleで行えるようになっていきます。
また、Google検索では、ゼロクリックサーチというものがあります。これは、検索結果の画面だけで調べたかった内容などを知ることができ、どのページもクリックすることなく検索を終えることを意味します。

このゼロクリックサーチは全検索の約半数近くであるらしく、Googleの検索結果が便利になるほど、ゼロクリックサーチは増えていくのではないかと言われています。
会話型AIと構造化データ

Jono Alderson氏は、会話型AIと構造化データについても触れていました。
Googleは現在、会話型AIの進化にもかなり力を入れており、今後間違いなく台頭してくるであろうと述べていました。
WEBサイトを取り巻く状況

最後に、Jono Alderson氏は、WEBサイトを取り巻く6つの構造について述べており、「WEBを取り巻いている全体的な構造」について理解しておくことの重要性について強調していました。
Googleを土台として考える現在においては、WEBサイトやSEOにとって重要であることを理解するために構造理解をするべきであると述べていました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「Googleの現状と未来について」ということで、検索エンジンやその周辺に関することについて学習できたセッションでした。これからのGoogleの進化をしっかりと追っていきながら、WEBサイトを取り巻く状況についてもしっかりと理解しておきたいと感じました。
クロールとインデックス
【SEOCON 2020】1日目第5セッションは、「クロールとインデックス」というテーマでTravelokaのJC Carlos氏からプレゼンテーションがありました。
「Traveloka(トラベロカ)」は、2012年にインドネシアの首都ジャカルタで設立されたオンライン旅行代理店です。
クロールとインデックスの仕組み

第5セッションは、「クロールとインデックス」ということで、JC Carlos氏からクロール・インデックスに関する様々な情報が発信されました。
セッション冒頭では、クロールとインデックスの仕組みについて説明していました。

▼ WEBサイトが検索結果に表示されるまでは以下の順で進んでいきます。
- WEBページがクロールされる(WEBページを発見するプロセス)
- WEBページがインデックスされる(発見されたページを登録・整理するプロセス)
- 検索結果に表示されるようになる
- ユーザーがページを閲覧する
※ GoogleはGooglebotと呼ばれるクローラーを持っており、このGooglebotが様々なページを発見しています。
クロールとインデックスで発生する問題点

JC Carlos氏は数千・数万のページを持つ巨大なサイトのマネジメントによくあるクロールとインデックスの問題点についても紹介していました。
【問題例】
- クロールバジェットの問題でクロールが進まない
- エラーページの存在などによるクロールエラー
これら以外にもいくつか紹介していましたが、今回は上記2つの問題の解決策が説明されていました。
クロールとインデックスの問題に対する解決策

- クロールバジェットの問題でクロールが進まない
これに対しては、「重複コンテンツを作らないようにすること」「価値のない非常に薄いコンテンツ(1・2行程度しか記載されていないページなど)を作成しないこと」「ページネーションコンテンツのカノニカル設定をすること」「テストページをインデックスさせないこと」などの解決策を挙げていました。 - エラーページの存在などによるクロールエラー
これに対しては、「カノニカルタグ設定の見直し」「XMLサイトマップの見直し」「リダイレクト設定の見直し」「no indexタグ設定の見直し」などの解決策を挙げていました。
クロールマネジメントに関するアドバイス

セッション終盤では、クロールマネジメントに関するアドバイスということで、大型サイト運営者に対してのアドバイスをしていました。
大きなサイトを運営している人はクロールの問題などに直面することが多く、サイトの管理が大変なことが多いため、クロールに関する問題点はしっかりとチェックし、対策を行っていくことを強く勧めていました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「クロールとインデックス」ということで、大きなサイトで起きうるクロール上での問題点やその解決策について学ぶことができたセッションでした。大型サイトを運営していく際はしっかりとクロールのチェックを徹底することが重要であると感じました。
SEOとビジネスについて
【SEOCON 2020】1日目第6セッションは、「SEOとビジネス」というテーマでClickMedia Pte LtdのFabian Lim氏からプレゼンテーションがありました。
ClickMediaはシンガポールに拠点を持つデジタルマーケティングエージェンシーで、WEBマーケティングに関するコンサルティングなどを行っています。
SEOとマネタイゼーション

Fabian Lim氏は、「SEOとマネタイゼーション」というテーマで、SEOのスキルを使って行えるビジネスについて紹介していました。SEOのエージェントとして他社のSEO対策を行うのも良いですが、SEOのスキルを使ってビジネスを展開することもおすすめしていました。
以下、SEOスキルを使って展開できるビジネスとして紹介されていたものを5つまとめました。
アフィリエイトマーケティング

1つ目のビジネスは、「アフィリエイトマーケティング」でした。
アフィリエイトとは、WEBサイトを使って商品やサービスの紹介を行い、そのサイト経由で購買が発生すると、そのWEBサイトの運営主に何%か報酬が入る仕組みのビジネスです。
SEOスキルを持っている人なら検索エンジンからWEBサイトへアクセスを集めたり、WEB上で集客することができるため、おすすめのビジネスの1つとして紹介されていました。
ローカルビジネスエージェンシー

2つ目のビジネスは「ローカルビジネスエージェンシー」です。
ローカルビジネスのWEB上での集客代理店を行うビジネスです。
Fabian Lim氏は、このビジネスの例として、地域のケータリング・スクール・イベント等のWEBサイトを立ち上げ、そこで集客代理などを行うことを紹介していました。
O2Oプロダクトマーケティング

3つ目は「O2Oプロダクトマーケティング」です。
O2Oは「Online to Offline」の略で、オンライン(ネット上)でサービス紹介等を行い、オフラインでの販売等に結び付けることを指します。
こちらもSEOスキルを持っている人なら検索エンジンからWEBサイトへアクセスを集めたり、WEB上で集客することができるため、おすすめのビジネスの1つとして紹介されていました。
バーチャルリアルエステート

4つ目は「バーチャルリアルエステート」です。
これは、WEBサイトを上位表示させてそのサイトを賃貸のように貸し出すというビジネスです。集客などが見込めるキーワードで上位表示を獲得し、そのサイトをレンタルとして貸し出すことで利益を出すモデルです。
Eコマースパートナーシップ

5つ目は「Eコマースパートナーシップ」です。
これは「ブランド力はあるが、WEBからの集客が全くできていない会社」に対し、改修やSEO対策を行いWEB集客・販促をできるようにするというものです。
SEOの観点からWEBサイトの改修を進め、WEBからの売り上げを増やすことがポイントとなるビジネスです。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「SEOとビジネスについて」ということで、SEOスキルを使ったビジネスについて学ぶことができたセッションでした。SEOのスキルは様々なものに応用が利き、いろいろなビジネスモデルがあると感じました。
WEBマーケティングのスキルハック
【SEOCON 2020】1日目第7セッションは、「WEBマーケティングのスキルハック」というテーマでCrazy Egg、kissmetricsのNeil Patel氏からプレゼンテーションがありました。
Neil Patel氏は「WEBマーケティングの界隈で知らない人はいない」と言われている程の有名人です。
デジタルマーケティングに関する幅広い情報を発信しており、様々なマーケティング活動を展開しています。今回は、アメリカからの中継セミナーということで、直接お会いすることができず残念でしたが、中継で様々な情報を発信してくれていました。
以下、紹介されていたものをいくつかピックアップしてまとめています。
サイトの更新について

1つ目は「サイトの更新について」です。
「しっかりとコンテンツを更新することはWEBマーケティングにおいて重要なことである」とNeil Patel氏は述べており、WEBサイトのみではなく、SNSやYoutube等のコンテンツもしっかりと更新することが大切であると強調していました。
ユーザーは様々な媒体やチャンネルから情報にアクセスしてくるので、全体をしっかりと網羅・更新していくことを勧めていました。
カスタマーとの交流・チャット

WEB上でカスタマーが手軽に質問できるチャット機能などをWEBサイトにつけておくと良いとカスタマーとNeil Patel氏は述べていました。手軽にチャットできることで、問い合わせ率の増加を見込むことができ、WEB集客などでの効果が期待できるようです。
クイズを設置する

商品・商材ジャンルにもよりますが、WEBサイトにクイズを設置することも有効な手段の一つのようです。
人はゲーム好きであるため、WEBサイト内にクイズやゲームを入れることによってより長い時間サイトに滞在したり、再度サイトに来たりなど、サイトのコンテンツとして楽しんでもらうことができます。
あまりやっているサイトがないらしく、有効なコンテンツとして勧めていました。
カウントダウンタイマー

カウントダウンタイマーで購買を促進することも効果的な手法の一つです。
WEB上でセール期間とそのセールが終わるまでの時間が表示されていれば、即決して購入してくれることもあるようです。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「WEBマーケティングのスキルハック」ということで、Neil Patel氏が実践・提案しているスキルハックについて学ぶことができました。WEBマーケティングには様々な手法がありますので、弊社でもいろいろな手法に挑戦していきたいと感じました。
キーワードカニバリゼーション
【SEOCON 2020】1日目第8セッションは、「キーワードカニバリゼーション」というテーマでPi DatametricsのJon Earnshaw氏からプレゼンテーションがありました。
「Pi Datametrics」はSEO・デジタルマーケティングに関するサポート・コンサルティング等を行っている会社です。イギリスに本社があり、東南アジア(バンコクやシンガポール)などにも支社があります。
カニバリゼーションとは

1日目の最終セッションは、Pi DatametricsのJon Earnshaw氏からプレゼンテーションがあり、コンテンツの重複やカニバリゼーションについて説明していました。
カニバリゼーションとは「共食い」という意味で、WEBマーケティングやSEOの分野では、ドメイン内の複数のページ間でキーワードが競合してしまい、Googleからの評価が各ページに分散してしまっている状態のことを指します。
カニバリゼーションはページ数の多いサイトで発生することが多く、過去作成したコンテンツと似通った内容のコンテンツができると、「Googleがどのページを検索結果として載せるにふさわしいか分からなくなる状態」となり、上位表示されにくくなります。
カニバリゼーションが発生する原因

▼ カニバリゼーションが発生する原因はいくつかありますが、以下のような場合に起きやすいようです。
- ページのタイトルがサイト内の他のページのものと似ている
- ページのコンテンツ構成がサイト内の他のページのものと似ている
ページが増えていくにつれて、このようなことが原因で気がつかないうちにサイト内で競合してしまっているケースが多いようです。競合した結果、ランクインしていたものが急に下がったり、ランクインしていたURLが別のURLと頻繁に入れ替わったりするなどの状態になるようです。

Jon Earnshaw氏はiphoneの新機種紹介ニュースのページなどを例に実際にカニバリゼーションが発生して、順位が下降していったデータなどを説明していました。

また、巨大なECサイトなどで、商品紹介のページがいくつもありカニバリゼーションが発生している例なども紹介していました。その他スポーツブランドを扱うサイトの例なども紹介されており、カニバリゼーションによる弊害を何個か知ることができました。
カニバリゼーションを回避する方法

▼ 最後に、カニバリゼーションを回避する方法についていくつか説明していました。
- タイトルやコンテンツ構成を変更する
- ページを合体させて一つのコンテンツにする
- 301リダイレクトの設定を行い、対策メインとなるページにリダイレクトさせる
順位が下降した時はカニバリゼーションが原因で下降していることもあるので、サイト内で競合しているものがないかチェックを行い、もしカニバリゼーションが発生していたら上記のような方法で解決することをすすめていました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「キーワードカニバリゼーション」ということで、サイト内のページ間で発生するカニバリゼーションについて学ぶことができたセッションでした。ページ数が多くなるとカニバリゼーションが発生することが多いようなので、似通ったページの発生がおきないように気を付けなければならないと感じました。
SEOとストーリーテリング
【SEOCON 2020】2日目第1セッションは、「SEOとストーリーテリング」というテーマでStory InstituteのIndhran Indhraseghar氏からプレゼンテーションがありました。
Indhran氏は「ストーリー×マーケティング」をテーマに、ストーリーを使ったマーケティング支援などを行っており、ストーリーが持つパワーについて情報発信をしています。
ストーリーテリングの重要性

ストーリーテリングとは、「伝えたいもの」や「購入してほしいもの」などがある時などに、それについての体験談・エピソード・背景を物語として紹介することで、聞き手・買い手に対して強く印象付けることです。
コンテンツマーケティングが流行りはじめてから、多くの企業や団体がコンテンツ作りに注力するようになりました。
ストーリーテリングの手法は、このコンテンツマーケティングおいて有効な手法の一つであると言われており、「ストーリーを伝える魅力的なコンテンツ作りが益々注目されています。」とIndhran Indhraseghar氏は述べていました。

ストーリーテリングの重要性は、各界の著名人からも言及されているようで、いくつか引用で紹介されていました。
The most powerful person in the world is the storyteller.
- Steve Jobs -
Marketing is no longer about the stuff you make but about the stories you tell.
- Seth Godin -

SEOを考えるにおいても、ストーリーテリングの重要性は益々上がっています。
多くの企業などが似通ったコンテンツを作り、検索エンジン上からの問い合わせや集客に励んでいますが、今後はそこに「ストーリー」があることがより重要となっていきます。
商品やサービスの背景にある物語やエピソードを公開し、それに対して共感が集めていくことで、SEOで成功していく可能性がかなり上がるとIndhran Indhraseghar氏は強調していました。
アテンションエコノミー

現在、私たちは「アテンション・エコノミー」の時代に生きていると言われています。
アテンション・エコノミーとは、情報過多のこの時代において、人々の注目を集めることが重要とされ、人々の関心や注目度の度合いが経済的価値を持つようになるという概念です。

ストーリーテリングは、このアテンション・エコノミーにおいて有効な手法の一つです。
「人々から関心を集め、その関心を継続的に受けることができれば、そこにお金の流れなどが発生してくる」とIndhran Indhraseghar氏は述べていました。
また、アテンション・エコノミーにおいては「信頼」が最も重要な要素とされています。
Indhran Indhraseghar氏は、「関心を引くと同時に、しっかりと信頼を得ることができればストーリーテリングは成功と言えるでしょう」とも述べていました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「ストーリーテリングとSEO」ということで、コンテンツマーケティングにおけるストーリーテリングの重要性について学ぶことができたセッションでした。アテンション・エコノミーにおけるストーリーテリングの手法については、今後も情報を追っていきたいと思います。
EコマースとSEO
【SEOCON 2020】2日目第2セッションは、「EコマースとSEO」というテーマでPi DatametricsのChris Lorimer氏からプレゼンテーションがありました。
「Pi Datametrics」はSEO・デジタルマーケティングに関するサポート・コンサルティング等を行っている会社です。イギリスに本社があり、東南アジア(バンコクやシンガポール)などにも支社があります。
▼ セッション冒頭では、以下のSEO知識習得に役立つWEBサイトをいくつか紹介していました。
どれも有名で有益なサイトなので目を通しておくことをおすすめしていました。
SEOの順序・考え方について

Chris Lorimer氏は、最初に、SEOの戦略を立てていくことについて述べていました。
具体的には、
- 「業界やマーケットのリサーチ作業」
- 「SEO対策のプランニング」
- 「SEO対策の実行」
- 「SEO対策の評価」
の4つの順でSEOを進めていくという話でした。

リサーチでは、各業界やマーケットの調査をする中で、カテゴリーやサブカテゴリーに該当するものの仕分け・整理などの必要性について述べていました。
プランニングでは、月間・年間のコンテンツ発信予定表作りを行うなど、順序良くSEO対策を進行していくための考え方について説明していました。
キャッチコピーと内部リンクについて

セッション中盤では、キャッチコピーと内部リンクの重要性について説明していました。
しっかりとキャッチコピー(タイトルや説明文など)を付けることでシェアされやすくなったり、内部リンクをきちんと設定していくことでSEO的に有利になったりするため、結果として、トラフィックが増加するというものでした。
しっかりとコピーを考え、内部リンクを設置していくことは基本的なことですが、これをきちんとしているかしていないかで大きく差が生まれるのでしっかりと行っていきましょうと述べていました。
カニバリゼーションについて

セッション終盤では「カニバリゼーション」について説明していました。
初日のJon Earnshaw氏のカニバリゼーションに関するプレゼンテーションでも述べられていたように、似通ったコンテンツの作成には十分気を付けてくださいと強調していました。
ECサイトはカニバリゼーションが発生しやすい例としてよく挙げられており、特に大きなサイトになるとカニバリゼーションが発生して順位が不安定になることが多いそうです。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「EコマースとSEO」というテーマで、SEOを進行していく上で必要となる考え方について学ぶことができたセッションでした。基本的なSEOの注意点に加え、カニバリゼーションについての注意もありましたので、ECサイトのSEOを行う際にはしっかりと監査していく必要があると思いました。
SEOの戦略とその流れ

第3セッションでは、「SEOの進め方」ということで、SEOを行っていくプロセスについて説明していました。
▼ 具体的には、下記のステップでSEOの進め方について説明していました。
- 競合調査
- オーガニックトラフィックの分析
- キーワードとトピックの分析
- コンテンツ作り
- 被リンク戦略
- SEOのモニタリング
以下、各ステップの内容をまとめていきます。
競合調査

1つ目の競合調査では、同じマーケットで展開している競合サイトの調査を行います。
「競合サイトはどれくらいあるのか」「どのようにトラフィックを集めているのか」「一番SEOで成功している競合サイトはどこか」など、競合サイトのやり方なども含め、ざっくりでも良いので把握しておくことをおすすめしていました。
オーガニックトラフィックの分析

2つ目に「オーガニックトラフィックの分析」について説明していました。
WEBサイトのどのカテゴリー・ページがどのような言葉でどれくらいトラフィックを集めているのか、又は集める可能性があるのかを分析しておくことはSEOの成功において必要なことなので、しっかりと調査しておきましょうと述べていました。
次の、キーワード・トピック分析と併せてやっておくことをおすすめしていました。
キーワードとトピックの分析

3つ目は「キーワードとトピックの分析」ということで、主にキーワードの選定について説明していました。
競合調査やオーガニックトラフィックの分析等で見つけたキーワードを整理して、各キーワード・トピックに対するページの構築を進めていくことについて述べていました。
SEOでは、この「キーワード」というのがかなり重要になってきます。しっかりと調査して整理しておくことをおすすめしていました。
コンテンツ作り

4つ目はコンテンツ作成についてです。
キーワードが決まったら、コンテンツを構築していきます。コンテンツを構築していくフェーズでは、キーワードに則して、「ユーザーにとって有益で信頼を得るに値するコンテンツ作り」が重要となってきます。
しっかりとしたコンテンツ構成を考えていきましょうと述べていました。
被リンク戦略

5つ目は「被リンク戦略」についてです。
コンテンツができたら、そのページに対してリンクがあるとSEO的に有効であることが多いです。しっかりと内部リンクを張り巡らせることや、外部サイトでのリンク掲載ができる機会(ガイドライン違反の場合を除き)があれば、しっかりと利用して被リンク対策を進めていくことをおすすめしていました。
SEOのモニタリング

6つ目は「SEOのモニタリング」についてです。
1~5までのSEO対策を進めたら、実際に検索結果でしっかりと順位をとれているかを確認したり、サイトへのアクセス増加に伴い、コンバージョンに影響が出ているかなどの確認をしたりして、しっかりとSEOのモニタリングをしていきます。
モニタリングをするこで効果検証することができ、SEOの施策を見直すきっかけになります。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「SEOの進め方」ということで、具体的なSEO進行のステップについて学ぶことができたセッションでした。これからSEO対策に取り組んでいく方にとって、かなり参考になる内容だと思いました。
クローラーの処理
【SEOCON 2020】2日目第4セッションは、「クローラーの処理」というテーマでTokopediaのM Rizqi Riandra氏からプレゼンテーションがありました。
「Tokopedia」は、2009年に創業されたインドネシアのオンラインショッピングサイトです。企業などがオンラインストア開設などをすることができる巨大なプラットフォームで、多くの人々に利用されています。
クロールに関する理解

セッション冒頭では「クローラーに関する理解」ということで、クローラーに関する理解の重要性について説明していました。クロールは、インデックスなどの前段階に行われることで、一番大元の始まりのステップです。
クロールされなければ、SEOなどの施策が成り立たたなくなるので、しっかりと理解しておくことを勧めていました。
クロールに関するチェックリスト

クロールを妨げている原因はいくつかあり、M Rizqi Riandra氏はいくつかチェックリストの例を挙げていました。
【クロールを妨げていないかのチェックリスト例】
- robot.txt.の見直し
- レンダリングについての見直し
- Botsのログの確認
- サーバーの確認
もし、クロールされていないことがあれば、これらの項目をチェックすることをおすすめしていました。
クロール周辺の知識

また、クロール周辺の知識としてクロールバジェットやエラーページについても説明していました。
ページ数が多いサイトによくあるようなのですが、クロールバジェットやエラーページがあることが原因でクロールされないこともあり、サイト運営者は注意した方が良いと述べていました。
コンテンツが生まれる場所

セッション終盤では、「コンテンツ・イズ・キング」についてこう述べていました。
「コンテンツは間違いなくキングだが、テクニカルな部分というのは、このキングが生まれる場所である。したがって、クロールをはじめとするテクニカルな部分を理解することは、コンテンツを支える上で非常に重要なものである。」
SEOの界隈ではコンテンツ・中身の話に考えがいきがちだが、しっかりとテクニカルな部分も理解しておくことの重要性を強調していました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「クローラーの処理」ということで、クローラーに関する様々なことを学べるセッションでした。特に、クロールをはじめとするテクニカルな部分の重要性を強調していたことが印象的でした。
コンテンツとリンクビルディング
【SEOCON 2020】2日目第5セッションは、「コンテンツとリンクビルディング」というテーマでiPrice GroupのAndrew Prasatya氏からプレゼンテーションがありました。
「iPrice Group」とは、東南アジアにおける各Eコマースプラットフォーム上の商品価格などをまとめて比較することができるサービスを展開している会社で、マレーシアに本部があります。
コンテンツの作り方

Andrew Prasatya氏のセッションでは、SEOにおいて最も重要な「コンテンツ」と「リンクビルディング」に焦点を当てて、それぞれのポイントを解説していました。
コンテンツ面に関しては、コンテンツの考案方法とそれを形に落とす方法について説明していました。

▼ コンテンツを考案していく上では以下のいずれかの要素がコンテンツにあることが重要であるとAndrew Prasatya氏は述べていました。
- 誰でも分かるような、簡潔でわかりやすいものにすること
- 他の人が知りえないような、新しい情報やオリジナルなものを入れること
- 具体的なものを見せること(例や表・グラフなどで具体性を持たせること)
- 信頼されるものにすること(思い込みやデータや根拠に基づかない主張を入れないこと)
- 感情に訴えかけること
コンテンツを考案していく際には、やみくもに作成するのではなく、しっかりと上記のような要素を入れるようにしておきましょうと強調していました。

コンテンツを作成していくときには、極力データ(数字)を入れておくことが重要とも述べていました。
数字があることで、読者が具体的に想像しやすくなったり、信頼されうるコンテンツになることが多いため、データをコンテンツにいれておくことを勧めていました。
リンクビルディング

リンクビルディングに関しては、自発的にコンテンツ拡散の動きをとっていくことについて説明していました。
何か紹介してくれそうなWEBメディアやブログ・SNS等があれば積極的にコンタクトをとり、コンテンツの拡散依頼をしていくことによって、徐々にリンクが増え、サイトへの流入を増やすことができます。

また、依頼する際は、それぞれ依頼先にあった独自のメールを作成し、しっかりと分かりやすいメールを考える等の注意点についても説明していました。
特に、他人にコンタクト・依頼する際のマナーをしっかり守ることを強調していました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「コンテンツとリンクビルディング」ということで、信頼されるコンテンツの構築とその拡散方法について学ぶことができたセッションでした。コンテンツの在り方やリンクビルディングの方法は様々あるかと思いますので、弊社では引き続き周辺情報を追っていきたいと思います。
ページスピード
【SEOCON 2020】2日目第6セッションは、「ページスピード」というテーマでYoast.comのJono Alderson氏からプレゼンテーションがありました。
「Yoast」はオランダにある会社で、SEOのプラグイン開発やSEO情報発信などをしています。特にワードプレスのプラグイン「Yoast SEO」は世界的に有名で、多くの人に利用されています。
ページスピードの重要性

2日目の最終セッションでは、「ページスピード」についてYoast.comのJono Alderson氏から説明がありました。
セッション冒頭では、ページスピードの重要性について解説していました。
- 48%の人々が2秒以内にページが表示されてほしいと思っている
- ページ表示開始に3秒以上かかると50%のユーザーが離脱する
- Cartのプロセスが遅い場合、20%ものユーザーが離脱する
上記のように具体的な数字を交えて、ページスピードを速めた方が良い理由を述べていました。

ページスピードの改善をする際には、サイトのページの構成がどのようになっているかを把握し、「各箇所において改善できる箇所を整理すると良いです」と述べていました。
ページ表示の速度改善は、ページ内のコンテンツのパーツごとにそれぞれ改善できるので、一度見直してみることを勧めていました。
ページスピードの改善

▼ ページ速度改善をする際に、大きな括りで取り組むことができるのが下記3つの点です。
- サーバー
現在使用しているサーバーの改善を行うことで、ページの表示速度が上がるケースは多いです。 - CMS・プラグイン
ワードプレスを使用している方は、無駄なプラグインが入っている場合は削除することを勧めていました。 - HTML/CSS
HTMLやCSSの最適化を行うことで、速度アップができることもあります。
この3点も、一度見直しておくことを勧めていました。

その他にも、キャッシュの利用やAMPなど、ページ速度を速める方法がいくつか紹介されていました。
最後に、「ページスピードの改善ができる箇所・できることはサイトによって必ずあるので、全体的にサイトの見直しを進めてみてください」と述べていました。
SEM Plus編集部からのコメント
今回は「ページスピード」というテーマで、ページの表示スピード改善方法について学ぶことができたセッションでした。ユーザー目線で見た際に、ページの表示速度はとても重要なポイントの一つになりますので、今後多くのWEBサイトが改善していく部分であると思いました。
ぜひ、読んで欲しい記事
 SEO対策LLMO診断・無料でできるチェックリスト40項目【2025最新版】2025/07/04
SEO対策LLMO診断・無料でできるチェックリスト40項目【2025最新版】2025/07/042025/07/04
 SEO対策「検出-インデックス未登録」がサーチコンソールに表示される原因と解決策2025/07/01
SEO対策「検出-インデックス未登録」がサーチコンソールに表示される原因と解決策2025/07/012025/07/01
 SEO対策llms.txtとは?書き方やLLMOでの効果について解説2025/07/04
SEO対策llms.txtとは?書き方やLLMOでの効果について解説2025/07/042025/07/04
 SEO対策サイトリニューアルがSEOに与える影響│順位下落防止のポイントを解説2025/06/24
SEO対策サイトリニューアルがSEOに与える影響│順位下落防止のポイントを解説2025/06/242025/06/24
 SEO対策LLMO対策代行会社おすすめ9選|LLMOコンサルティング外注業者の選び方を解説2025/07/04
SEO対策LLMO対策代行会社おすすめ9選|LLMOコンサルティング外注業者の選び方を解説2025/07/042025/07/04
 SEO対策403(Forbidden)エラーの意味とは?発生する原因と解決方法を解説2025/06/13
SEO対策403(Forbidden)エラーの意味とは?発生する原因と解決方法を解説2025/06/132025/06/13