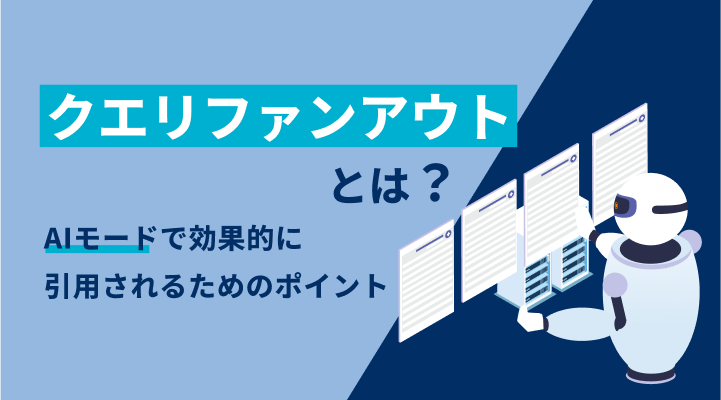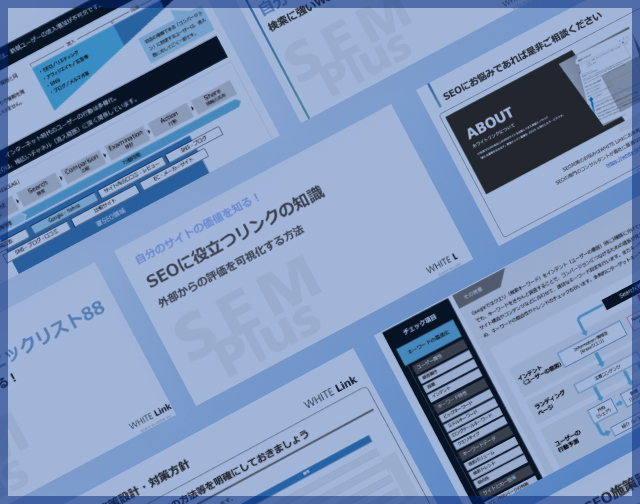生成AIが台頭する今、SEO担当者に求められる新スキル~戦略立案からLLMOまで徹底解説

これからの時代のSEOには、生成AIを活用した高度な分析や施策が欠かせません。今回は生成AI×SEOをテーマにした書籍『AI時代のSEO戦略』の著者、シンクムーブ株式会社代表取締役・豊藏氏に、今後のSEO担当者に求められる新たなスキルを解説してもらいました。事業会社や支援会社のSEO担当者にとって必見の内容です。
検索エンジンやSEOの世界は、ChatGPTやGemini、Claudeといった生成AI普及によって大きく変化しつつあります。従来ならユーザーがキーワードを入力して検索結果を眺め、そこから複数のサイトを訪れて情報を比較検討する流れが一般的でした。
しかし今では、AIがユーザーの質問や要望を理解してくれるため、「そもそも検索エンジンにアクセスする必要がなくなるのではないか」と懸念する声も聞こえてきます。
とりわけSEO担当者やWebマーケターにとって「AIに仕事を奪われるのでは?」「どんなスキルを身につければ今後も通用するのか?」という不安が募るのも無理はありません。
しかし、生成AIの台頭は脅威であると同時に、業務の効率化や新たな戦略立案のチャンスをもたらす側面も見逃せません。
本記事では、生成AI時代に求められるSEO担当者の新スキルや戦略について、実務的かつ具体的に解説していきます。「これからどうしたらいいのか?」という疑問に応えながら、AI活用時代でも第一線で活躍できるヒントを提示します。ぜひ最後までお読みいただき、今後の行動に役立ててください。
執筆:シンクムーブ株式会社 代表取締役 豊藏翔太
生成AIの登場でSEOはどう変わる? – AIがもたらす検索環境の変化と課題
生成AIはユーザーの質問に対し、高度な言語モデルを用いて即座に回答を提供します。
Googleが提供を始めた新機能「AI Overview」によって、ユーザーは検索キーワードを入力すると即時に要約された情報にアクセスできるようになりました。


上記の回答を元に、ChatGPTやGeminiを利用することで、より深いレベルで質問を重ねながらユーザーが必要な回答を得ることも可能です。
これらの新たな検索体験は、ユーザーが検索結果をクリックして個々のウェブサイトを訪問する回数を減らす要因となり、いわゆる“ゼロクリック検索”が増加する傾向を加速させています。
AIがユーザーに直接回答を完結させてしまうことにより、オウンドメディアやブログへの訪問が極端に減る恐れがあり、SEOを中心としたオウンドメディア運営をしていた企業が不安を感じるのも無理はありません。
こうした理由から、従来のSEO戦略だけでは十分に流入を確保できない局面へと近づいています。
生成AIで自動化・効率化できるSEO業務 – AIに任せられる領域と活用法
このパートでは、AI×SEO×ファシリテーションを強みとしている私が、AIを用いて取り組める業務について解説していきます。
コンテンツ制作の効率化
生成AIはキーワードやトピックを入力するだけで、記事の構成案や下書きを瞬時に提案してくれます。
たとえば「タイトル案を出して」「見出し構成を提案して」といったプロンプト(AIへの指示文)を投げかければ、数十秒で複数パターンのアウトラインを受け取ることが可能です。
ChatGPTを活用して書いた文章をリライトしたり、キャッチフレーズを生成させたりすることで、執筆にかかる時間を大幅に短縮できる点が大きなメリットといえます。
たとえば商品紹介記事を作る場合にChatGPTに
ターゲット層は○○、用途は△△、どのような悩みを解決するかペルソナを具現化して
などの条件を与えて下書きを作成させ、人間が最終的に校正・加筆するフローです。
担当者はAIライティングツールの挙動を学びながら、時間と労力の最適化を狙うことができるでしょう。
キーワード調査・分析の自動化
キーワードリサーチや関連語句のブレインストーミングにも生成AIは有用です。
従来の手法では、キーワードプランナーなどのツールを使って関連キーワードを抽出し、さらに競合サイトのメタタグや本文を読み込みながら「どのような検索意図が存在するのか」を分析するプロセスが必要でした。
AIを活用すると、ある程度の指示を与えるだけで類義語や関連キーワードを大量に生成したり、競合ページの要点をまとめたうえで「見落としている検索ニーズ」を提案してくれたりします。
たとえばChatGPTに
キーワードXを中心に、関連するロングテールキーワードやユーザーが抱えそうな疑問点をリストアップして
と尋ねれば、多くのアイデアが一度に得られます。
その後、人間の目でそれらを取捨選択し、ニーズがありそうなキーワードを優先的にコンテンツ化していく流れです。
競合サイトのURLを入力して
このサイトの強みと弱みを短く要約し、隙間となるニーズを提案して
といった指示をAIに行うこともできます。
AIはアイデアの拡散や収束どちらも優れている為、たたき台づくりはAIに任せ、人間がブラッシュアップすることでさまざまな取り組みが可能となります。
その他定型業務の効率化
メタデータ(タイトルタグやディスクリプション)の下書き作成や構造化データ(JSON-LDなど)の生成支援、あるいはアクセスログレポートの要約といった、定型業務にも生成AIは有効です。
SEO担当者の日常業務を振り返ると、サイト全体のメタタグを整備するときに同じようなパターンで文章を書くケースは少なくありません。
また、ログ分析レポートの冒頭まとめや表記ゆれの修正など、繰り返し作業を伴うタスクが多いのも実情です。
AIを活用すると、まずテンプレートとなる指示やフォーマットを与えておき、具体的なサイト情報や数値を入力するだけで、それなりに形の整った下書きを一括生成できます。特に多言語サイトの場合、AIが翻訳からメタ情報の作成までを一気に提案してくれるので、大幅に時間とコストを節約できるでしょう。
ただし、現状のAIはあくまで「人間のチェック」が必須です。
鵜呑みにせず必ず事実関係を確認し、表現にミスがないかを最終チェックすることが重要になります。AIの力で大量の草案を用意し、それを人間が精査・修正して完成度を高めるのが理想的な活用方法といえます。
AIでは代替できないSEO領域:人間にしか担えない役割 – 戦略立案・ファシリテーションなど「人」にしかできない仕事
ここまで、AIに任せるべき業務についてお話をしてきましたが、その中でも引き続き人間が取り組むべきものはなんでしょうか。ここでは、2025年3月30日時点の現状を元に、考察を進めていきます。
戦略立案とクリエイティビティ
AIは過去のデータや公開情報をもとに、統計的・論理的な処理を行う点で非常に優れています。しかし、ビジネス目標やブランド戦略、企業としての優先順位など、高度な文脈理解とクリエイティビティを要する決定は人間の役割が不可欠と考えています。
どの市場を狙うのか
どんなターゲットに向けてどのようなコンセプトで商品を訴求するのか
何をKPIとして追うのか
これらは企業ごとに異なる文脈や経験・洞察が必要となり、AIだけに任せられるものではありません。
AIによる分析結果はあくまで「既存データからの推測」であると強調されており、人間が新たな企画や戦略を生み出すための補助線”として位置づけることが望ましいです。
競合が想定していない切り口や、まったく新しいコンテンツの着想などは、人間特有の柔軟な発想力がなければ難しい領域です。

実際の事例でも「思い切った打ち手を考えられるかどうか」で大きな差がつくため、AI時代でもクリエイティブな思考力はより重視されるでしょう。
ファシリテーションとコミュニケーション
SEO担当者の仕事は「分析をする、記事を作るだけ」ではありません。
社内のコンテンツ担当やデザイナー、外部のライター、クライアント企業の担当者など、多岐にわたるステークホルダーとの調整や意見交換が日常的に行われます。
たとえば、SEO方針を社内の制作チームに共有し、ライティングの方向性を理解してもらいながらフィードバックを行う段階では、単に情報を伝えるだけでなく、相手がどのように受け止めているのかを把握し、適切なサポートを提供するコミュニケーション力が欠かせません。
AIにできるのは文章生成や情報の要約であり、「人間関係の構築」や「現状や状況を認知する」「利害関係をマネジメントする」などの機微を伴う行為は苦手です。
特にファシリテーションには人間の共感や説得力が重要で、これらは今後もAIでは代替が困難だと考えられています。
SEO担当者がプロジェクト全体を俯瞰し、利害関係者をスムーズに巻き込みながら結果を出すためにも、こうしたソフトスキルが一層求められるでしょう。
品質管理とE-E-A-Tの担保
AIが生成するコンテンツには、事実誤認や文脈の曖昧さなどが含まれる可能性があります。そのため人間による品質チェックと専門性の付与が不可欠です。
Googleの検索品質評価ガイドラインでも重視される「E-E-A-T(Experience,Expertise,Authoritativeness,Trustworthiness)」を十分に満たすためには、たとえば以下のような人間の作業が必要になります。
- 事実確認
-
AIが提示したデータや論拠に誤りがないか、別の信頼できるソースを使って検証する。
- 専門知識の付与
-
自分や社内の専門家の実体験や知見を記事に加筆し、単なる一般論にとどまらない深みを与える。
- 権威ある情報源へのリンク
-
信頼度の高い論文や公的機関へのリンクを適切に挿入し、情報の正確性と権威を補強する。
特にプロンプトスキル(言語化能力)は、生成AI時代のSEO担当者にとって全ての基本となるため、日々自身の言語化能力を高める事は大きな価値になりそうです。
こうしたプロセスを経る事で、検索エンジンやユーザーからも信頼度の高い評価を得られるのです。AIが生成した下書きに対し、人間がどれだけ“リアルな経験と専門性”を肉付けできるかが勝負の分かれ目になるといえるでしょう。
ユーザーファーストの視点
最後に、いくらAIが高度な生成能力を持っていても、それがユーザーの“本当の悩み”を解決し、理想をかなえるストーリーを描けるかは別問題です。
AIは与えられた指示に従って文章を組み立てることは得意ですが、ユーザーのリアルな感情や本質的な課題を深掘りし、最適解を示すには人間の洞察や共感が不可欠だからです。
例えば、SEO記事の企画段階では「表面的なキーワードに応えるだけでなく、ユーザーが抱えている潜在的なニーズを拾えているか?」を見極める必要があります。
そして実際に記事を公開した後も、読者からの反応やSNSでのコメントをもとに内容を改善していくといった柔軟性こそが強いコンテンツを生み出します。
ユーザー視点での最終判断や、想定外のシチュエーションに応じた臨機応変な対応は、人間にしか担えない重要な役割といえるでしょう。
生成AI時代に求められる新しいSEOスキルセット – AIと共存するために身につけたい能力
これまで「AIが得意な領域」と「人間にしかできない領域」を区別して見てきました。では、そのうえでSEO担当者は今後、どのようなスキルを身につければよいのでしょうか?
以下に代表的な新スキルをリストアップし、ポイントをまとめます。
| スキル | 概要 | 具体的な活用例 |
|---|---|---|
| プロンプトスキル (言語化能力) | AIに質の高い出力をさせるための“指示文作成力”を磨く。 適切なキーワードや文脈、制限条件を与えることで、欲しい情報を正確に引き出す。 | 「○○なトーンで、見出し案を5つ出して」と詳細に指示し、記事構成の自動提案を得る。 |
| データ分析と AIリテラシー | AIが集めてきたログや生成結果を読み解き、改善に活かす力。 また、AIの仕組みや限界を理解して誤情報を見抜く“AIリテラシー”も重要。 | AIの提案するキーワードリストを検証し、競合調査やアクセスログと照合して最適化へつなげる。 |
| 編集力・校正力 | AIのドラフトをベースに、読みやすく正確で説得力のある文章に仕上げる力。 一貫性の確保や誤情報の修正、専門用語の正確な解説の追加などが含まれる。 | ChatGPTが生成したリード文を、事実確認・語調の調整・事例の肉付けなどで磨き上げ、最終原稿とする。 |
| 戦略思考と コンサルティング力 | 経営視点でSEO施策を企画し、全体最適を図る力。 AIに任せる領域と人間が担う領域を切り分け、提案書やプロジェクトを推進するコンサルティング力も含まれる。 | 社内外のリソース状況やビジネス目標を踏まえ、「このフェーズはAIを使い、ここは人が手厚く対応する」といったプランを組み立てる。 |
| 継続的学習と適応力 | AIや検索アルゴリズムは常に進化しているため、新機能や新動向を追いかけ続ける姿勢。 変化に柔軟に対応し、業務プロセスをアップデートできる能力。 | 海外のSEOブログやGoogle検索セントラル公式情報を定期的にチェックし、AIのアップデートにも迅速に対応する。 |
上記のスキルセットを意識することで、AIを単なる「道具」として使うだけでなく、自らの専門性と組み合わせてより大きな成果を生み出すことが可能になります。

特にプロンプトスキル(言語化能力)は、生成AI時代のSEO担当者にとって全ての基本となるため、日々自身の言語化能力を高める事は大きな価値になりそうです。
「LLMO」の理解と重要性 – Large Language Model Optimizationとは何か
生成AIとSEOが交わる最先端のトピックとして注目されているのが、LLMO(Large Language Model Optimization) という概念です。従来のSEOは「Googleの検索アルゴリズムに合わせてサイトを最適化し、検索結果で上位を獲得する」ことを目的としていました。
ところが、AI Overviewや生成AIが普及するにつれ、ユーザーは検索エンジンのリンクをクリックせずともChatGPTやGeminiの回答だけで満足するケースが増えています。
そこで、ChatGPTの回答内容に自社サイトの情報を取り込んでもらう仕組みや、信用度を高める施策が必要になるというのがLLMOの考え方です。
具体的には以下のような取り組みが挙げられます。
- LLMs.txtの導入
-
AI向けのサイトマップのように、自社サイトの重要ページやデータを大規模言語モデルに読み込ませやすくするための仕組み。
- 引用しやすいコンテンツ構造
-
事実や統計データを明確に整理し、AIが文章を生成するときに引用しやすい形にしておく。特に箇条書きや表形式での整理が有効。
- ブランド名や固有名詞の訴求
-
ChatGPTなどが回答を生成する際に、特定のキーワードと一緒に自社ブランド名も連想させるような最適化を行う。
LLMOはまだ新しい概念であり、確立された手法が少ないのが現状です。
しかし「AI検索の時代にどうブランド露出を高めるか」という大きなテーマに対して、LLMOの視点を持つことは競合との差別化につながる可能性があります。
実際、直近では「生成AIに聞いたら”おすすめの会社”として紹介されたので問い合わせをした」というケースも増えています。
ゼロクリック検索が増えても、AIの回答を通じて自社ブランドの認知を高める間接効果が狙えるため、積極的に学んでおく価値がある領域です。
SEO担当者が今後取り組むべきアクションプラン
ここまでの内容を踏まえ、「では具体的にどのようなアクションを取ればいいのか?」という視点で、明日から実践できるステップを提案します。
- 業務の見直しとAIが活用できる場所の選定
まずは自分のSEO業務を書き出し、自動化や効率化が期待できるタスクを仕分けします。たとえばメタタグの作成や記事の下書き、アクセス解析レポートの要約などから少しずつAI導入を試みることで、抵抗なく始められるでしょう。
- 生成AIツールを試用する
ChatGPT、Gemini、あるいは他のAIライティングツールなど、無料・低コストで使えるサービスから試してみましょう。「記事トピックに対するアウトラインの作成」「既存文章のリライト」など実際の業務で手を動かしてみることで、AIの得意分野や苦手分野が肌感覚で理解できます。
- コンテンツのE-E-A-T強化
AIで下書きを作ったとしても、最終的には人間が事実確認や専門性の付与を行い、信頼性の高いコンテンツに仕上げる必要があります。社内の専門家にインタビューを行う、実際の体験談を盛り込む、権威ある情報源を引用するといった工夫で、AIに差別化されない本物の価値を提供しましょう。
- 最新情報のキャッチアップ
月に一度は「AI×SEO」に関するニュースや事例をウォッチし、必要なアップデートを自社の戦略に取り入れられるよう準備します。特にGoogleの公式アナウンスや、業界有識者のブログなどをチェックしておくと、変化が起きた際にいち早く対応できるでしょう。
- 戦略提案にチャレンジ
AIとSEOを組み合わせた新しい施策を、自分がリーダー役になったつもりで考えてみましょう。上司やクライアントに対するミニ提案として共有すると、戦略思考とコンサルティング力が鍛えられます。失敗を恐れずに試行錯誤を続けることで、独自のノウハウを培えるはずです。
まとめ – 生成AI時代のSEOの課題と今後
最後に、本記事のポイントを整理して振り返りましょう。
- AIがもたらす変化
-
ChatGPTやAI Overviewの登場により、検索エンジン経由のクリックが減り、従来型のSEO施策だけでは流入を確保しにくくなっている。
- AIで効率化できる領域
-
コンテンツ制作、キーワード調査、定型業務などはAIを活用することで時間とコストを節約し、人間はより創造的・戦略的な業務に注力できる。
- AIでは代替できない人間の役割
-
ビジネス目標に基づく戦略立案、ファシリテーション、品質管理、ユーザーファーストの視点などは人間の強み。特にE-E-A-Tを高めるために専門性や実体験を提供することが鍵となる。
- 新スキルの重要性
-
プロンプトスキルやデータ分析のリテラシー、編集力、戦略思考、継続的学習など、生成AIと共存するために必須のスキルを身につける必要がある。
- LLMOへの注目
-
大規模言語モデルに自社情報を最適化する「LLMO」が今後のAI検索時代の重要テーマとなる。LLMs.txtの活用や引用しやすいコンテンツ設計など、新たな最適化の概念を学ぶ意義が大きい。
生成AIの台頭は、SEO担当者にとっては確かに大きな変化をもたらすトレンドです。しかし、それを脅威と捉えるかチャンスと捉えるかは自分次第ともいえます。
「AIをいかに使いこなし、人間にしかできない分野でどのように価値を高めるか」が、生成AI時代でも活躍し続けるための鍵といえるでしょう。
豊藏 翔太(トヨクラ ショウタ)
SEO会社「アイオイクス株式会社」の事業責任者を経てシンクムーブ株式会社を設立
現在は、シンクムーブ株式会社の代表取締役を務めながらアイオイクス株式会社フェロー及びCOUNTER株式会社 生成AIアドバイザーを兼務。
SEOやWebマーケティングの支援からAIを活用したセミナー、講演及び教育プログラムの企画、実施及び運営まで幅広くおこなっています。
書籍「AI時代のSEO戦略」の著者でもあり、生成AIを活用したSEOの第一人者として精力的に情報の発信を続けている
シンクムーブ株式会社 公式URL:https://thinkmove.jp/
Xアカウント:https://x.com/shotatykr
ぜひ、読んで欲しい記事
-
 SEO対策robots.txtとは?書き方と設定場所・確認方法を解説2026/02/25
SEO対策robots.txtとは?書き方と設定場所・確認方法を解説2026/02/252026/02/25
-
 SEO対策nofollowとは?設定方法と設定例・利用するケースと注意点を解説2026/02/25
SEO対策nofollowとは?設定方法と設定例・利用するケースと注意点を解説2026/02/252026/02/25
-
 SEO対策ECサイトのSEO対策|上位表示に必要な施策をすべて徹底解説2026/02/20
SEO対策ECサイトのSEO対策|上位表示に必要な施策をすべて徹底解説2026/02/202026/02/20
-
 SEO対策動画SEOとは?4つの効果と11の対策方法を解説2026/02/19
SEO対策動画SEOとは?4つの効果と11の対策方法を解説2026/02/192026/02/19
-
 SEO対策オーガニック検索/自然検索とは?流入を増やす方法を解説2026/02/16
SEO対策オーガニック検索/自然検索とは?流入を増やす方法を解説2026/02/162026/02/16
-
 SEO対策URL正規化とは?正規化の方法と注意点・必要な理由を解説2026/02/13
SEO対策URL正規化とは?正規化の方法と注意点・必要な理由を解説2026/02/132026/02/13